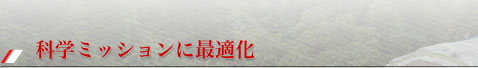 |
 |
||||
M-Vロケットの良さは、理学(衛星)と工学(ロケット)の世界が一体となって開発してきたという点にあります。衛星とロケットの開発が一体化し、科学と工学の研究者が共同で作り上げてきたのです。私たちはそれを「理工一体」と呼んでいますが、宇宙開発においてはひとつの理想の世界です。まずロケットを作り、後からその仕様に合った衛星が搭載されるのを待つのではなく、あらかじめこういう惑星探査をしたいとか、こういう天文観測をしたいというミッションの目的を念頭においてロケットを作ってきたわけです。つまり、M-Vロケットは、搭載する科学衛星の要求に柔軟に応えるように設計されたカスタムメイドのロケットであって、特に、上段ステージは衛星ごとに仕様を変えたりすることもできます。 M-Vロケットは、3段式ですが、必要に応じてキックモータ(4段ステージ)を追加することができます。搭載する衛星によって仕様を変えるのは、大きなところではこの第4段のキックモータと衛星のエンジンで、ロケットと衛星がトータルで最高の能力を発揮することができるように、両者をバランスよく設計していきます。基本となるベースは決まっていますが、毎回、搭載する衛星に対して最適なロケットを作っているわけです。ロケットが衛星ごとに作られていますから、今回「ASTRO-F」を打ち上げるのはM-Vロケット8号機、次に太陽観測衛星「SOLAR-B」を打ち上げるのがM-Vロケット7号機となっていて、衛星の打ち上げ順序が変わっても、衛星とロケットの号機の関係は基本的には変わることはありません。 M-Vロケットは地球周回低軌道に1.8トンの衛星を打ち上げる能力がありますが、地球の重力圏外に惑星探査機を飛ばすには、通常はもっと大きなパワーが必要です。M-Vロケットの場合には、科学ミッションと共同ですべての設計を最適化していて、例えば、軌道設計ひとつをとっても、1段目から4段目まで間髪を入れずに燃やした後、探査機を分離、探査機が自らのエンジンを噴射するところまで、ロケットと衛星を一体化して設計しています。それが完全に最適化されているため、ロケット自体のパワーは非力でも、遠くの宇宙まで500kg程度もの惑星探査機を飛ばすことができるのです。 さて、今回「ASTRO-F」を搭載したM-Vロケット8号機では、衛星分離後のロケットの姿勢制御を工夫しています。固体ロケットの場合、燃料の燃えかすから出るかすかなガスの勢いでロケットがわずかに加速するため、衛星を分離したあとにロケットが衛星に追突するという危険性があります。実際、過去にそういった事故がありました。そのため、衛星分離後、ロケットの姿勢を変えて衝突を回避します。ここで、「ASTRO-F」は繊細な赤外線望遠鏡を搭載していますから、ただ衝突を回避するだけでなく、ロケットから出るガスが衛星にかからないようにロケットの姿勢を制御します。まるで曲芸のようですが、ガスがかかって望遠鏡が曇ってしまったら大変ですから、分離の仕方など細かなところにも非常に神経を使っているのです。 このように、M-Vロケットは科学ミッションの要求にきめ細かく応えられる柔軟性をもったロケットといえます。そして、観測の目的から衛星ごとに固有で複雑な要求をもつ科学ミッションにとって、M-Vロケットのもつ柔軟性はとても大切な特性となっています。 1997年にM-Vロケット1号機の打ち上げが成功、翌年の1998年には3号機(2号機の打ち上げ時期は現在未定)の打ち上げにも成功し、このまま順調に進むだろうと思っていた矢先に事故が起きました。2000年2月10日に打上げた4号機の第1段モータが飛行中に故障し、搭載していたX線天文衛星を軌道に投入することができなかったのです。この事故は、ロケットモータの燃焼異常というかなり根本的なところで起きたものであり、構造、材料、推進、制御を始めとして、旧宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)が一致団結一丸となって原因究明に取り組みました。 解明された事故原因は、第1段モータのノズルスロートに構造上の欠陥があり、摂氏3000度という高温の燃焼に耐えられずに破損したということにありました。検討の結果、ノズルスロートの材料を全く新しいものに変更して設計を変えることにしました。同じ材料を使っていた3段目も合わせて変更し、これらの変更とその確認のための燃焼試験に約2年の歳月を費やしました。 一方、性能向上とコスト削減を目指して、第2段ステージを高性能の高圧燃焼モータに作り変えるという計画がもともとあり、事故対策と平行してこれを実施しました。この2段目の新規開発時にも、ノズルの材料が高圧燃焼で破損されるという問題が発生し、この解決にかなりの時間を費やしました。4号機の事故後の最初の打ち上げが2003年5月ですから、全ての問題を解決するのに3年あまりを要したことになります。私たちは、たとえ打ち上げのスケジュールを遅らせたとしても根本的に問題を解決するのだ、という態度で取り組み、徹底的に改良を施したわけです。 この姿勢が功を奏し、2003年5月にM-Vロケット5号機で小惑星探査機「はやぶさ」の打ち上げに成功することができました。続く6号機で、2005年7月にはX線天文衛星「すざく」の打ち上げにも成功しています。今回の8号機の打ち上げは、改良してから3機目となります。今回成功してはじめて、M-Vロケットの信頼性にも実績で胸が張れるのではないかという気持ちです。 ペンシル以来開発されてきたMシリーズロケットには研究教育という側面があり、M-Vロケットの開発においても性能最優先で極限まで工学技術を追求するというところがありました。今ではM-Vロケットの開発も基本的には一段落し、既に完成度の高い領域に達していますから、今後はより信頼性を追求するための工夫が必要だと思っています。M-Vロケットの外観は変わりませんが、中身は継続的に改良しています。例えば、ロケットに命令を送る際、これまでは1ヵ所でこの命令を受けていましたが、今では2ヵ所で命令を受けられるように指令系統を多重化するなど、設計改良を加えています。部品の構成を変えたり回路を変えることは、一度やれば終わりではなく、より信頼性が高くなるように継続して検討する必要があると思っています。 |

|
||||
|
|||||
