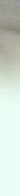 |

古くはTBS(当時)の秋山豊寛さんと菊地涼子さん、そしてJAXAの野口聡一宇宙飛行士も4週間の短期訓練をロシアで経験しています。ですが日本人として、ソユーズ宇宙船の運航にも関わる本格的な訓練を受けるのは、我々3人が初めてです。
ロシアでの訓練は、その背景に米ロの思想の違いまで垣間見せてくれる非常に貴重な経験でした。一般にNASAの宇宙飛行士養成プログラムは「タスク・オリエンテッド」で、ロシアのそれは「スキル・オリエンテッド」だといわれます。
NASAはタスク、すなわち場面場面に応じた業務を確実にこなす「確かさ」を宇宙飛行士に求めます。いろんな状況を想定して訓練プログラムを作成し、地上とも連携しながらそれを処理していく能力が重要とされます。
一方のロシアはスキル、つまり宇宙飛行士個人の知識や理解力、判断力を重視しています。背景にはこういう事情もあります。
ソユーズ宇宙船は1周90分で地球を回りますが、地上とコミュニケーションができるのは基本的にロシアの領土上空にいるときだけです。1周回当たり、長い場合は20〜30分間通信が可能といいますからやっぱりロシアは広いわけですが、もちろん状況によってはまったく通信できない周回もある。
そういうときには、宇宙飛行士が自分でトラブルに対処しなければなりません。ロシアの宇宙飛行士に、宇宙船をブラックボックスではなくシステムとして理解する能力と、操作のスキルが求められる理由のひとつはこれなんです。
3人乗りのソユーズ宇宙船を操縦するのは、コマンダー(船長)とフライトエンジニアです。フライトエンジニアには、船長とほぼ同じ作業を実行できるスキルが求められます。そのため我々の825時間にのぼる訓練でも、半分以上がソユーズのシステムを習得することに当てられていました。
「熱制御システム」「通信システム」「姿勢制御システム」など、ひとつのサブシステムの講義を終えるごとに、専門家による口頭試問が課せられます。こうした試験は、旧NASDAでの宇宙飛行士認定時の試験を除けば、私にとっては学生時代以来の経験でした。
どちらかといえば「単位を与えるため」だった学生時代の試験とは、まったく違う厳しさがありました。ガガーリンセンターのロシア人の宇宙飛行士候補生たちは、仲間うちで常に成績を公開され、それを意識しながら訓練の日々を送っています。
私も大学受験のときは、大手予備校の合格判定が最低ランクだったのにショックを受けて死ぬ気で勉強した思い出がありますが(笑い)、ロシアでの取り組みはそれ以上だったかもしれません。
|
 |
2/4 |
 |
|
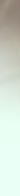 |