ESAは、日本との協力が重要だと考えています。NASAやアメリカ政府との歴史的共同ミッションを経た私たちは、数年前、優れた技術・人材を有し、ヨーロッパとの共同作業に大変興味を示していたアジアの国に目を向けてみることにしたのです。将来の共同ミッションを実現させるために、科学分野を中心に、研究者の交流、データの共有、地上施設の共同利用などが徐々に行われています。
最終的に目指す大規模なミッションは、地球型惑星のひとつである水星に、ESAとJAXAそれぞれが開発した探査機を計2機送るという、2012年に打ち上げが予定されているベピ・コロンボ計画です。
JAXAは技術の面でもパートナーとしても素晴らしく、私たちは日本との協力関係に大変満足しています。今後も多くのプロジェクトを通して、より良い関係が築き上げられることを願っています。
|
 |
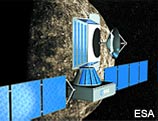 |
| 水星表面探査機(MPO)。ESAによる3軸制御方式の探査機 |
|
 |
 |
| 水星磁気圏探査機(MMO)。JAXAが提供するスピン衛星で、水星の磁気圏とプラズマ圏の調査、太陽系の中で最も表面温度の高い惑星である水星と太陽風の関係を研究することが目的 |
|

