
Q.宇宙三機関、宇宙開発事業団(NASDA)、航空宇宙技術研究所(NAL)、宇宙科学研究所(ISAS)が統合してJAXAが発足しましたが、統合の効果、行革の効果をどう思われますか?
A.それぞれの歴史的な背景や、違ったミッションをもった三つの団体が一緒になる。これまでもこの三つになるまでにいくつかの合併はあったようですが、今度のJAXA誕生については、行革の一環として特殊法人すべてを抜本的に見直すという背景があります。
多くの公益法人、特殊法人のそもそもの目的が時間と共になくなってしまったか、あるいは陳腐化してしまったか、あるいは変わったか、そういうことを踏まえての見直しです。二つを一つにしたり、三つを一つにして、合理化、効率化を図ろうとすることは、国民のお金をベースにしているのですから、もちろん必要なことで、私は決して否定する気持ちはありません。
しかし、宇宙や航空、ロケットという、いろいろな意味で国民の夢へとつながる部分、そして日本だけでなく世界においても、大きな意味での発展へと結びついている分野の機関が一緒になるということについては、効率化も大切ですが、統合による新しい成果をあげることも大切だと思います。
単純な言い方をすると、1+1+1が3ではなく、それが「4」になったり「5」になったりする。個々では出来なかったことが、三つ一緒になることによって、何か新しいものが出来る。それが全く新しい分野のことなのか、あるいは、今まで三つがそれぞればらばらで行っていたために、思い切って集中して出来なかったことが、一緒になることで、密度が濃いものが出来るとか。そういう部分の成果が上がることが、とても大切なことだと私は思いますね。
民間の企業の中でも、会社の中で部門を一緒にしたり、会社と会社を一緒にするということを行いますが、やはり同じことが言えます。その中で特に注意しなければならないのは、統合したことで、アウトプットの質が下がらないようにすることです。
これは一番目に見えやすいことですが、例えば、二つの部門に各10人ずついたとします。その10人、10人いた計20人のスタッフを一つにまとめれば、同じ仕事が15人で済むということになり、5人減らしました。その時、10と10で20出ていたアウトプットも5人分減ってしまうと何もなりません。特に質が下がっては。
やはり、三つ一緒になったからこそ出来ること、仕事の中身、あるいは広がりなど。その点がきちんとフォローされるようにすることが大切だと思います。
|
|
 |

 |
富士ゼロックス株式会社 代表取締役会長 1933年生まれ。'56年慶應義塾大学経済学部卒業。 '58年米ペンシルベニア大学ウォートンスクール修了後、富士写真フイルム入社。'68年富士ゼロックスに転じ取締役販売部長、'78年取締役社長を経て、 '92年代表取締役会長に就任、現在に至る。その他、科学技術・学術審議会委員、日本ユネスコ国内委員会委員、社団法人経済同友会終身幹事、三極委員会アジア太平洋委員会委員長、学校法人国際大学理事長、学校法人慶應義塾理事・評議員、日本惑星協会副会長等を兼任。
※小林陽太郎氏は、2015年9月5日に逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。 |

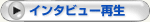
ファイルサイズ:11MB
フォーマット:MPEG |



