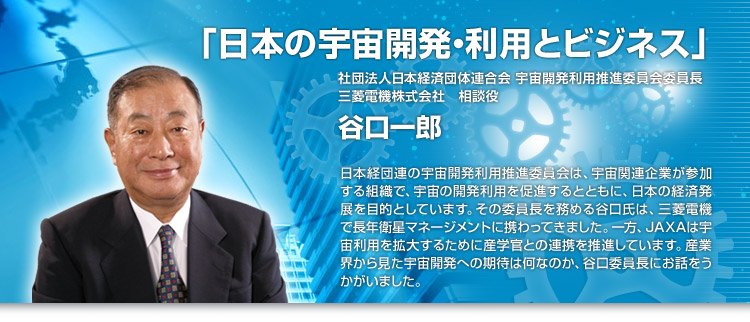
谷口一郎(たにぐちいちろう)
社団法人日本経済団体連合会・宇宙開発利用推進委員会委員長。三菱電機株式会社 相談役。工学博士。
1936年、兵庫県生まれ。1959年、京都大学理学部物理学科卒業後、三菱電機株式会社に入社し、中央研究所に配属。1971年、鎌倉製作所転任、管制システム部長、飛しょう体部長、通信機製作所副所長、鎌倉製作所所長を経て、1991年、取締役 電子システム事業副本部長に就任。以降、常務取締役 電子システム事業本部長、専務取締役 電子システム事業本部長を経て、1998年に取締役社長に就任。2002年に取締役会長、2006年4月に取締役相談役、同年6月に相談役となり、現在に至る。1997年から(社)経済団体連合会(現(社)日本経済団体連合会)・宇宙開発利用推進会議会長(現宇宙開発利用推進委員会委員長)を務める。
Q.経団連の宇宙開発利用推進委員会とは、どのような委員会なのでしょうか?
産業界の中で宇宙開発・利用をどのように進めていくかを調査研究し、政策に提言することを目的に設立された委員会です。1961年、宇宙開発事業団(1969年創設/現JAXA)が発足される8年前に設立されました。宇宙開発の企画立案をするための企画部会と、宇宙開発をどのように利用に結びつけていくかを考える利用部会で運営し、現在は宇宙関連メーカー、宇宙利用企業が56社参加しています。毎年、日本の宇宙開発を促進させるための政策提言を行うほか、宇宙開発に関する論文などを掲載した小冊子を発行するなど広報活動による普及啓発にも務めています。
Q.日本にとって、宇宙開発はどのようなものでしょうか?
日本政府は科学技術創造立国を目指し、科学技術政策の基本的な枠組みを定める「科学技術基本法」を1995年に施行しました。資源のない日本を支えるのは、科学技術しかありません。科学技術の発展は私たちにとって非常に大きなテーマです。特に宇宙開発は最先端の技術ですから、それを推進することは国益につながり、将来の日本を支える若い人材を育てる意味でも大切だと思います。だからこそ、アメリカやヨーロッパ、ロシア、中国、韓国、インドなどの諸外国は、宇宙開発利用を重要な国家戦略として位置づけています。また、宇宙開発が外交手段の一つになることもあります。例えば、最近の中国は、アフリカなどの発展途上国に宇宙関連機器、設備、ノウハウ等を提供する見返りに、エネルギー資源の確保を確約してもらう提案などを行っています。同じように、日本も宇宙開発を国家戦略として大いに進めるべきだと思います。
しかし、科学技術基本法の規定に基づいて策定された、第2期科学技術基本計画(2001年〜2005年を対象)では、宇宙開発予算が他の分野よりも削減されてしまいました。科学技術基本計画とは、我が国が取り組むべき科学技術政策を具体化したもので、5年に1度策定されます。第2期の期間中に予算が減ったことで、宇宙関連の企業で働く技術者の方たちが約3割減少しました。これはとても残念なことです。日本には部品を含め、信頼性や性能で世界に誇れる技術がたくさんあります。それがみすみす消えてしまうようなことがあってはなりません。そこで、私ども経団連の宇宙開発利用推進委員会やJAXA、宇宙開発委員会が、総合科学技術会議をはじめとする関係省庁に、宇宙開発の重要性を理解していただけるよう請願しました。そして、2006年3月に閣議決定された第3期科学技術基本計画(2006年〜2010年を対象)では、幸いにも宇宙関係を国家の推進4分野の1つに位置づけていただきました。この4分野とは、「エネルギー」「ものづくり技術」「社会基盤」「フロンティア」です。宇宙は「フロンティア」の中に含まれています。さらに、総合科学技術会議の中で決定された5つの国家基幹技術の中にも、宇宙輸送システムと海洋地球観測探査システムの2つの宇宙関連技術が含まれました。このように、宇宙開発の重要性が認識されはじめたことで、これからは予算状況が好転するだろうと期待しています。私たち産業界も頑張っていきたいと思います。
Q.日本の宇宙開発は、諸外国に比べて国のイニシアティブが低いと思われますか?
宇宙開発を国家としてどう扱うかを示すのは非常に重要なことです。アメリカやヨーロッパ、ロシア、中国、韓国、インドといった宇宙開発推進国では、宇宙開発を国家戦略として強く推進していますから、宇宙に関する法整備もきちんとできています。ところが、日本には宇宙利用に関する法律がありません。そこで、私たち経団連の宇宙開発利用推進委員会は、2006年6月の政策提言で、宇宙基本法の制定を強く支持すると表明しました。従来の宇宙開発は、開発だけに重点を置いてきたと思いますが、宇宙基本法では、安全保障、産業化、研究開発という3つを柱にしています。さらに、総理大臣が最高責任者となる宇宙開発戦略本部を設立することも提言しています。今年も7月中旬に提言を発表することにしていますが、宇宙基本法の早期制定により、一元的な推進体制を整備し、宇宙産業化の円滑な推進をはじめバランスのとれた宇宙開発利用の必要性を訴えることにしています。日本の宇宙開発利用を新たなステージに引き上げ、宇宙新時代を迎えるためには、宇宙基本法が不可欠です。(※注)
また、日本では、宇宙に関する広報活動が低いことも問題だと思います。国民の皆さんに宇宙開発や科学に関する活動をお知らせし、関心を持っていただくことはとても重要です。しかし、経団連の場合もそうですが、年間の事業計画を立てる時に広報計画が後回しになってしまいます。衛星やロケットが打ち上がった時にはニュースで取り上げられますが、それ以外でJAXAの仕事が一般に紹介されることはほとんどありません。広報が重要だと分かっていても、どのように国民にアピールしていくかは大変難しいことです。そういう意味では、JAXAのホームページは1つの手段ではありますが、もっと国家レベルでの広報活動が行われるようになると素晴らしいと思います。そうすれば、国民がもっと宇宙を身近に感じてくれるようになると思います。通信や放送、天気予報、カーナビといったあらゆる分野で宇宙が生活に使われていることは、皆さんも知っているはずですが、もっと積極的に宇宙活動を広報していくべきだと思います。
※本インタビュー後、2007年6月20日に宇宙基本法案が国会に上程された。
