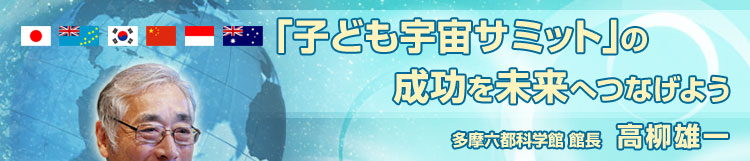
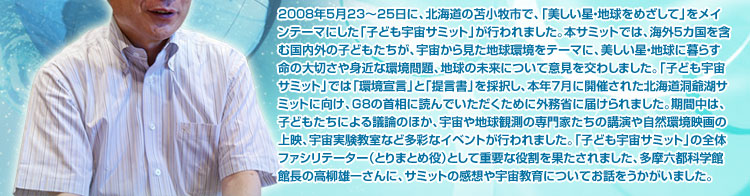
高柳 雄一(たかやなぎ ゆういち)
多摩六都科学館 館長
1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年、東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)に入局。主に科学系シリーズ番組をてがける。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフ・プロデューサーを歴任、1994年からNHK解説委員。2001年9月、高エネルギー加速器研究機構教授に就任。2003年4月に電気通信大学共同研究センター教授に就任し、NHK部外解説委員を兼務。2004年4月から多摩六都科学館館長を務める。小惑星No.9080にTakayanagiと命名される。主な著書に「創造の種」(NTT出版)、「火星着陸」(NHK出版)、「天体の狩人」(ベネッセ・コーポレーション)など。2008年5月に北海道苫小牧市で行われた「子ども宇宙サミット」の全体ファシリテーターとして、サミットのとりまとめを行う。
多摩六都科学館 館長
1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年、東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)に入局。主に科学系シリーズ番組をてがける。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフ・プロデューサーを歴任、1994年からNHK解説委員。2001年9月、高エネルギー加速器研究機構教授に就任。2003年4月に電気通信大学共同研究センター教授に就任し、NHK部外解説委員を兼務。2004年4月から多摩六都科学館館長を務める。小惑星No.9080にTakayanagiと命名される。主な著書に「創造の種」(NTT出版)、「火星着陸」(NHK出版)、「天体の狩人」(ベネッセ・コーポレーション)など。2008年5月に北海道苫小牧市で行われた「子ども宇宙サミット」の全体ファシリテーターとして、サミットのとりまとめを行う。
Q.「子ども宇宙サミット」とは、どのような取り組みなのでしょうか?

子ども宇宙サミットの開会式
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)
また、今年は日本の北海道洞爺湖町でG8サミットが開催され、世界の指導者たちが環境やエネルギーの問題を議論することになっていましたので、その問題を子どもの視点から話し合い、将来どう活動していくべきかという提言書をつくり、G8サミットに訴えかける機会にしたいという目的もありました。
Q. 何歳ぐらいの子どもたちが集まり、どのように話し合いが行われたのでしょうか?

分科会のようす
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)
小学5年生から高校2年生までの子どもたちで、国内からは、応募95名から選考された20名、海外からは9名が参加しました。韓国、中国・香港、インドネシア、オーストラリア、そして、南太平洋に位置するツバルの子どもたちです。ツバルはサンゴ礁からできた島国で、温暖化による海面上昇により、国が海に沈んでしまうかもしれない問題に直面しています。
話し合いは、テーマを設定して分科会で行われました。「環境問題で失うもの」「人間にできること」「宇宙に期待する役割」「科学技術の役割」「子どもの役割」という5つのテーマで、男女の数はだいたい半々になるように、また、年齢もうまく散らばるようにグループをつくり、大人がついて通訳をするなどサポートしました。私が参加したグループでは、「人間にできること」について話し合いましたが、子どもの意見を尊重しつつ、子どもが困った時に助け船を出すよう心がけました。グループのまとめ役や書記も子どもたちが話し合いで決めて、全員がそれぞれ役割を持てるよう工夫しながら進めていきましたので、内容的にも充実した議論が展開されたと思います。話し合いの結果は、「わたしたちの願い」という環境宣言と、提言書としてまとめられました。
* 関連リンク:環境宣言と提言書の内容はこちら「子ども宇宙サミット」特設サイト
Q.子どもたちの話し合いで特に印象に残っていることは何でしょうか?

分科会で子どもたちと話す高柳氏
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)