Q. 高柳さんから見て、日本の子どもと海外からの子どもたちの違いはありましたか?

子ども宇宙サミットの参加者
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)
グループで話し合うほかに、海外の子どもが自分たちの置かれている状況を発表する機会があり、とても立派な内容でした。海外の子どもたちは、日本の子どもに比べると、プレゼンテーションの訓練をしっかり受けているように思います。また、海外の子どもたちは、自分の生活に密着した発表をしました。例えば、今回参加したオーストラリアの子どもは、現実に、地球温暖化によるサンゴの白化現象や干ばつを経験していますし、ツバルの子も、海面上昇によって国が海に沈んでしまうかもしれないという危機に面しています。一方、日本の子どもたちは、そういった環境問題をテレビやインターネットを通してしか見て来なかったので、同じ子どもの仲間から、実体験として聞けたのは、ものすごくインパクトがあったと思います。日本の子どもたちは、節約や省エネが必要であることは学校などで教わって「こと」としては分かっていますが、それが現実の環境問題にどうつながっていくのか、また、自分たちのこれからの生き方にどう関わっていくのかということを、自分の身になって考えていなかったことに気づかされたのではないでしょうか。
Q. サミットに参加した子どもたちの反応はいかがでしたか?

ジョーンズ博士の基調講演
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)
また、ジョーンズ博士が中心になって、地球の地図を描くゲームを行いましたが、どの子どもも自分が住んでいるところを真ん中にして描きます。日本の子どもは日本列島から描き、オーストラリアの子はオーストラリアから描くのです。このように、みんなで一緒に地図を描くという作業を1つ取っても、自分たちの視点が、ある意味でとても自分中心に偏っているというのを、子どもたちは実感したようです。地球上にはいろいろなコミュニティーがあり、そのコミュニティーの人たちが、自分たちの住んでいる世界をどのようにとらえているかを知ることは、とても大事だと思いますので、そういう意味で、今回のサミットは十分に機能したと感じました。
ただ、何といっても、子どもたち同士が議論をしたことが重要だったと思います。会場で講演を聞くと、知識として残りますが、それに基づいて議論し、相手に意見を投げてキャッチボールすることが、本当の意味での体験になって、子どもたちに大きな影響を与えたと思います。
Q. 今回の経験は、子どもたちの今後にどのように活かされていくと思いますか?

インターネット中継に挑戦する子どもレポーター
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)
一番感じたのは、日本の子どもたちだけで話しているのと、海外の子どもたちが加わるのとでは、全然違うということです。自分たちの住む世界とは違う世界が別にあって、どこにでもいろいろな問題があるということを子どもたちは知りました。しかし、それはどこかで共通の問題であり、それに対する取り組みも、ある意味で一緒にできるのだという連帯感を、子どもたちはしっかり持って帰ったと思います。このような経験によって、子どもたちは視野を広げ、世界の共通の課題として地球の問題をとらえることができるようになったでしょう。
また、サミット会場には日本宇宙少年団で活動しているような子どもたちがレポーターとして集まり、子ども宇宙新聞を発行し、子ども宇宙サミットの進行状況をインターネットでリアルタイムに紹介しました。このように、子ども同士の共有をどうやって広げていくかという取り組みも行われたわけですが、サミットに参加した子どもだけでなく、レポーターとして参加した子どもたちにも大きな影響を与えたと思います。さらに、手伝いをした大人たちが、子どもたちから刺激を受けた部分も相当あると思います。
Q. 今後「子ども宇宙サミット」は、どのような展開をしていくのでしょうか?
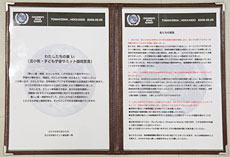
子ども宇宙サミットで採択された提言文
(提供:YAC(財)日本宇宙少年団)
今回のサミットは北海道苫小牧市の協力で行いましたが、今度は別の地方自治体の方が手を挙げていただき、そこに世界から子どもたちが集まって、自分たちが置かれている問題をお互いに共有し、提言してほしいですね。地球環境問題は世界共通の課題ですから、世界中の子どもたちが集まって話し合うことは、ますます重要になってくると思います。今回提言した子どもたちもやがて大人になるわけですから、次の子どもたちが、また子どもの視点で話し合うというように、世代をバトンタッチしてずっとつないでいくという意味でも、「子ども宇宙サミット」を定期的に続けてほしいと思います。