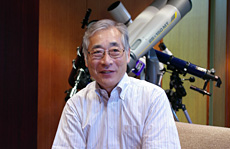Q. 高柳さんは多摩六都科学館の館長をなさっていますが、科学館の役割は何だと思いますか? 子どもたちの教育に、宇宙や科学をどのように活かしていけばよいとお考えですか?

多摩六都科学館
私たちの世界では何事も自分とどこかでつながっているのです。自分の住んでいる世界にきちんと興味を持つことは、生きていくうえで必要な知恵だと思います。その大事な知恵を手に入れるためにも、科学が見つけてくれた世界とのつながりを小さい頃から体験するなり、味わうことはとても大切です。その子どもが将来科学者にならなくても、例えば、人間の営みのなかで、「科学という活動が生きていくうえで支えになっている」と思うだけで、その国の文化にとって、科学は健全に成長していくと思います。そういう“きずな”“つながり”を体験してもらうのが、科学館の役割ですし、そういう意味で、宇宙や科学を子どもたちの教育に活かしていきたいと思います。
Q. 多摩六都科学館での取り組みで特徴的なものは何でしょうか?

多摩六都科学館の宇宙分野の展示室
いろいろありますが、例えば、宇宙関係では、国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」の実物大模型や、スペースシャトルのコックピットの3分の1の模型、「ムーンウォーカー」という月面と同じ6分の1 重力の世界が体験できる施設のほか、直径27メートルの大きなプラネタリウムがあります。プラネタリウムでは毎日生解説と全天周映画を上映しています。科学館では宇宙のほか、地球や生命などの科学を5つのゾーンに分けて展示していますが、どの分野も、体験できる場をたくさん提供できるよう工夫をしています。例えば、科学館の周りの雑木林の葉っぱの裏には小さいプランクトンがついていますが、それを科学館にある学習室の顕微鏡で見ることができます。子どもたちは、自分たちの周りにあるものを、少し視点を変えて見ることによって、そこにマクロやミクロの違った世界があることを知り、それが実に豊かであることに気づきます。やはり、知識というのは、体験して得られることが多いんですね。体験するということは、身体で見ると同時に、心でも見ているのです。サン・テグジュペリの「星の王子さま」という有名なお話の中に、「心で見なきゃ本物は見えないよ」という有名な言葉がありますが、その通りだと思います。
先ほど「高齢者の方に星空の話をした」と申し上げましたが、科学館にはいろいろな世代の方がいらっしゃいます。最近は、お孫さんとおじいさんが一緒に星空を見る機会はほとんどないと思いますが、科学館のプラネタリウムに来れば、疑似体験ではありますが、お孫さんと一緒に星空を楽しむこともできるんですね。多摩六都科学館では、七夕の時期に、願い事を書いて笹に飾るといった催しも行っていますが、そういった昔からの行事を通して、世代とのつながりを大事に保っていけるような、そういう場でもありたいと思っています。
Q. 高柳さんは今後どのような活動をしていきたいですか?