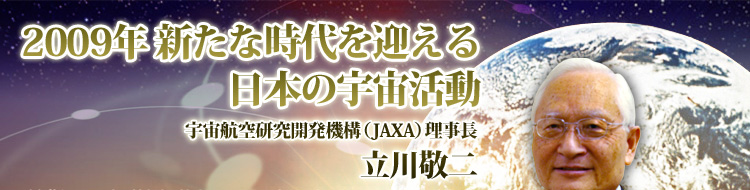

Q. 昨年を振り返って、どのような一年でしたでしょうか?また、昨年のJAXAの成果で、国内外で注目されたのはどのようなミッション、プロジェクトでしょうか?
昨年を振り返ると、特に3つの分野で大きな成果があったと思います。
1つ目は宇宙利用の分野で、2006年に打ち上げた陸域観測技術衛星「だいち」が、災害監視という観点で世界的に大きな貢献をし、中国を初めとするアジア各国から感謝状等をいただきました。昨年末にはユネスコ(国際連合教育科学文化機関)から、「だいち」を利用した世界遺産の監視保護が提案され、アジアを中心とした10か所の世界遺産を年2回程度撮影し、その情報をユネスコに提供することになりました。また、昨年は超高速インターネット衛星「きずな」の打ち上げを行い、衛星通信としては世界最速の1.2Gbpsでの通信に成功しました。実利用に向けた「きずな」の実験も始まり、今後はこれらの高い技術力を実証した衛星の利用方法の開拓が重要だと思います。
2つ目は宇宙探査関係で、2007年に打ち上げた月周回衛星「かぐや」が大きな成果を上げました。特に、ハイビジョンカメラによって撮影された、「満地球の出・入り」の映像は全世界に向けて公開され、好評を博しました。「かぐや」の本来の目的である科学ミッションについても、所期の観測目標をほぼ達成し、昨年末から後期運用に入っています。これまでの主な科学的成果は、レーザー高度計のデータを元に、国立天文台、国土地理院と協力して作成した月の詳細な地形図や、地形カメラのデータから、アポロ15号の噴射によって生じた痕跡を確認したり、月の裏側のマグマの噴出活動が長期間続いたことや、永久影の底の表面に氷としての水が存在しなかったことを突き止めました。「かぐや」の成果は、アメリカの科学雑誌「サイエンス」でも発表されています。
3つ目は、国際宇宙ステーション(ISS)です。昨年は、日本初の有人宇宙施設となる「きぼう」日本実験棟が宇宙に設置されるという、画期的な年になりました。3月にまず土井隆雄宇宙飛行士が「きぼう」の船内保管室を、6月には星出彰彦宇宙飛行士が船内実験室とロボットアームをISSに取り付けました。8月からは本格的な宇宙実験が「きぼう」で始まり、これからいろいろな成果が期待されます。
昨年を振り返ると、特に3つの分野で大きな成果があったと思います。
1つ目は宇宙利用の分野で、2006年に打ち上げた陸域観測技術衛星「だいち」が、災害監視という観点で世界的に大きな貢献をし、中国を初めとするアジア各国から感謝状等をいただきました。昨年末にはユネスコ(国際連合教育科学文化機関)から、「だいち」を利用した世界遺産の監視保護が提案され、アジアを中心とした10か所の世界遺産を年2回程度撮影し、その情報をユネスコに提供することになりました。また、昨年は超高速インターネット衛星「きずな」の打ち上げを行い、衛星通信としては世界最速の1.2Gbpsでの通信に成功しました。実利用に向けた「きずな」の実験も始まり、今後はこれらの高い技術力を実証した衛星の利用方法の開拓が重要だと思います。
2つ目は宇宙探査関係で、2007年に打ち上げた月周回衛星「かぐや」が大きな成果を上げました。特に、ハイビジョンカメラによって撮影された、「満地球の出・入り」の映像は全世界に向けて公開され、好評を博しました。「かぐや」の本来の目的である科学ミッションについても、所期の観測目標をほぼ達成し、昨年末から後期運用に入っています。これまでの主な科学的成果は、レーザー高度計のデータを元に、国立天文台、国土地理院と協力して作成した月の詳細な地形図や、地形カメラのデータから、アポロ15号の噴射によって生じた痕跡を確認したり、月の裏側のマグマの噴出活動が長期間続いたことや、永久影の底の表面に氷としての水が存在しなかったことを突き止めました。「かぐや」の成果は、アメリカの科学雑誌「サイエンス」でも発表されています。
3つ目は、国際宇宙ステーション(ISS)です。昨年は、日本初の有人宇宙施設となる「きぼう」日本実験棟が宇宙に設置されるという、画期的な年になりました。3月にまず土井隆雄宇宙飛行士が「きぼう」の船内保管室を、6月には星出彰彦宇宙飛行士が船内実験室とロボットアームをISSに取り付けました。8月からは本格的な宇宙実験が「きぼう」で始まり、これからいろいろな成果が期待されます。

超高速インターネット衛星「きずな」
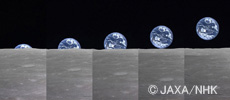
「かぐや」が撮影した「満地球の出」

「きぼう」日本実験棟(提供:NASA/JAXA)
Q. 昨年の5月に宇宙基本法が制定されましたが、これによって日本の宇宙戦略は、どう変わるのでしょうか?宇宙基本法では、JAXAを含む宇宙機関の見直しが書かれていますが、JAXAはどう変わるのでしょうか?

宇宙基本計画には、宇宙開発利用の目的として、(1)国民の生活を豊かにすること、(2)安全保障への貢献、(3)外交の推進、(4)産業の育成、(5)惑星探査や有人宇宙活動など、人類の夢や次世代への投資といった、主に5つの柱がありますが、JAXAはこのほとんどに関連します。ですから、これまで以上にJAXAの体制をより充実、強化する必要があると思います。その詳しい内容については、現在ワーキンググループを作って検討を進めており、今年の春から夏にかけて具体化される予定です。JAXAは、新しい宇宙基本法の精神に沿って、今まで培ってきた技術や経験を最大限に活用し、日本の宇宙利用に大きく貢献していきたいと思います。
Q. 今年はまず1月に温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」の打ち上げがありますが、この衛星について、国内外の期待度はいかがでしょうか?
「いぶき」の目的は、地球温暖化の主要因となっている二酸化炭素やメタンガスの全球観測です。これまでの地上観測では観測点が約280地点しかなかったのに比べ、「いぶき」の観測点は約56,000地点もあり、世界中の温室効果ガスの濃度分布を把握できます。「いぶき」と同時期にNASAが打ち上げる炭素観測衛星「OCO(Orbital Carbon Observatory)」との観測データの相互交換も予定しており、地球温暖化の予測精度の向上に向けて、世界各国からの関心が高まっています。
「いぶき」は、世界76カ国、EC及び56国際機関で進められている「全球地球観測システム(GEOSS)」の1つであり、昨年7月の洞爺湖サミットでも、GEOSSの加速化が言及されています。「いぶき」の観測によって、国連気候変動枠組条約や京都議定書を含めた、地球温暖化対策に大きく貢献できると期待されています。
関連リンク:温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」
「いぶき」は、世界76カ国、EC及び56国際機関で進められている「全球地球観測システム(GEOSS)」の1つであり、昨年7月の洞爺湖サミットでも、GEOSSの加速化が言及されています。「いぶき」の観測によって、国連気候変動枠組条約や京都議定書を含めた、地球温暖化対策に大きく貢献できると期待されています。
関連リンク:温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」
 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」