
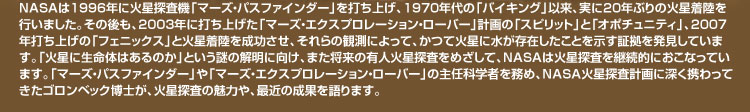
マシュー・ゴロンベック(Matthew Golombek)
NASAジェット推進研究所(JPL)火星探査計画主任研究員。惑星地質学者。
1976年、ラトガース大学卒業。1981年、マサチューセッツ大学で地質学/地球物理学の博士号を取得。アメリカ・テキサス州ヒューストンの「月惑星研究所」を経て、1983年よりジェット推進研究所の研究員となる。1997年に火星に着陸した「マーズ・パスファインダー」の科学主任をはじめ、2004年に着陸した「マーズ・エクスプロレーション・ローバー」では、科学主任として着陸地の選択担当チームを率いる。現在は火星の研究のほか、火星探査機の着陸地選定の研究員として、2011年に打ち上げ予定の火星探査機「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」の着陸候補地の選定を行う。共著としてナショナルジオグラフィック協会出版の「火星:解き明かされる赤い惑星の謎」がある。
NASAジェット推進研究所(JPL)火星探査計画主任研究員。惑星地質学者。
1976年、ラトガース大学卒業。1981年、マサチューセッツ大学で地質学/地球物理学の博士号を取得。アメリカ・テキサス州ヒューストンの「月惑星研究所」を経て、1983年よりジェット推進研究所の研究員となる。1997年に火星に着陸した「マーズ・パスファインダー」の科学主任をはじめ、2004年に着陸した「マーズ・エクスプロレーション・ローバー」では、科学主任として着陸地の選択担当チームを率いる。現在は火星の研究のほか、火星探査機の着陸地選定の研究員として、2011年に打ち上げ予定の火星探査機「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」の着陸候補地の選定を行う。共著としてナショナルジオグラフィック協会出版の「火星:解き明かされる赤い惑星の謎」がある。

火星(提供:NASA/JPL-Caltech)
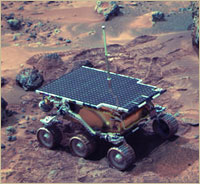
火星を探査中のマーズ・パスファインダーのローバー(提供:NASA/JPL-Caltech)

双子の火星探査機スピリット/オポチュニティ(提供:NASA/JPL-Caltech)

エアロシェルに入った探査機が、パラシュートを使って火星に着陸。(提供:NASA/JPL-Caltech)
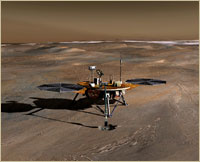
火星探査機フェニックス(提供:NASA/JPL-Caltech)
Q.博士にとって、火星探査の魅力は何でしょうか?
火星探査の魅力は、誰も知らなかったことを発見することです。探査はこの一言に尽きます。私たち人類は、未知なるものに対する探求心を生まれながらに持っています。私たちは、ほかに存在するものとどう違うのか、また、それらにどう適応できるのか、知りたいのだと思います。
Q.現在、博士は、火星のどのようなことを研究していますか?
私は、ローバー(移動式探査機)科学チームに所属しています。ローバーが火星の地表を実際に移動して観測した結果と、これまで軌道上から取得した火星地表の画像などのデータを関連づける研究をしています。探査機の着陸後は、軌道からの観測によって得た火星の地表に関する知識が正しかったかを確かめます。最近は、火星の気候を研究するプロジェクトにも参加しています。火星の気候を理解するため、火星表面がどれくらいの速さで侵食し変化していったかを調べます。遠い昔、火星には地球と同じように水があり雨も降っていたのならば、どのようなスピードで侵食され、今のような激しく乾いた地表になっていったのかを研究します。
また、次の火星探査機の着陸地を選ぶのも、私の仕事です。探査機の着陸地を決めるときは、軌道から取得されたデータをもとに、安全に着陸できる地表を予測します。そのために、岩石の分布についても研究しています。地表の岩石は、探査機の着陸の際に事故を引き起こす原因になりかねません。また岩石がたくさんありすぎると、ローバーの走行を妨げます。NASAは、2011年に火星探査機「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」を打ち上げる予定ですが、現在、その着陸候補地の選定を行っています。候補地を決めるためには、火星で撮られた高解像画像などを利用し、可能な限り調べます。軌道からの観測で、地表の様子を正確に予測できるようになれば、着陸地選択の成功率が上がります。私はこれまで、「マーズ・パスファインダー」、「スピリット」、「オポチュニティ」という3機の探査機の着陸地点の選択にかかわってきましたが、どれも予測は当たりました。今後も火星探査を続けていくためには、着陸の成功率を上げることはとても重要なのです。
Q.新しい探査機の着陸地を決めるにあたって、重要なことは何でしょうか?
一番大切なのは、着陸機とローバーにとっての安全性です。失敗する可能性が高い場所に着陸機を送り込むのは、誰にとっても良くないですよね。科学的成果を得るためには、着陸に成功しなくてはいけません。そのためにも、地表を把握することはとても大切です。安全な場所を選ぶためには、その場所の安全性を確信できるまで研究に研究を重ね、できることはすべてやり尽くします。
すべての火星着陸機はエアロシェル(探査機を火星大気突入時の高熱から守る外殻)とパラシュートを使いますが、その際重要なのが、着陸地点の高度(標高)です。一定の高度まで降下しないとパラシュートを開くことができません。ですからオリンポス山頂のような高地には、探査機を着陸させることができないのです。ですから着陸地点を選ぶ時には、高度(標高)がとても重要な要素となります。
次に重要なことは、地表面の堅さです。火星には凝集力の低い塵の堆積物がいくつかあると考えられていますが、それが厚く積もっている可能性があります。そのような場所に探査機が着陸したら、すっぽり見えなくなるまで沈んでしまうかもしれません。また、塵の堆積物の上に着陸することは、太陽電池パネルにとってもよくありません。塵がパネルの上を覆ってしまい、パワーが落ちてしまうからです。岩がゴロゴロある場所も、探査機がその上に着陸したらダメージを受けてしまうのでだめです。険しい急斜面も、衝突したり、転がり落ちてきちんと着陸できない可能性があるので良くないですね。これらのことが、着陸地点を選ぶ上で注意しなければならない点です。あとは探査機の設計エンジニアから、それぞれの着陸機とローバーの必要条件を教えてもらい、ふさわしい着陸地点の検討を開始します。
一方、太陽エネルギーを動力としている探査機の場合、長期使用を考えているなら、太陽エネルギーを一番多く受けられる場所を選ぶことも大切です。そうなると、一番太陽に近く、一番暖かい場所ということで、赤道付近ですね。火星探査機「フェニックス」のように極地に着陸すると、日照不足により太陽電池が切れ、ミッションが早く終了してしまいます。ですから、着陸地を選ぶときは緯度も重要です。
さらに、科学的な面を考える必要もあります。例えば、このミッションが達成しようとしていることは何なのか。どのような観察機器が搭載されるのか。調べたい物質が着陸地にあるか、といったことも考えて着陸地点を決めます。もし古代の火星環境の研究が目的ならば、古代の岩石が地表に露出している場所に行きたいですよね。着陸機にはそれぞれ異なる科学ミッションがあり、それに応じて設計されています。もちろん観測機器も異なります。ですから着陸地の選択には、科学的な面と安全性の2つのことを主に考慮します。
火星探査の魅力は、誰も知らなかったことを発見することです。探査はこの一言に尽きます。私たち人類は、未知なるものに対する探求心を生まれながらに持っています。私たちは、ほかに存在するものとどう違うのか、また、それらにどう適応できるのか、知りたいのだと思います。
Q.現在、博士は、火星のどのようなことを研究していますか?
私は、ローバー(移動式探査機)科学チームに所属しています。ローバーが火星の地表を実際に移動して観測した結果と、これまで軌道上から取得した火星地表の画像などのデータを関連づける研究をしています。探査機の着陸後は、軌道からの観測によって得た火星の地表に関する知識が正しかったかを確かめます。最近は、火星の気候を研究するプロジェクトにも参加しています。火星の気候を理解するため、火星表面がどれくらいの速さで侵食し変化していったかを調べます。遠い昔、火星には地球と同じように水があり雨も降っていたのならば、どのようなスピードで侵食され、今のような激しく乾いた地表になっていったのかを研究します。
また、次の火星探査機の着陸地を選ぶのも、私の仕事です。探査機の着陸地を決めるときは、軌道から取得されたデータをもとに、安全に着陸できる地表を予測します。そのために、岩石の分布についても研究しています。地表の岩石は、探査機の着陸の際に事故を引き起こす原因になりかねません。また岩石がたくさんありすぎると、ローバーの走行を妨げます。NASAは、2011年に火星探査機「マーズ・サイエンス・ラボラトリー」を打ち上げる予定ですが、現在、その着陸候補地の選定を行っています。候補地を決めるためには、火星で撮られた高解像画像などを利用し、可能な限り調べます。軌道からの観測で、地表の様子を正確に予測できるようになれば、着陸地選択の成功率が上がります。私はこれまで、「マーズ・パスファインダー」、「スピリット」、「オポチュニティ」という3機の探査機の着陸地点の選択にかかわってきましたが、どれも予測は当たりました。今後も火星探査を続けていくためには、着陸の成功率を上げることはとても重要なのです。
Q.新しい探査機の着陸地を決めるにあたって、重要なことは何でしょうか?
一番大切なのは、着陸機とローバーにとっての安全性です。失敗する可能性が高い場所に着陸機を送り込むのは、誰にとっても良くないですよね。科学的成果を得るためには、着陸に成功しなくてはいけません。そのためにも、地表を把握することはとても大切です。安全な場所を選ぶためには、その場所の安全性を確信できるまで研究に研究を重ね、できることはすべてやり尽くします。
すべての火星着陸機はエアロシェル(探査機を火星大気突入時の高熱から守る外殻)とパラシュートを使いますが、その際重要なのが、着陸地点の高度(標高)です。一定の高度まで降下しないとパラシュートを開くことができません。ですからオリンポス山頂のような高地には、探査機を着陸させることができないのです。ですから着陸地点を選ぶ時には、高度(標高)がとても重要な要素となります。
次に重要なことは、地表面の堅さです。火星には凝集力の低い塵の堆積物がいくつかあると考えられていますが、それが厚く積もっている可能性があります。そのような場所に探査機が着陸したら、すっぽり見えなくなるまで沈んでしまうかもしれません。また、塵の堆積物の上に着陸することは、太陽電池パネルにとってもよくありません。塵がパネルの上を覆ってしまい、パワーが落ちてしまうからです。岩がゴロゴロある場所も、探査機がその上に着陸したらダメージを受けてしまうのでだめです。険しい急斜面も、衝突したり、転がり落ちてきちんと着陸できない可能性があるので良くないですね。これらのことが、着陸地点を選ぶ上で注意しなければならない点です。あとは探査機の設計エンジニアから、それぞれの着陸機とローバーの必要条件を教えてもらい、ふさわしい着陸地点の検討を開始します。
一方、太陽エネルギーを動力としている探査機の場合、長期使用を考えているなら、太陽エネルギーを一番多く受けられる場所を選ぶことも大切です。そうなると、一番太陽に近く、一番暖かい場所ということで、赤道付近ですね。火星探査機「フェニックス」のように極地に着陸すると、日照不足により太陽電池が切れ、ミッションが早く終了してしまいます。ですから、着陸地を選ぶときは緯度も重要です。
さらに、科学的な面を考える必要もあります。例えば、このミッションが達成しようとしていることは何なのか。どのような観察機器が搭載されるのか。調べたい物質が着陸地にあるか、といったことも考えて着陸地点を決めます。もし古代の火星環境の研究が目的ならば、古代の岩石が地表に露出している場所に行きたいですよね。着陸機にはそれぞれ異なる科学ミッションがあり、それに応じて設計されています。もちろん観測機器も異なります。ですから着陸地の選択には、科学的な面と安全性の2つのことを主に考慮します。