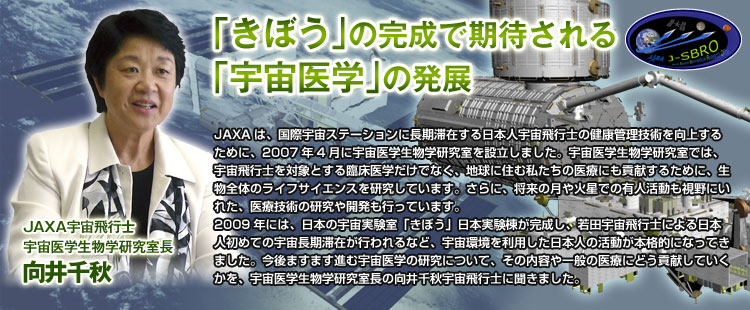
Q. 宇宙医学とはどういう学問でしょうか?

「きぼう」船内実験室にて作業を行う若田宇宙飛行士(提供:NASA/JAXA)
宇宙という環境を使った、究極の予防医学だと思います。宇宙空間は、「無重力環境」「宇宙放射線環境」「閉鎖環境」という、人間にとって過酷な環境です。例えば、国際宇宙ステーションのような微小重力の環境では、1Gの地球上から重力が減少することによって、骨や筋肉が弱くなります。地球は大気層によって保護されているため、宇宙空間を飛び交う放射線が地上までほとんど届きませんが、宇宙にいると放射線の影響を受けます。また、人が宇宙で生きられるところは、宇宙ステーションやスペースシャトルなど閉ざされた空間の中だけです。狭い、制限された世界で他の文化を持つ人たちと一緒に生活するとなると、精神心理的なストレスも受けます。一時期、建物内の空気汚染の影響で、のどの刺激や痛み、頭痛など健康障害をおこすシックハウス症候群が話題になりましたが、狭い空間に長くいると、周囲のいろいろなものから出てくるガスなどによって体調を悪くすることがあります。
このような宇宙環境にかかわる身体への影響を予防して、元気に宇宙へ送り出した飛行士を、元気な姿で地球に戻すのが、宇宙医学の目的だと思います。そのためには、宇宙に滞在しているときや、帰還した後の健康維持や管理に必要となる医療技術の研究開発が必要です。
また、宇宙医学の面白さは、元気な人が宇宙へ行って、宇宙で病気のような状態になり、地上に戻ってくるとまた元気になる、という全過程を短期間で見られることだと思います。通常、地上で病院に行くときには、気持ち悪くなったとか、骨が弱くなったといった症状が出た状態のときです。患者さんは症状が進んだ状態で病院に来ますので、病気の初期状況を把握するのが難しいのです。一方、宇宙医学では、例えば、元気だった宇宙飛行士が宇宙酔いにかかって治るまで、あるいは、骨が弱くなって帰還してまた普通に戻るまでのすべてのプロセスを見ることができるのです。そのような点が宇宙医学研究の魅力だと思います。
このような宇宙環境にかかわる身体への影響を予防して、元気に宇宙へ送り出した飛行士を、元気な姿で地球に戻すのが、宇宙医学の目的だと思います。そのためには、宇宙に滞在しているときや、帰還した後の健康維持や管理に必要となる医療技術の研究開発が必要です。
また、宇宙医学の面白さは、元気な人が宇宙へ行って、宇宙で病気のような状態になり、地上に戻ってくるとまた元気になる、という全過程を短期間で見られることだと思います。通常、地上で病院に行くときには、気持ち悪くなったとか、骨が弱くなったといった症状が出た状態のときです。患者さんは症状が進んだ状態で病院に来ますので、病気の初期状況を把握するのが難しいのです。一方、宇宙医学では、例えば、元気だった宇宙飛行士が宇宙酔いにかかって治るまで、あるいは、骨が弱くなって帰還してまた普通に戻るまでのすべてのプロセスを見ることができるのです。そのような点が宇宙医学研究の魅力だと思います。
Q. JAXAの宇宙医学生物学研究室ではどのような研究が行われているのでしょうか?

「きぼう」船内実験室の内部(提供:NASA/JAXA)
宇宙生物学研究室が行っている研究は、問題解決型の医学研究です。人間が宇宙を飛行すると、宇宙酔いになる、骨が弱くなる、カルシウムが抜けてしまう、筋肉が弱くなる、運動がうまくできないといった問題が山積みです。そのような問題を放置しておくと身体にどのような影響があるかを調べ、それを予防するための対策を考えることが研究の一番の目的です。ですから、国際宇宙ステーションをターゲットにした研究を行っています。
その研究領域は5分野あります。
また、国際宇宙ステーションを十二分に使うためには、将来を見据えた目線も必要ですから、「月面の開拓医学」と称して、これらの分野を月面での有人活動をも視野に入れて研究しています。さらに、国際宇宙ステーションだけでなく、模擬環境として、南極の基地も利用して研究を行なっています。
その研究領域は5分野あります。
- 1)
- 生理的な対策。薬剤を用いた骨量減少・尿路結石の予防対策や、微小重力環境における効果的な運動器具・トレーニング法の研究。
- 2)
- 放射線被曝管理。放射線を防御する方法や、被曝した放射線の量を調べる計測器の研究。
- 3)
- 精神心理支援。異文化の人たちと生活したり、閉鎖された空間内で効率よく働けるような精神心理を保つための、適応訓練の研究。また、その適応の評価方法に関する研究。
また、国際宇宙ステーションを十二分に使うためには、将来を見据えた目線も必要ですから、「月面の開拓医学」と称して、これらの分野を月面での有人活動をも視野に入れて研究しています。さらに、国際宇宙ステーションだけでなく、模擬環境として、南極の基地も利用して研究を行なっています。
Q. 月面の開拓医学とは具体的にどのような研究を行なっているのでしょうか?

月面を歩くアポロ14号の宇宙飛行士(提供:NASA)
月面の開拓医学はまだ始まったばかりです。アポロ計画では12人の宇宙飛行士が月面に降り立ちましたが、その当時は冒険的な要素が強く、ライフサイエンスの研究にまで至りませんでした。
月面の医学では、月面に行った人が安全に過ごせるようにするため、月面での遠隔医療システムや、レゴリスという月面のダストの肺への影響、国際宇宙ステーション以上に強い宇宙放射線の被曝による影響を研究します。そのほか、月面での歩行や姿勢制御を研究する運動生理学や転倒防止についても研究します。月面にいるアポロの宇宙飛行士の映像を見ると、月面を歩いているというよりは、ぴょんぴょん跳ねている感じです。また、よく転んでいます。地上と同じ姿勢制御ができないのは、月面の重力が6分の1Gであることに関係しているのかを調べたいのです。
月面の医学を行なう最大の理由は、月の重力が6分の1Gだからです。宇宙ステーションと月の両方の研究を行なうと、地球上ではできない1と0の間の可変重力の分野も知ることができるのです。宇宙ステーションの微小重力下では、骨や筋肉に異常が起きますが、月面の6分の1Gではどうなるのか?どのくらいの重力があったら異常が起きるのか、起きないのか。それらを調べることによって、地球上では重力に隠されて分かっていない生理現象や病気のメカニズムが分かってくる可能性もあります。そういう意味で、月面の開拓医学に非常に興味を持っています。
また、0Gの研究については、自前の有人ロケットを持ち研究の歴史の長いアメリカやロシアにはかないませんが、月面の医学については、どの国も同じ位置にいます。がんばれば、日本がこの分野で世界のトップに立てるかもしれないのです。
月面の医学では、月面に行った人が安全に過ごせるようにするため、月面での遠隔医療システムや、レゴリスという月面のダストの肺への影響、国際宇宙ステーション以上に強い宇宙放射線の被曝による影響を研究します。そのほか、月面での歩行や姿勢制御を研究する運動生理学や転倒防止についても研究します。月面にいるアポロの宇宙飛行士の映像を見ると、月面を歩いているというよりは、ぴょんぴょん跳ねている感じです。また、よく転んでいます。地上と同じ姿勢制御ができないのは、月面の重力が6分の1Gであることに関係しているのかを調べたいのです。
月面の医学を行なう最大の理由は、月の重力が6分の1Gだからです。宇宙ステーションと月の両方の研究を行なうと、地球上ではできない1と0の間の可変重力の分野も知ることができるのです。宇宙ステーションの微小重力下では、骨や筋肉に異常が起きますが、月面の6分の1Gではどうなるのか?どのくらいの重力があったら異常が起きるのか、起きないのか。それらを調べることによって、地球上では重力に隠されて分かっていない生理現象や病気のメカニズムが分かってくる可能性もあります。そういう意味で、月面の開拓医学に非常に興味を持っています。
また、0Gの研究については、自前の有人ロケットを持ち研究の歴史の長いアメリカやロシアにはかないませんが、月面の医学については、どの国も同じ位置にいます。がんばれば、日本がこの分野で世界のトップに立てるかもしれないのです。