
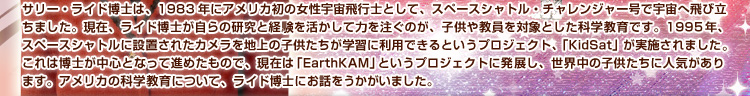
サリー・ライド
元NASA宇宙飛行士、サリーライド・サイエンス社代表
1978年、スタンフォード大学で物理学博士号を取得。同年、応募者8000人以上の中から、35人のNASA宇宙飛行士候補生(うち女性は6人)の1人に選ばれる。1983年、アメリカ初の女性宇宙飛行士として、スペースシャトル・チャレンジャー号で宇宙へ飛行。1984年、2度目のスペースシャトル搭乗。1987年にNASAを退官し、スタンフォード大学特別研究員となる。1989年、カリフォルニア大学サンディエゴ校の物理学教授とカリフォルニア宇宙協会会長に就任。チャレンジャー号の事故(1986年)、コロンビア号の事故(2003年)の調査委員のメンバーを務める。2001年、科学教育の普及推進を目的としたサリーライド・サイエンス社を設立。
※サリー・ライドさんは、2012年7月23日に逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。
Q. 博士が代表を務めるサリーライド・サイエンス社の活動について教えてください。

科学フェスティバル(提供:Sally Ride Science)
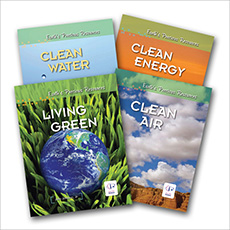
サリーライド・サイエンス社が提供する教材(提供:Sally Ride Science)
私たちはさまざまな科学教育プログラムを行っていますが、主な活動は次の3つです。
1つ目は、当社の活動の中でも最も大規模で、世界的に知られている「EarthKAM:Earth Knowledge Acquired by Middle School Students (アースカム)」です。これはNASAが資金提供をしている学校用の国際的な教育プロジェクトで、世界中の中学生が国際宇宙ステーションに設置されたデジタルカメラを学習のために利用できるというものです。地球科学を学んでいる子供たちでも、環境問題や気象について学んでいる子供たちでも、それぞれの学習内容に合わせて、世界各地の写真を宇宙から撮影することができます。「アースカム」は宇宙科学と地球科学、環境科学を組み合わせたユニークな取り組みでとても人気があり、日本の学校も何校か参加したことがあります。
2つ目の活動として、当社では小中学校の教員を対象としたトレーニング・プログラムも提供しています。教員訓練コースやテーマ別の短期講座を通じて、効果的な科学の教え方や科学に対する興味をかきたてる方法などについて、具体的に教えています。「いかに科学を教えるか」という点にポイントを置き、最新の研究成果に基づいた科学教育の方法を先生方に教えているのです。ここ数年来、私たちはこの取り組みに大いに力を入れており、当社の活動の中でも進展著しい分野と言えるでしょう。
そして3つ目に、学校の授業や家庭学習で使える教材を製作しています。いずれも小中学生向けのもので、宇宙から地球環境まで科学の幅広い分野をカバーしています。学校の教科書を補うための補助教材として、特定のテーマについて教科書よりもずっと深く掘り下げていますので、とても好評です。
以上のように、学校用のプログラム、教員向けの講座、補助教材の提供というのがサリーライド・サイエンス社の主要な取り組みです。さらに、11〜13歳の女の子を対象とした科学フェスティバルなども開催しています。
Q. 科学教育のなかで特に力を入れている分野はありますか?やはり、なんと言っても宇宙ですね。ただし宇宙だけでなく、地球科学、環境、気象変動、環境科学に関する教材も提供しています。また、科学のあらゆる分野をカバーする本のシリーズの製作にも取り組んでいます。生命科学、物理学、地球科学、宇宙科学など、テーマは科学全般に及び、全部で36冊の本を出す予定です。私たちは、科学がいかにワクワクする面白いものなのか、そして科学のさまざまな分野についてどんなことを学ぶべきなのか、子供や先生たちに伝えていきたいと思っています。
Q. 博士は一貫して小学校の高学年から中学生の科学教育に力を入れてこられました。この年齢層の子供たちをターゲットにしようと考えたのはなぜですか?

科学フェスティバル(提供:Sally Ride Science)

テニスに夢中だった学生時代のライド博士(提供:Sally Ride)
これはアメリカの場合ですが、多くの研究調査の結果によれば、子供たちは小学校4年生から5年生、つまり9歳や10歳の頃はとても科学に関心を持っています。ところが11、12、13歳になるにつれて、だんだん科学からの関心が離れていきます。そしてこの年齢でいったん関心が薄れてしまうと、再び科学に興味を持たせることはとても難しいのです。
ですから、特定の年齢層にターゲットを絞るとすれば、小学校から中学校へ上がる前後の、科学に対する関心を失いがちな年齢層ということになります。10歳から13歳くらいまでの子供たちです。私たちが全力を傾けて取り組んでいるのは、なんとかしてその層の子供たちが科学に興味を持ち続け、科学と関わり続けるようにすることです。ほんの2年ほど前までは科学が好きで、すごく面白いと思っていた子供たちですから、その関心を失わないようにしてあげることができれば、高校や大学へと進んでも科学に関心を持ち続けてくれることが期待できるわけです。 Q. なぜ11歳くらいの年齢層から科学への関心を失い始めるのだ思いますか? アメリカの場合は、わが国の文化と深く関わっています。この20年間、アメリカでは科学の大切さを強調してきませんでしたし、科学がいかに興味深くワクワクするようなもので、仕事としてもかっこよく、やりがいのあるものかを、子供たちに伝えてこなかったのです。
私が育った1960年代、アメリカは科学と技術をとても重視していました。宇宙開発の初期の時代で、科学と工学にとても力を入れていて、子供たちも科学や工学をすごく「かっこいい」と感じながら大人になっていったものです。
ところがやがて、国全体としてそうした傾向が薄れてしまい、この20年ほどは、科学や技術に大きな力点を置いてきたとは言えません。ですから子供たちは、科学や技術がどれほど重要か分かっていないのです。新聞を読んでも、科学は重要な話題として取り扱われていません。テレビやインターネットで科学に関する話題を見ても、重要なことだとはあまり思えないし、自分の目標となるような科学者たちもあまり目にする機会がないのです。
しかし最近、アメリカではそんな状況が変わりつつあります。まだこの1〜2年のことにすぎませんが、国として科学教育に力を入れ、その重要性を強調するようになってきました。 Q. 2010年9月にオバマ大統領は、次世代の科学者を育てるための、科学・技術・工学・数学(Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEMと言う)の教育に関する新しいプログラムを発表しました。これも望ましい変化の1つですね? そう思います。とてもいい変化だと思います。オバマ大統領は、本当に力強く科学教育を支援してくれていて、実際に、科学と科学教育に関するいくつかの重要な提言を発表しています。国のリーダーがこれほどはっきりと支援を表明し後押ししてくれること、そして、その姿勢が国民の目に見えるということはとても心強いことです。
2010年9月に発表されたSTEM教育を振興する政策は、「革新のために教育を」と大統領が呼んでいる提言の下に組み込まれていて、実は私もあるプログラムの開発に副委員長として参加しています。このプログラムは「Change the Equation(方程式を変えろ)」と呼ばれています。(※’equation’には数学の方程式の意味と、状況・問題・課題といった意味があり、これは両方をひっかけた語呂合わせのネーミング。科学・数学教育の停滞を打破しようというねらいの提言)
この10〜15年の間、科学に関するさまざまな教育プログラムに多大な資金を提供してくれた企業がたくさんありますが、そういった企業を一致団結させ、ひとつの声として科学教育の重要性を訴え、推進力となってもらおうというのが「Change the Equation」のねらいです。つまり、科学教育を支援してくれる各社の努力を組み合わせることでより大きな力を発揮してもらい、いっそうの効果をあげようと言うのです。このプログラムに参加する企業は、科学教育関連に限らず、情報通信、製造、運輸、医療、卸売業など幅広い分野にわたっています。私のサリーライド・サイエンス社も参加企業のひとつです。
