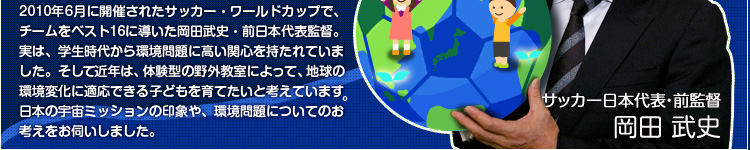
岡田武史(おかだたけし) サッカー日本代表・前監督 中学1年生よりサッカーをはじめ、大阪府立天王寺高等学校3年時に日本ユース代表に選ばれる。その後、早稲田大学政治経済学部に入学しサッカー部に所属。大学卒業と同時に古河電気工業サッカー部に入部し、在籍中に日本代表選手として活躍。1997年にサッカー日本代表監督に就任し、FIFAワールドカップ初出場を果たす。監督としてJ2コンサドーレ札幌、横浜F・横浜マリノスを優勝に導いた後、2007年に2度目のサッカー日本代表監督に就任。2010年6月のワールドカップ・南アフリカ大会で、チームはベスト16に進出。現在は日本サッカー協会環境担当理事。
Q. 日本の宇宙ミッションで印象に残っているものはありますか?

小惑星探査機「はやぶさ」(提供:池下章裕)
何と言っても「はやぶさ」の帰還です。私がインストラクターをやっている富良野自然塾の環境教育に、「石の地球」といって、直径1mの地球のオブジェを使って、地球のことを分かりやすく説明するプログラムがありますが、その尺図で小惑星イトカワがどれだけ遠いかを計算してみたんです。すると、「はやぶさ」は、24km先にある0.01mmにもならない小さいところ、イトカワに着陸したことが分かったのです。これは本当にスゴイことです。「はやぶさ」は途中で数ヵ月も音信不通になっていたのに、プロジェクトチームの努力もあって、7年にもおよぶ旅から無事に帰還しました。これには感動しましたね。
また、「はやぶさ」が帰還したのは2010年6月で、ちょうどワールドカップ・南アフリカ大会の決勝トーナメント、パラグアイ戦の前でした。私は、サッカー日本代表チームは勝つと信じていましたが、周囲のほとんどの人が勝つとは思っておらず、まさか決勝トーナメントまで進むとは思っていませんでした。「はやぶさ」も、帰還できると思われていなかったので、そういう意味では、日本代表チームと共通点があるのかもしれませんね。
Q. もし宇宙へ行けるとしたら、どんなことをしてみたいですか?宇宙についてはどのようなイメージをお持ちですか?
宇宙から、地球を見てみたいです。私にとって宇宙は、生命のつながり、命の尊さを感じさせてくれるものです。宇宙はとてつもなく大きく、その大自然の中に、私たちが住む美しい星、地球があります。広大な宇宙に比べると地球はとても小さく、そこで今、この一瞬一瞬を生きているということに謙虚さを感じます。宇宙から地球を見たら、蟻の作った蟻塚も人間の作ったビルも同じ地球の自然だと思います。つまり、我々人類は地球の生命活動の一部であると認識できるのではと思っています。
Q. 環境問題についてどのようなお考えをお持ちですか?

(提供:NASA)
地球環境が大変だとよく言われていますが、私はそうは思いません。46億年の歴史の中で、地球の環境はどんどん変わってきて、その変化に生物が適応してきたのです。しかし、産業革命以降のこの200年程で地球の気候変動が急激になり、人間社会はその変化に適応しづらくなりました。そのため、地球環境の変化をスローダウンさせるというのが、一般的に環境活動と言われるものです。その一方で、その変化に社会や人間が適応していくというのも、環境活動だと思います。特に私は、環境変化に適応できる人間を育てたいと思っています。
地球の人口を見ると、1900年に15億だった人口が、1950年にその倍の30億、2000年には60億、そして、今は68億を超えたと言われています。これだけ人口が爆発的に増えても地球の大きさは変わりませんから、このままでは地球が持つわけがないというのは、誰が考えても分かることです。その中で日本人は最も環境等の変化に適応できず、一番に絶滅するのではないかという危惧を持っています。
日本人は豊かな暮らしに慣れ「生きる力」がとても弱くなっています。日本では年間3万人が自殺をして、9万人が行方不明になるという異常事態が続いています。アフリカでは飢えや感染症で多くの人が亡くなっていますが、自殺者はゼロだと言われています。なぜ、この豊かな日本でこれだけの人間が自ら命を絶つのでしょうか。なぜ、100万人もの人が引きこもりになってしまうのでしょうか。日本人に「生きる力」を付け、環境変化に適応できる人間を作っていかなければならないと考え、それを実行する団体を立ち上げようと準備をしています。 Q. その人材育成は、どれくらいの年齢層を対象に考えていますか? どのようにして「生きる力」を教えるのでしょうか? いずれは若者と呼ばれる年代すべてを対象にしたいと思いますが、まずは小学生を対象に考えています。昔、小学生は外で遊んでばかりいました。私も小学生の頃は、学校の帰りにランドセルを置いてよく友だちと遊び、鉄橋の上を歩き、落ちたら死ぬかもしれないという「ドキッ!」を楽しむ危険な遊びもしていましたね。今思うと、そのような「ドキッ!」が脳幹へ刺激を与え、生きる力をどんどん育てていたように思います。
しかし今の日本の子どもは、「これをしてはダメ」と言われることばかりで、餌が流れてきて体を洗ってもらい、屋根のついた厩舎にいる家畜のようになっているのかもしれません。何もしなくても生きていける状況にある子どもたちは、当然、生きる力が弱くなります。しかしこれは、子どもたちのせいではありません。便利、快適、安全な豊かな社会が、そうさせてしまったのです。私はこの状況を非常に恐ろしいことだと思っています。だからといって子どもたちに、鉄橋を渡ってもいいですよとは言えませんので、脳幹を刺激するような別の機会を作ってあげたいと思います。
それにはいろいろな方法があると思います。例えばスポーツです。スポーツで高い目標を達成したときに「やった!」と感動したり、駄目だったときに「なにくそ!」と頑張る力は、ある意味で脳幹へ刺激を与えます。その刺激が生きる力を育むのです。しかしスポーツだけでは、スポーツをする限られた子どもだけになってしまうので、野外活動も考えています。キャンプなどで、皆でいろいろな苦難を乗り越えていくようなプログラムを作り、できるだけ全部自分たちでやらせるようにしたいと思っています。
子どもが馬と1週間過ごすという体験スクールを視察したことがありますが、これは、子どもたちが馬小屋の2階に藁を敷いて寝て、馬の世話をし、最後には馬に乗れるようになって、馬と一緒に山を越えてキャンプをするというプログラムでした。このスクールに参加した子どもたちの目が、最初と最後ではまったく違っていたそうです。やはり、「体験」によって人間は成長していくものだと実感しました。野外活動を体験することだけで、生きる力が付くとか何かが大きく変わるとは言えませんが、生きる力を引き出す「きっかけ」を、何か1つでも良いので子どもたちに与えることができればと思っています。
Q. なぜ環境問題にご興味を持たれるようになったのでしょうか?

富良野自然塾の環境教育プログラム(提供:富良野自然塾)
30年程前の学生時代に、ローマクラブの『成長の限界』を読んだのがきっかけです。この報告書は、このまま人口増加や環境汚染が続けば、資源の枯渇や環境の悪化によって、人類の成長は限界に達するということを提言したものです。これを読んだとき「ここに書いてあることは本当かな?」と思い、環境問題に関心を持つようになりました。そして1980年にアメリカ政府が出した報告書『西暦2000年の地球』や、いち早く環境問題に警鐘を鳴らした生物学者、レイチェル・カーソンの著書などに出会いました。 Q. 環境問題に関してどのような活動をされていますか? 実際に活動しようと思ったきっかけは何でしょうか? 2002年に、南アフリカで開かれた環境サミットにNPOの一員として参加しています。また2007年には太陽光発電など再生可能エネルギーの普及を目指した任意団体、「地球環境イニシアティブ(GEIN)」の代表発起人となり、その活動に参加してきました。そのほか、作家の倉本聰さんが主宰する富良野自然塾のインストラクターをやっています。この自然塾では、閉鎖されたゴルフ場を元の森に還そうという活動と、そのゴルフ場跡地を使った環境教育を行っています。
活動をしようと思ったのは、子どもたちに何かしてやらなければならないと思ったからです。環境問題が深刻になる中、地球の未来を考えたときに、自分たちは何もしなくてよいのだろうか?私たちの時代は大丈夫だからと言って楽をして、次世代の子どもたちに借金を負わせてもいいのだろうか?と思いました。子どもたちに地球の「希望の光」をつなぐために、踏み出してみようと思ったのが正直なところです。中には環境活動に対して「そんな事どうせやったって」と言う人もいますが、私はどんな小さな1歩でも良いので、皆さんに踏み出してほしいと思っています。
