 |
 |
 |
 |
 |
|
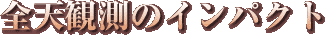


世界中の天文学者にとって全天観測(宇宙の地図作り)は、かなりエキサイティングなアイデアです。我々の研究に相当のインパクトを与えてくれるでしょう。ですから「あかり(ASTRO-F)」の打ち上げと軌道投入が成功し、その後、観測装置が問題なく稼働し続けることを願っています。
 |
|
| |
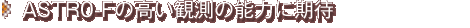

私が特に興味があるのは、全天観測による数10億光年彼方に存在する銀河の分布図の作成です。私は、1983年のIRASでこれを最初に試みました。「あかり」は、この研究をさらに発展させるのに最適です。
また、「あかり」は、ヨーロッパ(ESA)のISOやアメリカ(NASA)のスピッツァーでも観測が難しかった遠赤外線領域をカバーします。この領域は観測がとても難しく、観測装置の開発も難易度が高いのです。「あかり」が今後、どれほど素晴しいデータを得られるのか見守っています。もちろん素晴らしい成果を願っていますよ。また、中間赤外線に関して「あかり」は、波長範囲全体をカバーする長所を持っています。スピッツァーでは、充分にカバーできません。しかし一方で、「あかり」にスピッツァーほどの感度が期待できるかは疑問です。ですから「あかり」とスピッツァーは、お互い異なる長所を持つ補完関係にあります。
「あかり」に関係する方たちは、今、期待と不安を抱えていると思います。宇宙計画に関わったことがある人なら誰もが知っていることですが、すべてが完全に、正常に動作するのを確認するまでは、冷静に状況を見守るのが賢明だと思います。
|
|
|
|
| |


「あかり」計画を知った時から、私の心の中では共同研究がスタートしたと言えます。なぜならデータ処理が課題となると思ったからです。そこで共同研究のチャンスがあるかも知れないと考え、日本の研究者に連絡しました。そして2000年、マンチェスターで開催された国際天文連合の国際会議の時に、はじめて直接、日本の研究者の方と話ができました。その後、何度かの会議を経て、最終的にイギリスと日本の間で国際共同研究の契約が交わされたのです。その後、オランダの研究者がチームに加わりました。
ヨーロッパチームの「あかり」への参加は、2つの側面があります。1つは、イギリスとオランダの天文学者によるデータ処理分野での協力です。私たちはこれまでにIRASやISOなどヨーロッパが関わった赤外線天文衛星での経験から、データ処理について多くのノウハウを提供できます。ここ数年間私たちは、日本の研究者と一緒に、「あかり」のデータ処理ソフトを開発してきました。データ処理に関しては、日本もマンパワーが不足していたので、とても喜ばれています。もう1つは、ヨーロッパ独自の研究テーマに関して、「あかり」のデータを自由に使うことができることで、とても楽しみにしています。
私たちヨーロッパもESAの計画で、2008年に赤外線天文衛星 ハーシェル(Herschel)を打ち上げる予定です。ハーシェルの望遠鏡の口径は3.5mもあり、「あかり」やスピッツァーの約4倍で、赤外線宇宙望遠鏡としては世界最大です。また、波長も60〜670ミクロンを観測する大規模な計画です。
日本の天体物理学と宇宙科学の発展は目を見張るものがあります。優秀な研究者も沢山いるので、日本との共同研究はとても素晴らしいです。日本は天文衛星だけでなく、ハワイにすばる望遠鏡もありますし、日本の天体物理学者にとって、今はとても刺激的な時だと思います。
|
|


ISO(1995)

ESAの次期赤外線宇宙望遠鏡
ハーシェル |
|
|
 |
 |
マイケル・ローワン-ロビンソン(Michael Rowan-Robinson)
ロンドン・インペリアル大学教授、「あかり」イギリス・オランダ共同研究グループ代表。
1969年博士号取得後、クイーンメリー大学数理学部の助手、講師を経て、その後、天文学に転身し、1987年に教授となる。1993年よりロンドン・インペリアル大学に勤務、天体物理学の主任教授となる。1977年からIRASに関わり、ISOでは、主任科学者の1人となる。また、ESAの科学計画やハッブル宇宙望遠鏡などの委員としても活躍。ESAの次期赤外線宇宙望遠鏡ハーシェルでは、主任科学者の1人として中心的な存在。これまでに160編以上もの論文を書き、数多くの本も執筆している。
|
|
|
|

