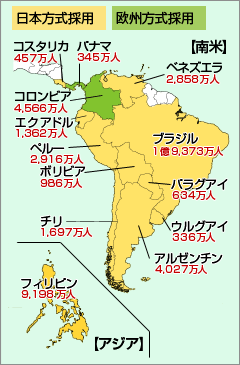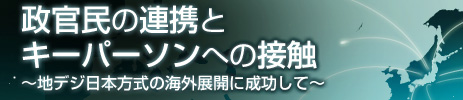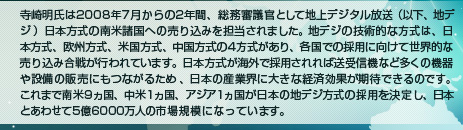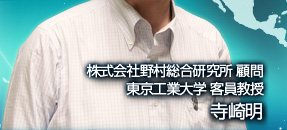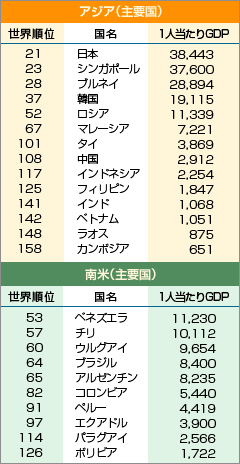Q. 地デジの海外展開を行った理由は何でしょうか? 南米は市場として注目されていたのでしょうか?
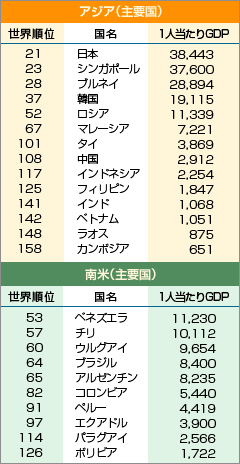
アジア、南米各国の1人当たりGDPの額(単位:ドル)(出典:世界銀行「World Development Indicators 2008」)
日本は少子高齢化が問題となっていますが、現在の日本の人口は約1億2700万人。2055年には約9000万人、2100年には5000万人を切ると言われています。人口減少により国内市場が縮小することを考えると、中長期的にも日本の産業にとってグローバル化は不可欠です。
また、最近は日本企業も南米の新興市場に熱い視線を注いでいますが、私が地デジ方式の売り込みを始めた頃は、それほど注目されていませんでした。よくアジア市場の話が出ますが、世界銀行などの資料で1人当たりのGDP(国内総生産)の値を見ると、南米諸国はアジア諸国よりもGDPの値が大きな国がたくさんあります。南米は資源や食料に恵まれているため、国民に購買力があるのです。実際に南米に行ってみると、その市場の大きさに驚くほどです。 Q. 地デジの日本方式を南米の主要国が採用したことで、日本の産業にどのような利益を生み出しましたか? 日本企業がグローバル化する大きなチャンスになったと思います。例えばブラジルがデジタル方式の放送を始めたのは2007年12月ですが、日本メーカーの薄型テレビのシェアが2006年に10%だったのが2009年には20%となり、確実に増えています。また地デジの日本方式が採用されると、テレビ(受信機)だけでなく、テレビ局が鉄塔から電波を出すための送信機も売れます。サンパウロでは、送信機の日本メーカーのシェアは20%程度から60〜70%に拡大しました。送信機は受信エリアの面積が広いほど数が必要なので、国土が広い南米は大きな市場となります。そのほかスタジオ機器の需要もありますし、日本方式という共通の放送基盤ができたことで放送番組やコンテンツの交流も考えられます。
また、日本方式のデジタル放送はワンセグ技術を入れていますので、ワンセグ携帯端末からもテレビが見られます。国内需要だけの日本の携帯電話は世界から孤立していて「ガラパゴス状態」だと言われますが、南米に日本方式の地デジが導入されれば、携帯端末メーカーにとって海外進出の突破口になると思います。南米では約4億の人口のうち、9割近くが日本方式の地デジを見ることになりますので、携帯端末市場にも大きな可能性があると思います。
さらには、地デジ以外の産業にも派生的な効果が見られます。地デジの売り込みを通して、各国の大統領や情報通信大臣など要人との人的ネットワークが構築できたため、ITS(高度道路交通システム)を使った渋滞情報やカーナビなど他分野への協力へと広がりつつあります。ブラジルは2014年にFIFAワールドカップ、2016年にはオリンピックの開催が予定されていますので、政府は渋滞を解消したいという強い気持ちを持っているのです。将来的には、ブロードバンドなどの情報通信放送や衛星ミッションなどにも波及効果があるかもしれません。

Q. 南米はコロンビアを除く主要国が日本方式を採用しています。南米のほとんどの国が日本方式を採用するまでの経緯を教えていただけますか?
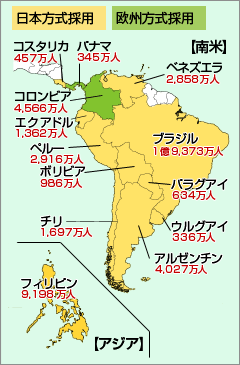
地デジ日本方式の採用状況。2011年4月現在、11ヵ国が採用(赤字は各国人口 出典:世界保健機構「世界保健統計2011」)
2006年にブラジルが最初に日本方式を採用しましたが、この決断には、日本方式の技術面での優位性だけでなく、日本政府からの政治的な働きかけが影響を与えています。日本方式を採用してくれれば、日伯(日本・ブラジル)方式として一緒にブラジル以外の国に普及させていきたい、という日本からの政治的なメッセージが決め手となったのです。
しかし、この後大変苦労をしました。南米ではブラジルだけがポルトガル語圏で、そのほかはスペイン語圏。つまりスペインが旧宗主国ですが、その旧宗主国の元首から南米各国の大統領に「地上デジタル放送は欧州方式でするように」と何度も直接電話があったそうです。その他にも、欧州委員会の首脳から南米各国の大統領に働きかけがあったと聞いています。その流れの中で、2007年にスペイン語圏のウルグアイが、また2008年には同語圏のコロンビアが欧州方式の採用を決めました。
ところが、2009年4月に、ペルーがスペイン語圏で初めて日本方式を採用します。実はこれにも政治が影響していました。この5ヵ月前にAPEC(アジア太平洋経済協力)首脳会議がペルーで開催され、その際の日本・ペルー首脳会談において、当時の麻生首相からガルシア大統領へ、直接、日本方式導入の働きかけが行われました。また、その際、ペルーからの要望により、日本がペルーとの経済連携協定(EPA)を前向きに検討すると表明したことも、結果的には好影響を与えたのではないかと思われます。
ペルーの日本方式採用決定で状況が一変し、他の国も日本方式の採用を決めました。そして2010年12月には、一旦、欧州方式に決めたウルグアイが日本方式に変更し、南米の主要国はコロンビアを除きすべて日本方式になりました。つまり、日本方式は事実上の南米標準になったのです。 Q. 日伯方式は効果的だったのでしょうか? はい。2国で他の国に当たりましたので、完璧な提案ができたという部分がありました。これは地デジに限らないことですが、相手国からは、その国の発展を促すという意味で、雇用の確保とともに工場や研究センターの誘致を要求されることが多々あります。
例えば、デジタルテレビの組み立て工場を作ってほしいと求められた場合、日本の企業が社内調整に時間がかかるのに対して、ブラジルはすぐに回答を出してくれました。ブラジルの企業が工場の設置に投資するということを、ブラジル政府が各国に積極的に提案してくれたのです。素早い意思決定をしてくれたブラジルとの連携は、とても効果的だったと思います。

Q. 地デジの南米展開に成功した秘訣は何だと思われますか?

地デジの方式を決めるキーパ−ソンが誰かをきちんと見極めて、彼らと接触したことです。南米の場合、その実質の決定権が大統領と放送を所管している大臣にあると分かった時点で、国が主導しなければならないと決断しました。先ほど申し上げたとおり、欧州の国が途上国に働きかける際、旧宗主国の元首や欧州委員会の首脳が直接電話で大統領に働きかけます。ですから日本も相手国の大統領に対して、首相から直接、首脳会談や電話で働きかけが行われました。
従来の日本のビジネスでは、まず担当者同士が話し合って段取りをつけ、次に局長や執行役員など部門の責任者同士が内容を詰め、最後に所管の大臣や企業の代表者が会って署名をするという、下から上へのボトムアップ方式を取ることが多いですよね。しかし発展途上国の場合、担当者から上司には話が上がらないと思った方がいいようです。その理由は、担当者からすると、重要な意思決定を必要とする案件を上げることにより、上司から「賄賂を受け取ったのではないか」と誤解されるのを防ぐためではないかと推察します。途上国では、キーパーソンは汚職を退治して国を良くしたいと思っている場合が多いのですが、現実にはなかなかゼロにならない状況にあると考えられます。
しかし、決定権がある人とだけ話をしても交渉は進みません。キーパーソンに働きかけて、そこで担当者を紹介してもらい、担当者同士で内容を詰めていくのです。相手国の担当者も、キーパーソンの紹介であれば変な対応はできませんからね。そして、時々キーパーソンとも進捗状況を確認する必要があります。まずキーパーソンときちんと話すことがビジネスのスタートですが、その後はキーパーソンと担当者という二重構造で、同時並行的に進めることがとても重要です。
Q. キーパーソンへの働きかけはどれくらい必要なのでしょうか?
交渉を成功させるためには、相手国のキーパーソンにしつこいと思われるくらい、継続的に接触することが何よりも大切だと思います。とはいっても、国会会期中に日本の大臣や副大臣などが頻繁に海外に出張するのは難しいため、私は、首相からの相手国大統領宛ての親書や、総務大臣からの所管大臣宛のレターをいただき、それを持参して南米に行きました。2008年7月からの2年間で南米を24回訪問し、月1回は南米に行き、現地の日本国大使とともに相手国の大統領や大臣等と会いました。過去に1回ないし2回面会していれば、その後は電話やレターでもかまいませんので、キーパーソン同士が時々接触をして、相手に繰り返し働きかけることが重要だと思います。
当時私は総務審議官の職でしたので、英語ではVice-Minister for Policy Coordinationと翻訳され、相手国の大統領や大臣にアポイントを入れやすかったことはあります。しかし、私のように政府としてではなく、民間企業が売り込みに行ったとしても、現地大使館との連携があればキーパーソンに会えると思います。多くの場合、相手国の大統領や大臣とのアポイントをとる際に現地大使館の裏打ちがあれば先方も安心しますので、今回の南米での活動にも、外務省との協力が必須でした。現地大使館は情報を持っていますので、相手国のニーズを知るうえでも、外務省や現地日本国大使館との連携がとても重要なのです。
Q. 相手国のキーパーソンに接触することが大切なのですね。
実は、このように相手国のキーパーソンに会って交渉をすることは、世界のビジネスでは珍しいことではありません。例えば2009年、日本航空の再建に当たり、アライアンス(企業提供)先をアメリカン航空にするかデルタ航空にするかで問題になったとき、両航空会社のCEO(最高経営責任者)がすぐに国土交通大臣と日本航空のトップに直接話しに来ました。
一般的に日本では、最終合意の場ではない、勝敗の行方が分からない交渉の場に企業の代表者が出席することはほとんどありません。代表者は最後の契約の時にだけ出席することが多いですね。しかし、日本の企業がグローバル化を本気で行いたければ、企業のトップが相手国のキーパーソンにアポイントを入れて、まず、直接働きかけることをもっと日常的に行うべきでしょう。大きい仕事をやろうと思ったら、企業のトップもある程度のリスクを覚悟して勝負しなければならないと思います。