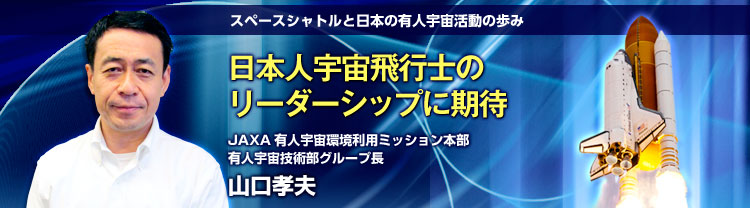Q. シャトルミッションで特に印象に残っているミッションは何でしょうか?

帰還した直後のスペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-114)(提供:NASA)

STS-114の打ち上げ。この後にスペースシャトルの外部燃料タンクの断熱材が剥離した(提供:NASA)
一番印象に残っているのは、2005年7月の野口宇宙飛行士が搭乗したスペースシャトルの飛行再開ミッションです。コロンビア事故の後、約2年半ぶりの打ち上げということだけでなく、私が今の部署に移って初めて担当したミッションでしたので、大変緊張したのを覚えています。
当時、野口宇宙飛行士は絶対に飛ぶという確固たる意思を持っていましたので、私たちも飛ばせたいと思っていました。でも自分たちの目でスペースシャトルの安全を確認するまでは飛ばすわけにはいきません。ですからJAXA内で検討チームを立ち上げ、NASAの再発防止策を1点、1点確認し、時にはNASAの現場に行って確かめました。それで大丈夫だという判断となったので、JAXAは野口宇宙飛行士のスペースシャトル搭乗を決心したのです。
でも、やはり打ち上げの時はドキドキしましたし、帰還するまでは安心できませんでしたね。しかも、このSTS-114ミッションでは、打ち上げ後に外部燃料タンクから断熱材の一部が剥離(はくり)したり、スペースシャトルの耐熱タイルが一部損傷したりしました。ミッションは問題なく最後まで行われたのですが、その報告を聞いた時は緊張が一気に高まりました。地球に帰還するまでは、いつ何があっても対応できるようにずっと身構えていたという感じでしたね。
Q. スペースシャトルの事故で得た教訓は何でしたか?
有人宇宙飛行にはリスクがあるというのは分かっていましたが、何か1つ見逃すことによって大事故につながるというのを改めて実感しました。事故の後は、JAXA内部でも、これまで以上に徹底的に飛行前の準備を行っています。あらゆる不具合を想定し、それについてどう対応するかの手順を皆で話し合い、その手順を訓練でシミュレーションして確認する。というような危機への備えを万全にしているのです。
また、コロンビア号の事故をきっかけに、私たちは家族の支援について見直しました。ミッションで何か起きた場合には隠さず、正直にすべて話すように心がけました。ですからSTS-114ミッションの打ち上げ後に断熱材が剥離した時も、電話ではなく直接家族と会って、家族が理解するまできちんと説明しました。やはり一番怖いのは「隠す」ことだと思いますし、きちんと話すことで家族も私たちを信頼してくれます。しかし、家族から質問をされて生半可な返事をしたら不安にさせてしまうため、何を聞かれても答えられるよう、私たちにも勉強が必要でした。家族支援のあり方を変えたのも、事故から得た1つの教訓だと思います。
Q. スペースシャトルの引退が、日本の有人宇宙活動にどのような影響を与えると思いますか?

古川宇宙飛行士らが搭乗するソユーズTMA-02M宇宙船(提供:JAXA/NASA)
宇宙飛行の機会が少なくなることが一番大きな影響です。でもこれからの宇宙飛行士はロシアのソユーズ宇宙船に搭乗しますので、アメリカだけでなく、次はロシアの有人宇宙技術を学べる良い機会になると思います。ソユーズ宇宙船は翼のあるスペースシャトルと異なり、カプセル型の宇宙船です。ソユーズ宇宙船の訓練やフライトを通して、カプセル型の有人宇宙船の技術を蓄積したいと考えています。また、日本人が国際宇宙ステーション(ISS)に長期滞在する機会を最大限に利用し、顕著な成果を出す必要があるとも考えています。