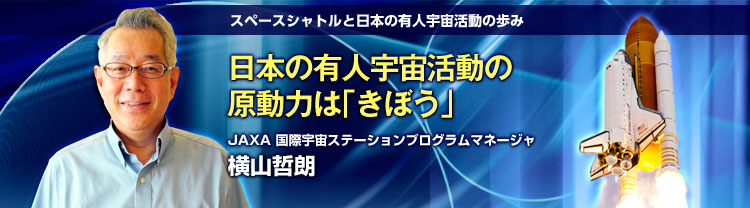Q. 「きぼう」の組み立てミッションをどのような思いで見ていましたか?

船内保管室に初めて入室する土井宇宙飛行士(左)(提供:NASA)
「きぼう」の組み立てミッションは、1回目は船内保管室の打ち上げで土井隆雄宇宙飛行士がこのミッションに搭乗し取り付けや整備などを行いました(2008年3月)。2回目は船内実験室とロボットアームを打ち上げ、このミッションには星出彰彦宇宙飛行士が搭乗しました(2008年6月)。そして3回目は船外実験プラットフォームおよび船外パレットの打ち上げで、若田光一宇宙飛行士が取り付けを行いました(2009年7月)。ISSの組み立てのために選抜した若田宇宙飛行士が「きぼう」を完成させて、最後を締め括ってくれたのは非常に嬉しかったです。
また、最初に「きぼう」の船内保管室のハッチが開けられた時はとても感慨深いものでした。日本が20年近い歳月をかけて開発した初の有人宇宙施設に、日本人が乗り込む歴史的な瞬間です。NASAの飛行管制官チーフの計らいで、私はジョンソン宇宙センター(JSC)のISSミッション管制室でその瞬間を迎えました。ハッチが開けられ、「きぼう」に入室した土井宇宙飛行士のメッセージが地上に届くと管制室は拍手に包まれ、私はとても晴れがましい気持ちになりました。その時の光景は、今でも私の脳裏に鮮明に残っています。
Q. 「きぼう」が完成するまでにどのような苦労がありましたか?

船内実験室がISSに取り付けられた直後のNASAの記者会見にて(提供:NASA)
「きぼう」の組み立てフライトは3便ありましたが、私は3便ともヒューストンにいて、シャトル飛行期間中に毎日行われるISSのマネジメント会議に出席していました。「きぼう」に限らず、NASAやヨーロッパで作られたものも初期設定での不具合は当然ありますので、その対処方法などを会議で決めていたのですが、国際協調の難しさはありましたね。
現在、「きぼう」は完成から2年以上が経ち、大きな問題もなくきちんと稼働しています。今では初期の不具合はすべて解決していますが、例えばこんなことがありました。
船内実験室を取り付けて間もない時に、冷却システムの立ち上げで不具合が発生したのです。船内実験室の機器は電気が入ると熱が発生しますが、この熱を取るのに水を使います。冷却水を循環させる配管をジャンパーホースで隣の「ノード2」(第2結合部)の熱交換器につないで、そこで船外に排熱します。そのジャンパーホースを接続した途端、配管内に気泡が混入した兆候が見られ、ジャンパーホースに水が充填されるべきはずがされていなかったようでした。この時はJAXAの技術チームが地上試験のデータに基づいて判断し、配管内の冷却水循環ポンプを一時的に増速して気泡を取り除くという対応策を編み出し、不具合を迅速に解決することができました。あらゆる事象を想定した地上での試験と、そのデータの蓄積が功を奏したのです。
その一方で、「きぼう」の不具合を未然に防いだこともあります。例えば先行していた欧州実験棟組み立てミッションで、欧州の管理コンピュータがアメリカ側と通信できない不具合が発生しました。ソフトウェアの修正で解決しましたが、これは「きぼう」の通信装置の立ち上げでも起こりうる不具合でした。日米欧で情報を共有してきたおかげで「きぼう」では問題とならずに済んだのです。
実はこうしたミッションの進捗状況は、NASAテレビの記者会見で毎日報告されますが、日本に関連する時は私も記者会見に出席して解説しました。3回の組み立てミッションで合わせて十数回の会見に出ましたが、日本で見られていることも意識しながら、専門性の高いアメリカの記者達にJAXAのプレゼンス(存在感)を示すべく質問を受けるのは緊張ものでしたね。「きぼう」完成の記者会見後に常連の古参記者が「(日本は)よくやった。おめでとう」と言ってくれた時は、それまでのさまざまな準備が報われたようで嬉しい気持ちになったのを覚えています。