地球温暖化が成層圏オゾンの対流圏への降下を促進
- ますます温暖化が加速 -
海洋科学技術センター
宇宙航空研究開発機構
概要
海洋科学技術センター(理事長 平野拓也)と宇宙航空研究開発機構(理事長 山之内秀一郎)の共同プロジェクトである地球フロンティア研究システム大気組成変動予測領域の秋元肇領域長、高橋正明グループリーダー(東京大学気候システム研究センター教授兼任)と須藤健悟研究員は、地球温暖化が進行すると、成層圏オゾン(注1)の対流圏への降下量が増加することを化学・気候モデル実験によって明らかにした。(図1,図2)この対流圏へのオゾン流入量の増加により温暖化が更に加速される可能性が示唆される。
この成果は、アメリカ地球物理学会速報誌「Geophysical Research Letter」の第30巻24号に掲載され、2月末に冊子が配布された。
背景
オゾンなど大気中の化学反応によって生成する物質が、地球温暖化による気候変動によってどのような影響を受けるか、そしてその変化が気候にどのようにフィードバックされるかは、化学-気候相互作用と呼ばれて最近大きな関心が持たれている。特に対流圏オゾン(注2)は気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 第3次報告書で二酸化炭素、メタンに次ぐ第3の最も重要な温室効果ガスであるとされ、温暖化・気候変動との関わりが注目されている。
地球フロンティア研究システムでは、こうした温室効果ガス増加に伴う気候変動等の現象を解明するために、対流圏化学過程とその気候への影響を地球全体で計算することが出来る化学・気候モデル"CHASER"(注3)を東京大学気候システム研究センター及び国立環境研究所と共同で開発し、オゾンなどの大気汚染物質の将来の分布の変動や、その気候影響の予測を行っている。
成果
IPCC から提案されている排出シナリオのひとつであるA2(多元化社会)シナリオ(参考1)に従い、オゾンの増加を計算すると、オゾンの鉛直分布には、温暖化の影響を考慮した場合としない場合とで大きな違いが出ることが分かった。温暖化を考慮した実験の結果によると、中低緯度の対流圏上層部のオゾンの量が大きく増加している。これは、温暖化によって成層圏と対流圏での大気循環が共に強まり、成層圏からのオゾンの流入量が増加するためであることも分かった(参考2)。
対流圏上層部のオゾンの増加は、強い温室効果を持つので、地表面気温の上昇に、より顕著な影響を及ぼすことが知られている(参考3)。したがって本成果は地球温暖化により対流圏上層部のオゾンが増加し、このオゾン増加がさらに温暖化を加速する可能性があることを意味している。
- 問合せ先
地球フロンティア研究システム 担当:太田
Tel:045-778-5687 Fax:045-778-5497
URL: http://www.jamstec.go.jp/frsgc/jp/
海洋科学技術センター 総務部普及・広報課 担当:鷲尾、五町
Tel:046-867-9066 Fax: 0468-67-9055
URL: http://www.jamstec.go.jp/
宇宙航空研究開発機構 広報部
Tel:03-3438-6107〜9
URL: http://www.jaxa.jp/
注1:成層圏のオゾン:
成層圏では、太陽からの強い紫外線が存在し、大気中の酸素(O2)を分解し,できた酸素原子(O)と酸素分子(O2)からオゾン(O3)が形成される。同時に、オゾンは光を吸収して分解し,酸素原子と酸素分子に戻る反応が起こり、この際、地球の生物に対して有害な紫外線を吸収する。
注2:対流圏(地表)のオゾン:
対流圏では、自動車や工場等から排出される二酸化窒素(NO2)が、太陽光により酸素原子と酸素分子に分解され、オゾンが形成される。光化学スモッグの主な原因で、生物にとっても有害な大気汚染物質。IPCC第3次報告書では二酸化炭素、メタンに次ぐ第3の最も重要な温室効果ガスであるとされている。
注3:CHASER(Chemical AGCM for Study of Atmospheric Environment and Radiative Forcing):
CCSR(東京大学気候システム研究センター)/NIES(国立環境研究所)/FRSGC(地球フロンティア研究システム)の気候モデルに光化学反応を組み込んだ気候モデルで、窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)、二酸化硫黄(SO2) などの汚染前駆物質の放出、大気中輸送・化学反応、降水除去などを計算し、オゾンや硫酸エアロゾルなどの生成・分布を全球的にシミュレートできる。
注4:ハードレー循環:
赤道付近で上昇し、南北30度あたりで下降する大気の循環。

図1
(上図): A2シナリオを用いて温暖化を考慮した実験による全球平均地表気温上昇の時間発展。
(下図): 成層圏から対流圏への正味のオゾン降下量(全球年間総量)の時間発展。温暖化の進行に伴って流入量の増加が予測されており、この実験では 2100 年までに 83% のオゾン降下量の増加が計算された。
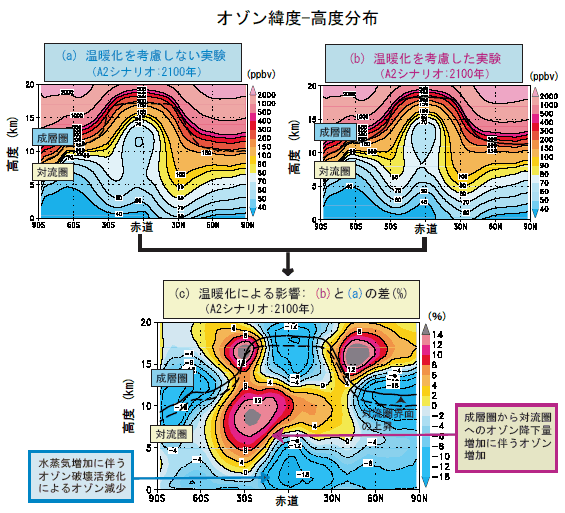
図2
上図(a,b): IPCCから提案されているA2シナリオを用いて計算した将来(2100年)のオゾン緯度-高度分布。(a):温暖化を考慮しない場合、(b):温暖化を考慮した場合。いずれの場合も対流圏中ではオゾン前駆物質放出量の増加により現在よりも30〜60%高いオゾン濃度が予測されている。
下図(c) : 温暖化によるオゾン濃度への影響(%)。対流圏下層では温暖化に伴う水蒸気増加によりオゾン減少となっているのに対して、対流圏上層では成層圏からのオゾン降下量の増加により中低緯度の広範囲にわたりオゾン増加となっている(この温暖化によるオゾン増加は現在から2100年までに気体放出量増加のみで予測されるオゾン増加量の20〜40%に相当する)。対流圏上層のオゾン変動は地表気温への影響が大きいため、温暖化による対流圏上層のオゾン増加が更に温暖化を加速する可能性が示唆される。

参考1:IPCCの世界発展シナリオ・排出シナリオ。「経済重視」または「環境重視」、「国際化」または「地域主義」の観点から世界発展のシナリオを分類している。
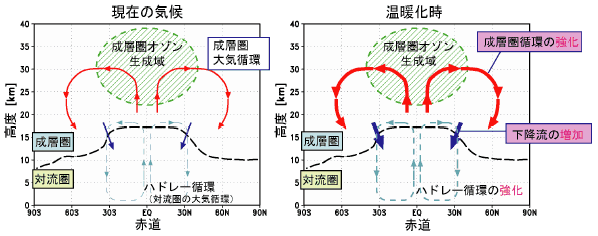
参考2:このモデル実験では温暖化時に成層圏及び対流圏の大気循環の変動(強化)が予測されている。
このような大気循環の変化により成層圏では赤道域から亜熱帯下部成層圏へのオゾン輸送が増加し、さらに対流圏の大気循環の変動に伴う下降流の増加により成層圏から対流圏へのオゾン流入が活発化する。
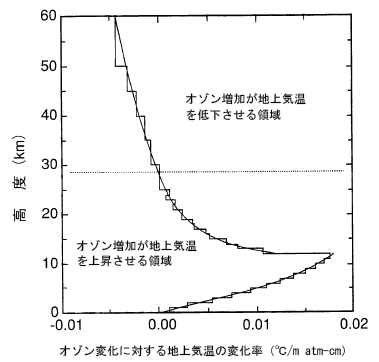
参考3:オゾン変化に対する地上気温の変化率の高度依存性
高度10Km 付近の上部対流圏のオゾン増加が、地上気温の上昇に最も有効である。
|
|
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910