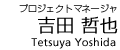気球という言葉から多くの方はアドバルーンや熱気球、飛行船を思い浮かべられるかもしれません。私たちが開発・運用している科学実験用の大気球は、人工衛星やロケットと並ぶ宇宙への飛翔体で、重量数百kg以上の搭載機器を高度30〜50kmの成層圏に打ち上げることができます。大気球はヘリウムガスの浮力で飛翔しますので、人工衛星やロケットのように大気圏を脱出できませんが、搭載機器に対する大きさや重量の制限が緩やかで、国内でだけでも数時間から一日程度の飛翔機会を年間10回以上、提供できます。
このような大気球の特徴を活かし、最先端の科学観測実験や工学実証実験に加えて、将来の宇宙科学を切り拓く独創的かつ先駆的な観測機器や飛翔体の性能試験を数多く実施し、宇宙科学の分野と知見の拡大に大きく貢献してきました。
より大きく重い搭載機器を、より高く、より長時間飛翔させることは気球開発の永遠のテーマです。さまざまな科学観測や工学実験がこのような気球の実現を待ち望んでいますし、また次世代気球の開発が新しい宇宙科学の研究を生み出します。大気球プロジェクトでは、成層圏を越えて中間圏を飛翔する日本独自の超薄膜高高度気球の開発を行ってきました。2002年には厚さ3.4ミクロンのポリエチレンフィルムで作られた気球により高度53.0kmの無人気球の世界高度記録を達成し、さらに薄いフィルムによる、より高高度での飛翔を実現する研究を続けています。数十日間一定の高度を飛翔できるスーパープレッシャー気球の開発でも、世界で初めての実用化を目指しています。気球が地球以外の大気をもつ惑星で長期間探査を行う日も近い将来やってくるでしょう。
世界最初の熱気球が飛翔してから200年以上経ちますが、気球はまだまだ進化していきます。大空に優雅に浮かぶ気球の可能性をもっともっと拡げたいと思います。
このような大気球の特徴を活かし、最先端の科学観測実験や工学実証実験に加えて、将来の宇宙科学を切り拓く独創的かつ先駆的な観測機器や飛翔体の性能試験を数多く実施し、宇宙科学の分野と知見の拡大に大きく貢献してきました。
より大きく重い搭載機器を、より高く、より長時間飛翔させることは気球開発の永遠のテーマです。さまざまな科学観測や工学実験がこのような気球の実現を待ち望んでいますし、また次世代気球の開発が新しい宇宙科学の研究を生み出します。大気球プロジェクトでは、成層圏を越えて中間圏を飛翔する日本独自の超薄膜高高度気球の開発を行ってきました。2002年には厚さ3.4ミクロンのポリエチレンフィルムで作られた気球により高度53.0kmの無人気球の世界高度記録を達成し、さらに薄いフィルムによる、より高高度での飛翔を実現する研究を続けています。数十日間一定の高度を飛翔できるスーパープレッシャー気球の開発でも、世界で初めての実用化を目指しています。気球が地球以外の大気をもつ惑星で長期間探査を行う日も近い将来やってくるでしょう。
世界最初の熱気球が飛翔してから200年以上経ちますが、気球はまだまだ進化していきます。大空に優雅に浮かぶ気球の可能性をもっともっと拡げたいと思います。