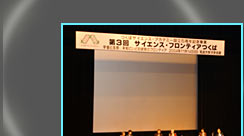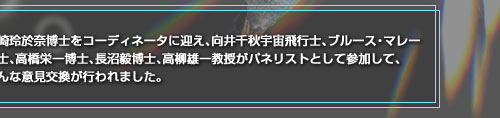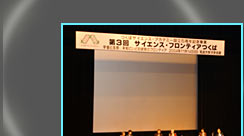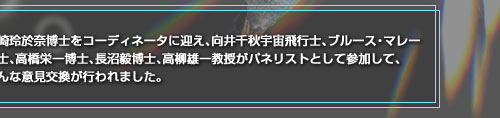| IIT技術は非常に速いスピードで進化し、それにともなってコストが下がっています。その技術は、宇宙だけではなくあらゆるところを網羅し、私たちは'60年代とはまったく違う世界に暮らしています。人類は、より内面的に、そしてより相互に情報伝達を行う種へと変化しているともいえるのです。社会が変わり、世界が変わっています。私たちはいわば非常におもしろい歴史の道筋の中にいるということになると思います。おそらく何らかの境界にいるといっても過言でもないでしょう。
テクノロジーが進むにつれて、ロボットが宇宙へ送り出され、新しい世界が広がっていきます。そして、次に人間が行くかというとそうではありません。有人飛行の発展のスピードは、ITの進歩のような段階には至っていないのです。現時点では、最も優れた人たちを選んで宇宙へ送っているわけで、毎年増えていくわけではありません。コストを考えると、宇宙へ行くのは当面“どこにでも行くことができる”ロボットということになるでしょう。一方で、人間はロボットを情報のツールとして使うユーザーとなり、見つけたものを総合的に判断する本来の意味での探検家となるのです。
国際宇宙ステーションやスペースシャトルは、1970年代の概念であり、これは、明確なビジョンがあった1950〜'60年代の新しい夢や希望を反映したものなのです。
今こそ、ロシア、日本、アメリカ、中国などが、何らかの形で有人宇宙開発をIT技術の時代に合わせ、もっと安価で効果的なものにしていく必要があると思います。そうしなければ、継続的な宇宙開発は、金銭的な負担に耐えられなくなってしまうでしょう。
なぜロボットが安いのか。それはテクノロジーが進んでいるから、そして、地球に戻って来る必要がないからです。テクノロジーの進歩は、コストを下げ、地球上の発展も進めるでしょう。
アメリカは、1999年の火星探査機マーズ・ポーラー・ランダーとマーズ・クライミット・オービターを失った時のような悲しみを、もうこれ以上味わいたくありません。その思いが、今回のスピリットとオポチュニティという2台の火星探査機を成功に導いたのです。一方で、アメリカ政府はコロンビアの事故以来2年間以上も人を宇宙へ送っていません。今後の有人宇宙飛行に対してはこれまで以上の費用をかけることになるでしょう。
|