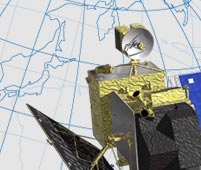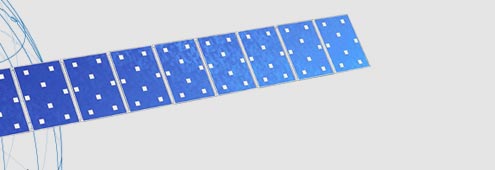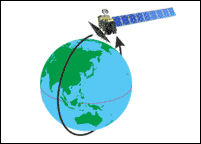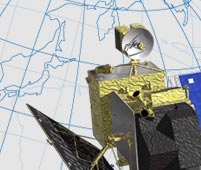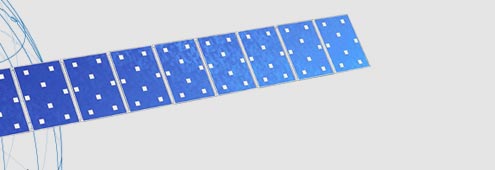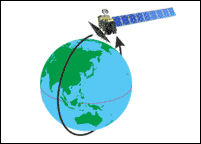|


「だいち」全景

データ中継技術衛星「こだま」を用いた伝送
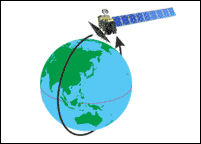
太陽周期軌道(だいち : 高度 約692km 周期 約100分) |
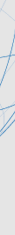 |
これまでの世界の地球観測衛星には、「だいち」(分解能2.5メートル)よりも分解能の低いアメリカの「ランドサット」(分解能30メートル)やフランスの「スポット」(分解能10メートル)と、「だいち」よりも分解能の高いアメリカの商用衛星「クイックバード」や「イコノス」(分解能1メートル程度)があります。これらの世界の地球観測衛星の中で「だいち」の位置づけは、商用衛星(クイックバードやイコノス)よりも精度が少し低いですが、従来の地球観測衛星(ランドサットやスポット)よりは詳細で、なおかつ46日間で全地球のデータを取得できるという中間的な機能をもった衛星です。これは世界にない、日本独自の特徴をもった衛星だといえます。今後は、これらの複数の衛星データを合わせて解析することも考えられます。例えば、「だいち」が観測したある地域のもっと詳細なデータがほしい場合には、商用衛星の高分解能データで見るとか、逆にもっとグローバル(広域)な評価をしたい場合は、2000キロメートルぐらいの範囲で地表を見ることのできる衛星のデータを組み合わせるなど、その目的によっていろいろな可能性が出てくるでしょう。
「だいち」の最も優れているところは、短期間である精度の地球全域を観測できるので、速報性が求められる災害対策などに最も適していることです。「だいち」は、これまでの地球観測衛星と違って、緊急観測が必要になると、センサやレーダの首フリ機能で任意の地点を観測することができます。その場合、光学センサとレーダのどちらかの観測機器しか使用できませんが、任意の目標を捕捉するのに最大で2日かかります。ただし日本の場合には、緯度の関係で、最大1日くらいの遅れで緊急観測したい場所を捕捉できると思いますので、災害時の利用価値はかなり高いと思っています。 |

「だいち」の目的は高分解能の地図の作成や災害状況の把握だけでなく、地球規模の観測による資源探査など、通常の生活にある程度密着したデータを提供し、幅広く利用していただくことが可能です。
例えば、「だいち」のレーダを使うと氷が映りますので、海上保安庁がそのデータを使って、冬期のオホーツク海の流氷情報を提供する予定になっています。また、農林水産省が水田の作付面積を管理したり、国土地理院が地図の更新をするのにも、「だいち」のデータが使われる予定です。これらは、地上の計測や航空写真などから既に作成されたものがありますが、今後は「だいち」によって情報を補填し、さらに精度の高いものになればと思います。このように、行政関係がメインユーザーですが、その他、地震や地殻変動の共同研究なども含め、間接的には、一般の方の生活にも「だいち」のデータが反映されるだろうと考えています。
「だいち」は陸域観測衛星ですから、地球の温暖化や、ガスの部分を計測するというようなセンサは搭載されていません。しかし、森林を認識する能力がありますので、地球レベルの森林分布図を作る計画が進められています。まずは、アジア地区を作成し、それから全地球規模のものを作る予定です。
また、「だいち」に搭載されている近赤外のセンサでは、都市化の状況を10メートル単位の精度で調べることができます。都市計画による環境の劣化状況などを把握し、環境汚染の悪化を防ぐのに役立てればと思います。
私たちの地球を守るためにも、世界的な環境管理を考えて貢献していきたいと考えています。 |
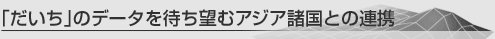
アジアをはじめとする発展途上国の中で、「だいち」に期待する声が高まっています。日本がある程度リードしていく必要もありますが、最近は、アジア各国が、宇宙開発やリモート・センシングに力を入れてきています。例えば、タイのGISTDA(タイ国家地理情報宇宙技術開発機関)は、タイ周辺のデータを渡してもらえれば、その処理や評価は自国でやりますと言っていますし、インドネシアとも、データ解析の共同研究についての協議を行っているところです。
日本では、全土を網羅している地図は最大縮尺2万5千分の1ですが、ほかのアジアの国では詳細な地図のない地域がたくさんあります。「だいち」は、全世界の標高も含め、2万5千分の1の地図ができる技術をすべて搭載していますから、そのデータをアジア各国に利用していただけたらと思います。詳細な地図が整備されると、土地の利用や災害対策にもきっと役立つでしょう。JAXAは今後も、アジア諸国への技術支援を続け、各国と連携していきます。
|
|
 |