|
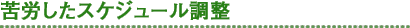
|
H-IIAロケットは私が常駐している種子島宇宙センター、そしてM-Vロケットは内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられます。H-IIAロケットとM-Vロケットの打ち上げチームは別ですが、約1ヶ月の間隔で打ち上げられたH-IIAロケット8号機と9号機のメンバーはほとんど同じです。今回初めて2機同時に打ち上げ準備をしましたが、共通で使用する設備や作業者のスケジュールを調整するのが大変でした。
H-IIAロケットの場合、通常打ち上げの1ヶ月半前にロケットを種子島に搬入し、作業を開始します。ロケットは、ロケット組立棟で2段目まで組立て、点検を行い、衛星組立棟等でおこなわれている衛星の準備が終わるのを待ちます。衛星の準備が終了したら、衛星を保護するためのフェアリングに衛星を収納します。衛星がロケット側に引き渡しされるのが、打ち上げの約2週間前で、2段目と結合するのが約10日前です。それ以降は、ロケットと衛星の担当者が、同じ場所で並行作業、共同作業を行うことになります。
今回は、最初にH-IIAロケット8号機の組立てを行い、衛星との合同作業の直前で待機状態とし、9号機の組立て、点検作業にとりかかりました。そのうちに8号機に搭載する衛星「だいち」の準備ができると、9号機の作業を休止して、8号機の作業を進めるというように、交互に作業をしましたから、8号機と9号機の作業を同時におこなうことはありませんでした。これらの作業を円滑に行うために、どのように人を配置し、どのように設備を使うとか、どのようにしたら効率よく進められるかスケジュールを検討するのが一番大変でした。スケジュールが決まったのは、昨年の10月から11月初旬です。
スケジュールが決まりますと、あとはそれに従って進めていくだけで、実際の作業は順調に進みました。ただ、その日に予定されていたスケジュールを確実にこなすという意味では、遅くまで作業をするなど努力したこともありました。
種子島にはもともと2機同時に組立て・点検できる設備を整備していますが、それを実践したのは今回が初めてです。スケジュールの調整で苦労はしましたが、種子島宇宙センターの設備を効率よく活用できたと実感しています。今後打ち上げ回数が増えて、短期間で準備する必要があった場合でも、対応できるという実績と自信ができました。 |
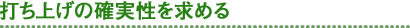
|
当初1月19日に予定されていたH-IIAロケット8号機の打ち上げは、装置の異常や天候不良で延期され、5日後の1月24日に行われました。確かに、打ち上げ延期となると、スタッフ皆の気持ちが一瞬落ち込みます。しかし、ロケットを確実に打ち上げるための延期は、正しい判断だと思います。
H-IIAロケットの場合、少々の雨は問題ありませんが、雷が発生すると打ち上げはできません。ロケットに搭載されている電子機器が雷で壊れると、制御できなくなってしまいます。また、風に対する制約もあります。ロケットはゆっくり上がっていきますので、まだスピードが出ないうちに突風が横から吹き付けると、進路が横にずれて、発射台の構造物にぶつかる可能性がでてくるからです。このように、天候によって左右されますから、打ち上げ時刻にこうなるという正確な気象情報が必要になってきます。
種子島宇宙センターでは、専任の気象予報士が常にデータを見ています。気象庁からの各種データの受信、射場の80メートルの気象塔などでの気象観測、過去のデータとの比較等を行い、独自に予報しています。最近の気象予報の精度はあがり、翌日の何時から何時の間に雨が降るとか、雷がくるというのが分かります。1〜2時間のずれはありますが、ほぼ間違いなく90パーセント以上的中します。
H-IIAロケットは液体燃料を使いますが、液体燃料は蒸発して気化しますので、タンクに入れたまま長期保存することができず、打ち上げ直前に充填します。燃料を充填してから延期が決まると、燃料タンクから一旦燃料を排出し、また再充填のために数日間かかります。そのような延期を防ぐためにも、燃料を充填する前に的確な判断が必要なのです。 |
|
|

第1射点から見た9号機(手前)と8号機(奥) |

衛星が保護されているフェアリングを、衛星組立棟から大型ロケット組立棟へ移動 |

大型ロケット組立棟から第1射点へ移動中の8号機
|
|
|