| |
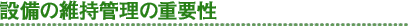
|
種子島宇宙センターは、種子島の東南端の海外線に面していて、海の青さと、ロケットが打ち上がっていく瞬間がマッチした時は最高です。特に夏は、太陽の光が海に反射してとてもきれいで、そういうところから「世界一美しいロケット発射場」といわれているのだと思います。しかし設備にとっては良い環境とはいえません。潮風が設備に直接吹きつきますから、塩分がついてとても錆びやすいのです。このため、水洗いをして、できるだけ錆びないよういつも注意しています。打ち上げ後は設備がロケットの燃焼ガスで損傷しますので修理します。修理した後、次の打ち上げに問題なく使えるかを点検します。計器類は、標準器と比較して狂いがないかなどを調べ、狂いがあったら直します。個々の設備の点検後、設備を組み合わせてのシステム点検を行い、次のロケットを待つこととしています。
射場の仕事はロケットや衛星はよく目立ちますが、それらの作業に使用する打ち上げ設備と、それを整備する人材がいなければ、打ち上げは成り立ちません。私たち設備関係者は打ち上げにも参画し、自分たちがこの設備をきちんと維持・管理しているんだという自覚をもって作業しています。目立とうなんていう気持ちはなく、「打ち上げを成功させたい」という気持ちでやっています。私は、宇宙センターでの仕事に誇りを持っています。 |
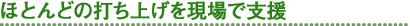
|
私は、種子島からの打ち上げにほとんど携わってきました。この30年間で、人工衛星を搭載したロケットの打ち上げを37回現場で見てきました。嬉しかったこと、辛かったこと、種子島にはたくさんの思い出があります。嬉しかったことで鮮明に覚えているのは、1975年9月9日に打ち上げられたN-Iロケット1号機で、これが私にとって初めての打ち上げでした。当時私は飛行安全班で、「ワイヤスカイスクリーン」という木の枠にワイヤーを張って、その線に沿ってロケットが飛んでいくかどうかを見る係でした。この時が日本初の垂直発射方式で、それ以前は発射台で角度をつけての斜め発射でした。理屈の上では分かっていても、感情としては半信半疑で、本当にうまく上がっていくのだろうかと心配でした。それが、目の前でゆっくりと上がっていき、しかも、ワイヤスカイスクリーンの枠内で、線に沿って飛んでいったので、すごく感動しました。今でもその時の光景を思い出します。
また辛かったことは、やはり失敗した時です。1999年11月のH-IIロケット8号機の打ち上げ失敗の時は、国土交通省航空局および気象庁の衛星「運輸多目的衛星」を搭載していて、私は航空局や気象庁の方たちとの対応窓口の責任者であり、また、ロケットの機体を調達する関係の責任者でもありました。その時の打ち上げは途中まで正常でしたが、1段目の燃焼が突然停止し、私は何事が起きたのか分からず唖然としました。しかし、その30分後には、責任者として記者のところに行って状況を説明しなければなりませんでした。私は落胆する関係者の方々を見て、大変な迷惑をかけてしまったと、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。原因究明を徹底的に行って、次の打ち上げを実施できたのが2001年8月のH-IIAロケット試験機1号機です。私にとって、失敗から成功までのその2年間はとても辛い経験でした。H-IIAロケット試験機1号機の打ち上げが成功した時は、涙が出そうなくらい嬉しかったです。この気持ちは、のちのH-IIAロケット6号機の失敗のあとに、7号機の打ち上げを成功させた時も同じです。
これからはもう絶対に失敗をおこしたくない、あってはならないと強く思っています。100パーセントに近い状態で打ち上げに臨むことができるよう、皆で一丸となって取り組んでいきたいと思います。 |
|
|

大型ロケット発射管制棟。通称ブロックハウス |

発射管制室。打ち上げの各段階の作業の指揮、操作、監視がおこなわれる |

総合指令棟。打ち上げ作業の各責任者が入り、全ての情報がここに集まる |

総合指令室で作業中の私
|
|
|