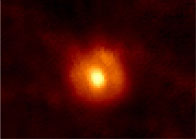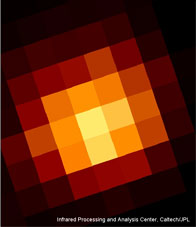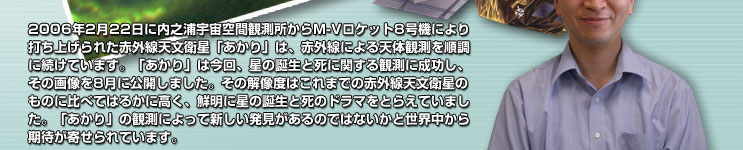

Q.「あかり」の最新画像で分かったことを教えてください。
これらの画像から、星の誕生と死の過程の新しい姿が見えてきました。
まず、ケフェウス座の散光星雲IC1396の赤外線画像です(※図1)。IC1396は私たちの太陽系から3000光年弱の距離にあって、太陽の数十倍の質量を持つ重い星が生まれている領域です。星は最後に大爆発をして死んでいきます。それを超新星爆発といいます。数百万年ほど前に誕生した星たちが、最期に超新星爆発を起こすと、ガスをその周囲に掃き寄せます。画像の中央付近で、星間ガスが吹き払われ空洞になっているところがそれに相当します。そのようにして吹き寄せられた星間ガスは、空洞の周囲で圧縮されて密度が濃くなります。そこで新しい星が誕生します。図1で、赤外線で明るく輝いてみえるところが、このようにして、新しい星が生まれつつあるところです。このIC1396領域は、このようにして、星の形成が連鎖的に起きている領域なのです。「あかり」は、掃き寄せられた星間ガスの分布や、そこで星が生まれつつある様子を鮮明にとらえました。これは世界初のことです。
次の画像は、太陽から約500光年の距離にある赤色巨星「うみへび座U星」です(※図2)。太陽程度の質量の星は、だんだん年老いてくると大きく膨れあがり、ぶよぶよ状態になり、表面から星を構成していたガスを宇宙空間に吹き出します。そのような状態の星を「赤色巨星」と言います。星から吹き出たガスは拡がるにつれて温度が下がり、その中でガスから塵が作られます。塵とガスは一緒になって拡がっていきます。この画像は、約1万年前に突発的にガスが吹き出し、その中で塵が作られ、それらが約0.3光年の距離まで拡がったところを観測していると考えられています。突発的なガスの噴出は、星の内部での核反応に関係していると考えられており、それを捉えた「あかり」の成果は、星の終末期の挙動を調べるための貴重な情報をもたらします。
また「あかり」は、試験観測中に、反射星雲IC4954付近の星が誕生する現場を鮮やかに描きだしました(※図3)。この領域は太陽系から約6千光年の距離にあり、数百万年前から星の形成が続いているといわれています。画像を見ると、ガスや塵の雲(星間雲)の中のいくつもの場所から、赤外線が強く放射されていることが分かります。これら一つ一つで星が誕生していると考えられています。星は、濃いガスや塵に囲まれた場所で誕生します。そのような場所は、可視光線では見ることができませんが、赤外線でこのように見透かすことができるのです。
同じ領域を、1983年に米・英・蘭の3カ国が協力をして打ち上げた世界初の赤外線天文衛星IRAS(アイラス)が観測しています。ただし、IRASの画像(※図4)では、何かがあることは分かっても、鮮明ではありません。「あかり」とIRASの画像を見比べると、目の前からヴェールが上がったという感じで、今まで見ていた世界とは全く違うという印象を受けます。「あかり」の方がはるかに高い解像度であり、「これで全天サーベイができるのは画期的なことだ」と、世界中の天文学者からたくさんの祝福をいただきました。解像度が高く、空間分解能があるというのは、細かい構造を見られるのはもちろん、遠くの宇宙を見ることができるということでもあり、とても重要です。
今までに公開された観測画像はほんの一例です。これからも、順次、皆さんに画像を紹介していきたいと思います。「あかり」は国内外の多くの皆様のご協力(注)により、ここまで来ました。今後、続々と出てくるであろう新しい科学的成果に期待しています。
注:「あかり」の焦点面観測機器の一つである遠赤外線サーベイヤは、情報通信研究機構からの検出器提供等を受け、名古屋大学、JAXA、東京大学、国立天文台等により開発されました。また、もう一つの焦点面観測機器である近・中間赤外線カメラは、東京大学、JAXA等により開発されました。「あかり」の運用とデータ処理は、上記国内研究機関と、欧州宇宙機関(ESA)、英国Imperial College London、University of Sussex、Open University、オランダUniversity of Groningen/SRON、及び、韓国Seoul National Universityとの国際協力により行われています。
| 1 2 3 4 |