
Q.「あかり」の後継機である「スピカ」の現在の開発状況
はいかがですか?
「あかり」は地図を作るミッションです。地図ができたら、次は当然、個別の天体を詳しく調べたいですよね。そのためのミッションが「スピカ(SPICA, Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics)」です。
望遠鏡の性能というのは、基本的には鏡の大きさで決まります。分かりやすく言えば、鏡が大きければそれだけたくさんの光を集めることができ、解像力も向上しますので、それだけ暗いものを見ることができるようになります。「あかり」の望遠鏡は口径約70cmですが、「スピカ」では口径3.5mの望遠鏡を搭載したいと考えています。これだけの口径にアップができれば、画期的に性能は向上します。「スピカ」をもってすれば、宇宙で最初に生まれた星を観測することができるかもしれません。また、私たちの太陽系以外の他の恒星のまわりにある惑星を直接的に観測できるようになるとも期待されています。
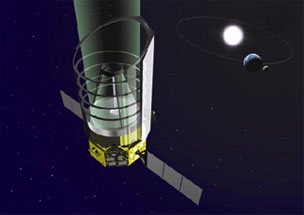 |
| 次世代赤外線天文衛星「スピカ」 |
そこで問題になってくるのが、望遠鏡をどうやって冷やすかということです。「あかり」の場合は、液体ヘリウムで望遠鏡を冷やしています。液体ヘリウムは気化しやすい液体なので、性能の良い魔法瓶を作る必要がありました。「あかり」の望遠鏡は11kgしかありませんが、魔法瓶全体の重さは460kgもあります。11kgの鏡を冷やすのに460kgも使っているのです。この方法で大きな望遠鏡を打ち上げようと思ったら、世の中に存在するどのロケットを使っても無理でしょう。ですから私たちは、「宇宙は冷たいのだから、宇宙へ行ってから冷やそう」という発想に変えました。そこで、機械式の冷凍機という、いわば超高性能冷凍庫エンジンのようなものを、JAXA総研本部や筑波大学と協力して開発しています。数年前から技術開発に取り組み、今では絶対温度1.7Kという超低温を達成する冷凍機が実験室では動いています。
また、もう1つの課題は、軽い鏡を作ることです。地上の望遠鏡のようにガラスを使って鏡を作っていては、大変に重いものになってしまい、宇宙には持っていけません。そこで、JAXA利用推進本部、総合技術研究本部、東京大学とも協力して、シリコンカーバイドという材料で軽い鏡を作ろうとしています。今は70cmの鏡を作って、極低温でも鏡が変形しないかどうかを調べている段階です。この材料を使うと、例えばハッブル宇宙望遠鏡のようなガラスの鏡と比べると、その10分の1くらいの重さで鏡を作れるのではないかと期待しています。
「スピカ」は2010年度半ばに打ち上げたいと提案しています。「スピカ」の詳細観測のためのガイドマップを作るためにも、「あかり」は大変に重要な役割を果たします。
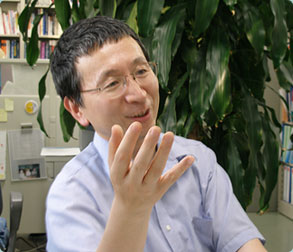
Q.天文学の面白さは何ですか?
天文学は自然科学の中で他と違う点が1つあります。それは、簡単に実験ができないということです。宇宙と同じ環境を実験室に作ることはできません。その理由は、まず時間がとてもかかるということ。星を1つ作るだけでも何十万年とかかります。また、非常に大きなスケールが必要であるということ。残念ながら、太陽のようなスケールのものを、実験室にはいれられません。ですから、宇宙というのはある意味では、壮大な実験室なんです。人類が絶対に作ることができないような環境が宇宙にはあります。例えば、アインシュタインが考えた一般相対性理論は、理論としては成立しますが、私たちが日常生活する上ではほとんど関係ありません。ところが、宇宙では日常茶飯事に一般相対性理論を考えなければなりません。宇宙は、私たちが頭の中だけで考えている理論を実証できる貴重な場所なのです。
また、天文学は、過去の宇宙を直接調べることができる非常に面白い学問だと思います。遠い天体を観測するということは、昔の天体を観測することです。例えば、10億光年離れた天体の光は10億年前に出た光ということになります。すなわち、10億年前の宇宙の過去の姿を見ているのです。したがって、宇宙はまるでタイムマシーンのようで、遠くの天体を見ることで、宇宙の歴史を直接に紐解くことができるのです。
「あかり」は、いわば、この「壮大な実験室」のなかを自在に飛び回る「タイムマシーン」なのです。「あかり」の観測によって、宇宙が繰り広げたドラマをこの目で見るのがとても楽しみです。
JAXA宇宙科学研究本部。赤外・サプミリ波天文学研究系教授。理学博士。専門は赤外線天体物理学。
1988年、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻課程修了。1990年に旧文部省宇宙科学研究所に着任し、1999年に教授となる。東京大学大学院理学系研究科・教授を併任。
| 1 2 3 4 | ||