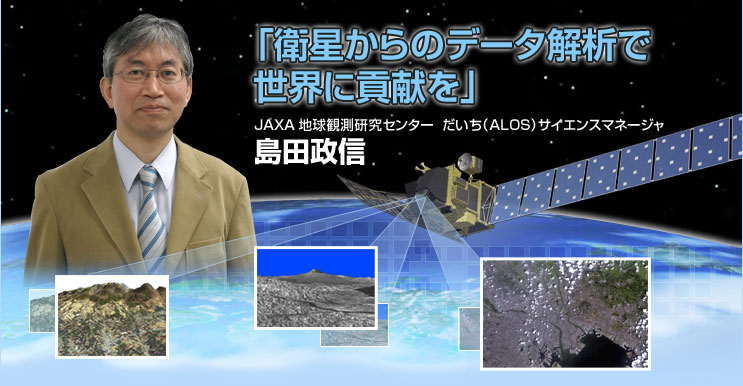
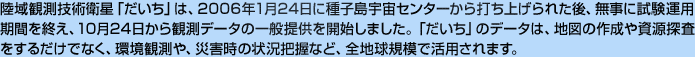
Q.島田さんが所属する地球観測研究センターでは、どのようなことをしているのですか? また、島田さんのふだんのお仕事を教えてください。
まずは地球観測衛星が観測するデータを解析し、センサの特性を調べ、外部利用者に提供する映像データの品質の維持や向上を行っています。一般に衛星が取得する観測データには、ノイズや縞が入っていたり、センサの地球を見る方向や地球の自転などの影響で歪(ゆが)んでいたりします。一例を挙げますと、真っすぐな道が歪んだり、平面が曲面に見えるといったようなことがあります。その歪みを補正し、ノイズを除去してデータを正しくすることを専門用語でキャリブレーションと言いますが、それがデータ取得後の最初の仕事です。キャリブレーションは基本的にコンピュータの中で行いますが、その処理をする数式を開発するのも私たちの仕事です。その数式の組み合わせをアルゴリズムと言いますが、衛星の劣化に応じてアルゴリズムを書きかえ、映像データの品質が落ちないよう調整します。私たちが年齢とともに耳が遠くなったり、目が悪くなったりするのと同じように、人工衛星も、打ち上げ直後の状態と、半年後、1年後、3年後では特性が異なり、観測画像も劣化していきます。過去のデータと見比べて、衛星の感度に変化がないかどうか、劣化してきていないかどうかをモニターし、感度劣化が判断された時には、既存のアルゴリズムの修正や、新しいアルゴリズムの開発を行います。
さらに、キャリブレーションが終わったデータを使って、地球環境の変化を抽出するとか、地震災害場所の抽出をする等の解析業務を行いますが、これらも地球観測研究センターの重要な仕事です。また、ノイズ除去をした画像から何が分かるか、どこで土砂崩れがあるか、どこで地盤沈下が起きているかといった災害状況把握なども行っています。
私の仕事は、データのキャリブレーションと応用解析技術の研究です。特に、衛星画像から地面の上昇や沈降などの変化を見つけるのが、私の研究の主なものです。
 フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)によるスキャニング(想像図) |
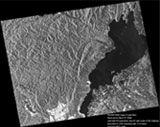 PALSARが観測した琵琶湖 |
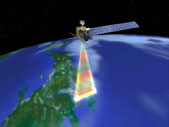 高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)によるスキャニング(想像図) |
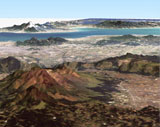 AVNIR-2で観測した阿蘇山の鳥瞰図 |
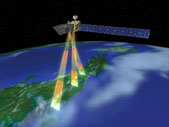 パンクロマチック立体視センサ(PRISM)によるスキャニング(想像図) |
 PRISMが観測した静岡県清水港 |
Q.2006年1月24日に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち」の観測画像は、これまでの地球観測衛星と比べていかがですか?
格段にいいです。海外の研究者の方からも、十分に使えるデータだと評価していただきました。私は主に「だいち」のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)を映像化する処理ソフトウェアの開発やその応用化研究に携わってきましたが、PALSARに関しては、手前味噌かもしれませんが、センサは非常に安定しておりますし、処理画像も十分に美しく、申し分のない成果を出しています。PALSARは、1992年に打ち上げられた地球資源衛星「ふよう1号(JERS-1)」に搭載された合成開口レーダ(SAR)の機能・性能をさらに向上させたもので、天候や昼夜に影響されることなく観測できます。SARとの大きな違いは、暗いものまでよく見える、分解能が向上したという2点です。画像の品質が良く、細かいところまで見えるので、例えば、琵琶湖の画像ですと真珠の養殖をしている筏(いかだ)まで分かります。
「だいち」には他にも2つのセンサが搭載されていますが、どちらも素晴らしい結果を出しています。高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)は、可視・近赤外域の波長を用いて、土地の表面の状態や利用状況を観測しています。また、パンクロマチック立体視センサ(PRISM)は2.5mの分解能で、衛星の進行方向に対して前方視、直下視、後方視の3方向の画像を同時に取得し、高精度の数値標高モデル(DEM)を作成しています。
「だいち」の観測データは2006年10月24日から一般に提供されていますので、皆さんにも幅広く活用していただけるものと思います。
| 1 2 3 4 |