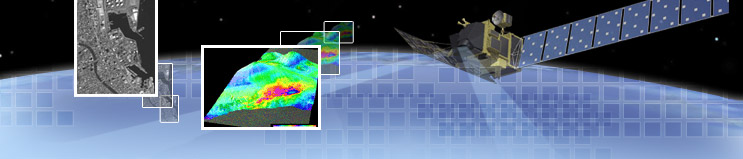
Q.地球観測の意義は何だと思いますか?
人工衛星の軌道から安定したセンサを用いて広域を繰り返し観測することで、正しい結果を恒常的に得られるというのが地球観測の大きな利点と考えます。それを活かして、近年、加速してきた地球環境変化を定量的に把握し、必要に応じてその結果を関係機関に提供し、また警告を発していけることに地球観測の意義があると思います。信頼性の高い結果については、センサの安定性の客観的な評価、校正、解析方法の評価が関わってきますが、1980年代以降に培ってきた技術の蓄積によって可能になったと思われます。
平たく言うと、短時間的、あるいは長時間的に、地球がどう変わっているかを見るということでしょうか。もちろん、技術面で問題がないというわけではありません。地殻変動においては、大気の揺らぎの影響など解決しなければならない課題が残っています。ただ、比較的、最終目標まで近づいてきたと思います。森林のバイオマス量の観測においては、1ha当たり60t以上の値で計測するという最終目標までまだ距離がありますが、この距離を近づけるのがチャレンジであるし、その技術的な問題点を克服できる可能性があるから地球観測を続けるのだと思います。
Q.データ解析の魅力は何ですか?
風の流れや波の動きなど、地球に現れるさまざまな現象、つまり地球の表情を、画像を通して感じられることです。そして新しい解析技術の開発によって、より効果的に可視化できることです。新しいアルゴリズムの作成には、試行錯誤が必要で、そう簡単にはいきません。衛星は運用期間が長くなると劣化し、常識では考えられないような縞が現れたり、品質が落ちたりします。しかし、観測データの特性を時間をかけて解析し、補正のためのルールを見いだし、処理アルゴリズムを改修することで正常に復帰した時や、処理ソフトウェアを改善して処理速度が上がるなどした時は、うれしくなります。これはデータ解析の世界だけでなく、他の分野にも言えることですが、努力した分だけ結果がついてまわるというのが面白い点です。
Q.島田さんはこれからどんな観測・研究をしていきたいですか?
「だいち」に関して言うと、1つ目は地球の物理現象の研究です。具体的に言うと、電離層です。電離層の密度は場所や時間によって変わりますので、その状況を調べてみたいです。2つ目は、差分干渉処理をする際に大気の影響を受けてしまうので、それを改善したいです。3つ目は、もっと大きな地球的視野で、地球の表面が動いている様子を見てみたいです。例えば、ヒマラヤ山脈とインドのデカン高原がぶつかり合った結果、インドシナ半島は東出し、そのぶつかり合いの度合いは1年間で数cmと言われています。このような地殻変動の状況を見てみたいです。また、画像を解析するためには、日本の国土地理院や気象庁だけでなく、外国の機関のデータも無償で使わせていただいていますので、地殻変動の予測や、災害予測というような形でフィードバックできたらと思います。
地球観測全般で言いますと、私はこれまで航空機搭載合成開口レーダの開発・研究や衛星搭載SARの利用研究をしてきましたので、引き続き、合成開口レーダに関連して視野を広げていきたいと思います。年々コンピュータの性能が上がり、処理速度が速くなったおかげで、より多くのデータを事細かく解析するソフトウェアやアルゴリズムを使えるなど、可能性が増えています。ですから、進歩する計算機と合成開口レーダを用いて、結果の高精度化を進めたいと思います。将来的には、全世界的な規模で木の高さを推定できればと考えています。「だいち」のレーダを使うと、濃淡の画像からバイオマス量がだいたい分かります。しかし問題は、そのようにして求められるバイオマス量は、高さ5m程の低木層のものなのです。それ以上の高い木については分かりません。木の高さや種類が分かるとバイオマス量は分かってきますので、将来、木の高さを測定できるレーダができれば、全世界的規模で木の高さ分布が出てきて、その高さを元にバイオマス量の分布図ができるのではないでしょうか。これはぜひ実現したいです。そして、さらに地球の理解が進んでくると、今度は月の軌道上に合成開口レーダを持っていって、月の表面の変化や資源探査をしてみたいと思っています。
JAXA宇宙利用推進本部。地球観測研究センター、研究領域リーダー。工学博士。
1977年、京都大学工学部航空工学科卒業、1979年、同大学修士課程修了。同年、旧宇宙開発事業団に入社、筑波宇宙センター・機器部品開発部でマイクロ波散乱計の開発、地球観測センターでJERS-1地上設備の開発とSARの研究、地球観測解析研究センター、地球観測利用研究センター、地球観測研究センターでSAR利用研究を行い、現在に至る。後方散乱係数を正確に測る理論研究を行い、1999年に学位取得(東京大学)。IEEE Geoscience and remote sensing学会会員、日本リモートセンシング学会理事、東海大学客員教授を兼任。
専門はマイクロ波リモートセンシング、合成開口レーダ処理、干渉SAR、多偏波SAR解析。
| 1 2 3 4 |



