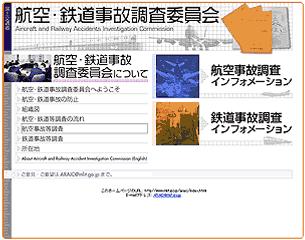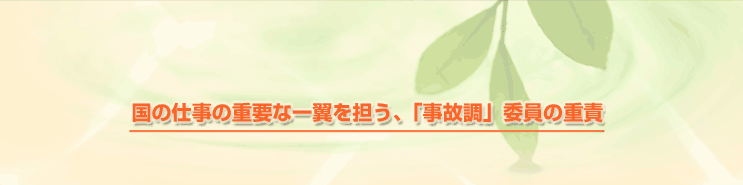 |
|
―― 「最年少で、しかも女性」と話題になりましたが、どんな経緯で航空事故調査委員に? 松尾 年末のとある午後、国土交通省のある課長さんが『お願いしたいことがあり、部長と一緒に参ります』と。 ―― だいたい要件は言わないものですよね、そういうときは。 松尾 ああいう役所の部長さんってけっこうエラいんだよね……、とか思っていたら、事故調の委員を依頼されてしまいました。びっくりしましたよ、雲の上の先生方がやることだと思ってましたから。でも、迷っても引き受けそうな気がしたのでその場で受諾のお返事をしました。2週間に1度、霞ヶ関に出かけるだけなら、と。 ―― 実際のお仕事は? 責任も重いでしょう? 松尾 考えていたより5倍ほどたいへんです(笑い)。まず委員のうち2人が欠席したら流会になってしまうので、休めない。行けば午前10時半から夕方までびっちり委員会があるし、何時間もかけて資料を読み込んでいかないとついていけない。でも、国がやるべき重要な仕事の一翼を担える、いい経験をさせてもらっている、と前向きに考えています。 ―― でもニュース報道などでそれほど頻繁に目にすることはないような気もします。そんなに忙しいんですか?
―― それで5倍たいへんだった(笑い)。 松尾 そうなんだそうですよ。 ―― ところで、過去の大きな航空事故は、それが痛ましい事故であったからこそ、金属の疲労破壊などといった材料や物性の新たな知識獲得につながる、という側面もありました。現在ではそういう「目新しい航空事故」は少なくなっていませんか? 松尾 現在飛んでいる飛行機、とりわけ大型旅客機はひじょうに安全な乗り物といっていいと思います。ジャンボジェットなど初飛行から30年以上も経っていて、改良が重ねられてきたわけです。不具合情報は速やかに世界的に共有される体制もできあがっている。 ―― 先生の場合、「爆発」「燃焼」などのご専門の分野を中心に、審議に関わるわけですか? 松尾 いえ、そういうことではありません。委員はどの分野にでも口を出していいんです。それに、私の専門分野が事故調の重要なポイントとなるような事故が、あったらたいへん。爆発物を満載したジャンボジェットがマッハ2で飛行中に……、というような、あり得ない事故ですからね。
|