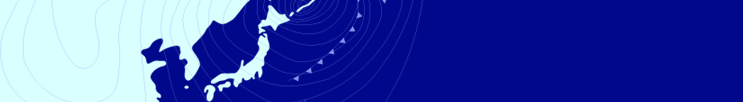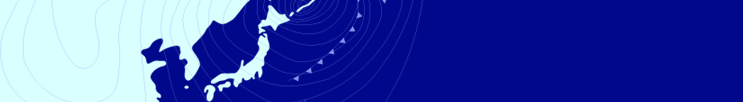気象衛星は天気予報になくてはならないものです。「レーダー」「アメダス」「気象衛星」は、天気予報の三種の神器。この3つがなければ、現在の天気予報はありえません。
「レーダーで雨雲を捉えているから、気象衛星かレーダーのどちらか片方でいいんじゃないか」と言う人もいますが、レーダーは実際に雨が降っているところに電波を飛ばして観測するのに対し、気象衛星は赤外線でもっと広い範囲の温度を観測することによって雲の分布や高さを測っている。そうすることで多面的に情報を得ることができるんです。 |
 |
| ■ |
アメダス
Automated Meteorological Data Acquisition System(地域気象観測システム)の略称。気象観測を地域ごとに細かく行うために、気象庁が1974年から全国に展開した自動気象観測システム。全国に約1300の観測点がある。 |
| ■ |
レーダー
短い波長の電波を発射し、大気中の降水粒子(雨滴、雪片)などに当たって返ってくる反射波を受信することによって、大気中の降水粒子の降水の強度、位置などを観測する装置。 |
|