
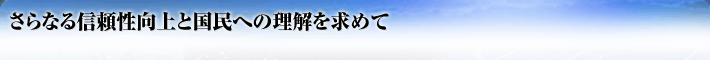

小惑星探査機「はやぶさ」
Q. JAXAに対する国民の関心は変わってきたと思いますか?また、国民の声をどのように受けとめていらっしゃいますか?
これまで国民の宇宙に対するご意見は、ロマンを求める夢物語的なことが多かったと思いますが、最近は、「宇宙を実用的な面で使ってほしい」という利用拡大に関心を持たれる方が多いようです。通信・放送・気象衛星という実績があって、その上で、防災や環境問題への対応など、新しい分野に衛星を利用してほしいということです。陸域観測技術衛星「だいち」が撮った画像が公開されて関心を呼んだこともあると思いますが、宇宙開発の成果に対する関心が高まり、国民の見方が変わってきたように思います。また、有人宇宙活動についての関心も高まってきています。「日本も意欲的に有人宇宙活動をやるべき」という国民の声が強まり国の政策に反映されれば、執行機関としてJAXAで推進していきたいと思います。さらに、小惑星探査機「はやぶさ」や月周回衛星「かぐや」の目立った成果もあり、宇宙探査への関心が高まってきました。「はやぶさ2」や「かぐや2」を作ってほしいというご意見が多いことも印象的です。
しかし、未だにJAXAがどのような活動をしているかご存知ない方もいらっしゃいます。なぜ国が宇宙航空の研究開発をやるのかということを理解していただくためには、やはり、JAXAから、自らの活動や成果に関する情報を積極的に発信いくことが重要です。これからも、広報活動に重点を置き、またタウンミーティングを開催して、国民との直接対話による意見交換の機会を持ちたいと思います。 JAXAはこれまでにタウンミーティングを21回行ってきましたが、これからも継続的に開催し、国民への理解を得るために努力していきたいと思います。

H-IIAロケット13号機
昨年1年間というよりも、私が2004年11月に理事長に着任して以来、この約3年間で少しずつ信頼性を向上してきたという実感があります。私自身、JAXAの信頼性を向上させるために一生懸命取り組んできました。
まずは、信頼性推進会議というのを設置し、いろいろな不具合への対応策を明確にしました。同時に、全JAXAに問題点を周知し、解決方法を全員一丸となって考えたり、その問題が影響を及ぼす他のプロジェクトはないかをチェックしました。このようなことを私たちは水平展開と呼んでいます。その一方で、民間の方を含むJAXA外部の方々で構成された、開発基本問題に係る外部諮問委員会を作り、より確実にミッションを達成するためにJAXAのやり方を全てチェックして、適切な勧告を出していただき、それを受けて改良してきました。これらによって、まず信頼性を回復するための体制づくりができました。
次に、個々のプロジェクトの審査については、JAXAの職員だけでなく、外部の有識者およびJAXAのOBの方々に評価委員になっていただいて、そこでも信頼性の面をチェックしていただきました。
特に不具合の水平展開について積極的に行いました。例えば、超高速インターネット衛星「きずな」で発見されたコンデンサの不具合問題を、すぐに月周回衛星「かぐや」に水平展開し、同様の不具合がないかを調査しました。その結果、同じような問題が「かぐや」でも見つかり、部品の交換を行いました。これらの作業によって打ち上げが1ヵ月延期されることになりましたが、水平展開を着実にやったことで、「かぐや」の不具合を未然に防ぐことができました。このような取り組みを行った結果、JAXAへの信頼性が高まってきたと思います。
ロケットでは、H-IIAロケット7号機から13号機まで7機連続して打ち上げに成功し、H-IIAロケットの打ち上げ成功率は92.3%まで上がりました。同時に、ロケットの組み立てから打ち上げまでの過程における不具合の件数を見ると、号数ごとに着実に減ってきていますので、こういった実績からも、信頼性向上の成果が出てきたと実感しています。
Q.昨年を振り返って、改善すべき点はどのようなところでしょうか?

昨年は、月探査機「ルナーA」というプロジェクトの中止を決定しましたが、その決断をするのが遅かったのではないかという意見がありました。「ルナーA」は、ペネトレータという観測装置で月の内部構造を調べるというプロジェクトでした。しかし、ペネトレータの開発が難航し、当初目標としていた2004年の打ち上げができなくなりました。その後、ペネトレータの開発にある程度の目途が立ったものの、先に製作されていた衛星の劣化が激しく、衛星をそのまま使うことができなくなりました。衛星の修復や再製作にかなりの予算が必要とされることから、議論を重ねた結果、中止を決めました。開発現場では衛星の劣化が分かっていたと思いますが、それが表面化したのは昨年でした。もう少し早くその問題が分かり、中止の決断をしていれば、無駄が起きなかったのではないかと外部からも批判されました。これを反省し、二度とこのような行き違いを起こさないために、プロジェクトの進捗管理を徹底するような体制を作りました。大きなプロジェクトはバランスよく進めていかなければなりません。今後は、どこかで問題が起きていれば、他の進行を一時止めて調整するなど、総合的に進捗状況を管理して、プロジェクトを確実に進めていきたいと思います。