
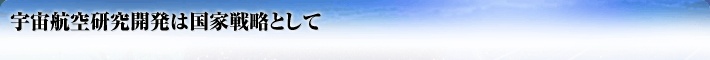
Q.今年は、どのような国際貢献を予定していますか?

超高速インターネット衛星「きずな」

温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」

今年もたくさんの国際協力の取り組みがあります。まずは、国際宇宙ステーションです。日本の実験棟「きぼう」が打ち上がりますが、米国・ロシア・欧州・カナダなど15カ国による国際共同プロジェクト中で、日本の責務を着実に果たしていきたいと思います。微小重力、宇宙放射線、広大な視野、高真空、豊富な太陽エネルギーなど、地上とは全く異なる宇宙という特殊な環境を利用して様々な実験を行い、その実験成果が21世紀の産業や私達の暮らしを豊かにすることを期待しています。
今年打ち上げ予定の超高速インターネット衛星「きずな」は、アジア諸国の大容量・超高速通信に大きく貢献できると思います。日本では既に全国的な高速インターネット網が整いつつありますが、アジア諸国ではまだまだ整備が遅れています。「きずな」を使って、アジア諸国での高速インターネット通信の普及を促進できればと思います。国内利用としては、災害時の通信確保に大きく期待されています。地震などが発生して通信網が壊滅しても被災地との通信を確保することができます。
また、温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」は地球規模の環境対策に貢献できると思います。地球温暖化や気候変動に対応するために、地上・海洋・宇宙から全地球規模の観測をするという、「全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)」を構築する国際プロジェクトが進行しています。「GOSAT」は、地球温暖化の要因である温室効果ガスを世界最高性能のセンサで観測します。これによって、地球規模でどの程度温室効果ガスを削減したかも分かり、GEOSSへの貢献が大いに期待されています。今年は、北海道の洞爺湖で主要国首脳会議(サミット)が開かれ環境問題がテーマとなるといわれていますが、「GOSAT」を活用して環境問題への世界的な対応にJAXAも貢献していきたいと考えています。
 Q.JAXAは2005年に宇宙教育センターを設立しましたが、今後どのように宇宙教育を進めていきたいですか?
Q.JAXAは2005年に宇宙教育センターを設立しましたが、今後どのように宇宙教育を進めていきたいですか?
JAXAの宇宙教育活動には5つの柱があります。まず、学校で宇宙教育をやっていただくことです。宇宙が教育の題材であれば、理科でも社会科の授業でもかまわないと思います。実際にそういった授業をやっていただくために、先生方と授業内容を共同開発し、教材や情報を提供するなどして、先生とうまく連携をとりながら進めます。2つ目は、「社会教育支援活動」と呼んでいる公募型の取り組みで、日本の各地域で宇宙を軸とする教育プログラムを実施することへの連携です。例えば、昨年は、全国35会場で2000名以上の小中学生を対象にしたプログラム「コズミックカレッジ」が展開されました。最初に地域の講師となる人たちを中心にプログラムを作り、その後で生徒を集めて、講師が各地で授業をやります。これはあくまで地域主体の活動で、それにJAXAがさまざまな支援をするわけです。3つ目は、「学生支援活動」といって、宇宙に関連した活動をしている大学生や高等専門学校の支援をします。4つ目は、国際協力で宇宙教育を行います。例えば、毎年開催されている国際宇宙会議(IAC)では、世界の学生を集めた学術セッションなどが行われていますので、そこに学生を派遣しています。宇宙分野の専門家や他国の学生と交流することで、宇宙に関心を持った人材を育成したいという目的です。5つ目は、JAXAが宇宙教育活動をしているということを世界に広め、たくさんの国が参加してくれるよう、情報の発信・交流をすることです。この5つを実現するために、宇宙教育センターを設立しました。
しかし、こういった教育活動はJAXAだけでは力不足です。他の機関とも連携を図って進めていくべきだと考えています。例えば、宇宙と海洋を結びつけて、理科教育を総合的にやってもらうようにしたいです。また、全国規模で宇宙及び科学に関する教育活動を行っている日本宇宙少年団などとの連携も行っていきたいと思います。その結果、若者の理科離れが抑制され、将来的に宇宙関連産業に関係してくれる人が増えたらいいと思っています。


Q.海外では、国家戦略として宇宙航空開発を推進しているところが多いですが、これについてどう思われますか?
アメリカ、ロシア、ヨーロッパ各国、中国、インドなど世界を見ると、ほとんどの国が国家戦略として宇宙開発を進めています。日本にも科学技術の基本的な政策を決定する総合科学技術会議があって、そこで宇宙政策が立てられていますが、より広範囲で包括的な日本の国全体としての宇宙戦略をぜひ作ってほしいと思います。JAXAは執行機関ですから、そういった戦略がきちんとあって、それをいかに実現していくかということになると思います。もちろん、JAXAだけではなく関係省庁が新しいニーズを発掘し、それを実現していけばいいわけですから、国家戦略というのはJAXAの問題だけでなく、もっと幅広く見ていくべきだと思います。
今年のJAXAにご期待ください。

超高速インターネット衛星「きずな」

温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」
今年もたくさんの国際協力の取り組みがあります。まずは、国際宇宙ステーションです。日本の実験棟「きぼう」が打ち上がりますが、米国・ロシア・欧州・カナダなど15カ国による国際共同プロジェクト中で、日本の責務を着実に果たしていきたいと思います。微小重力、宇宙放射線、広大な視野、高真空、豊富な太陽エネルギーなど、地上とは全く異なる宇宙という特殊な環境を利用して様々な実験を行い、その実験成果が21世紀の産業や私達の暮らしを豊かにすることを期待しています。
今年打ち上げ予定の超高速インターネット衛星「きずな」は、アジア諸国の大容量・超高速通信に大きく貢献できると思います。日本では既に全国的な高速インターネット網が整いつつありますが、アジア諸国ではまだまだ整備が遅れています。「きずな」を使って、アジア諸国での高速インターネット通信の普及を促進できればと思います。国内利用としては、災害時の通信確保に大きく期待されています。地震などが発生して通信網が壊滅しても被災地との通信を確保することができます。
また、温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT」は地球規模の環境対策に貢献できると思います。地球温暖化や気候変動に対応するために、地上・海洋・宇宙から全地球規模の観測をするという、「全球地球観測システム(GEOSS:Global Earth Observation System of Systems)」を構築する国際プロジェクトが進行しています。「GOSAT」は、地球温暖化の要因である温室効果ガスを世界最高性能のセンサで観測します。これによって、地球規模でどの程度温室効果ガスを削減したかも分かり、GEOSSへの貢献が大いに期待されています。今年は、北海道の洞爺湖で主要国首脳会議(サミット)が開かれ環境問題がテーマとなるといわれていますが、「GOSAT」を活用して環境問題への世界的な対応にJAXAも貢献していきたいと考えています。

JAXAの宇宙教育活動には5つの柱があります。まず、学校で宇宙教育をやっていただくことです。宇宙が教育の題材であれば、理科でも社会科の授業でもかまわないと思います。実際にそういった授業をやっていただくために、先生方と授業内容を共同開発し、教材や情報を提供するなどして、先生とうまく連携をとりながら進めます。2つ目は、「社会教育支援活動」と呼んでいる公募型の取り組みで、日本の各地域で宇宙を軸とする教育プログラムを実施することへの連携です。例えば、昨年は、全国35会場で2000名以上の小中学生を対象にしたプログラム「コズミックカレッジ」が展開されました。最初に地域の講師となる人たちを中心にプログラムを作り、その後で生徒を集めて、講師が各地で授業をやります。これはあくまで地域主体の活動で、それにJAXAがさまざまな支援をするわけです。3つ目は、「学生支援活動」といって、宇宙に関連した活動をしている大学生や高等専門学校の支援をします。4つ目は、国際協力で宇宙教育を行います。例えば、毎年開催されている国際宇宙会議(IAC)では、世界の学生を集めた学術セッションなどが行われていますので、そこに学生を派遣しています。宇宙分野の専門家や他国の学生と交流することで、宇宙に関心を持った人材を育成したいという目的です。5つ目は、JAXAが宇宙教育活動をしているということを世界に広め、たくさんの国が参加してくれるよう、情報の発信・交流をすることです。この5つを実現するために、宇宙教育センターを設立しました。
しかし、こういった教育活動はJAXAだけでは力不足です。他の機関とも連携を図って進めていくべきだと考えています。例えば、宇宙と海洋を結びつけて、理科教育を総合的にやってもらうようにしたいです。また、全国規模で宇宙及び科学に関する教育活動を行っている日本宇宙少年団などとの連携も行っていきたいと思います。その結果、若者の理科離れが抑制され、将来的に宇宙関連産業に関係してくれる人が増えたらいいと思っています。

Q.海外では、国家戦略として宇宙航空開発を推進しているところが多いですが、これについてどう思われますか?
アメリカ、ロシア、ヨーロッパ各国、中国、インドなど世界を見ると、ほとんどの国が国家戦略として宇宙開発を進めています。日本にも科学技術の基本的な政策を決定する総合科学技術会議があって、そこで宇宙政策が立てられていますが、より広範囲で包括的な日本の国全体としての宇宙戦略をぜひ作ってほしいと思います。JAXAは執行機関ですから、そういった戦略がきちんとあって、それをいかに実現していくかということになると思います。もちろん、JAXAだけではなく関係省庁が新しいニーズを発掘し、それを実現していけばいいわけですから、国家戦略というのはJAXAの問題だけでなく、もっと幅広く見ていくべきだと思います。
今年のJAXAにご期待ください。