
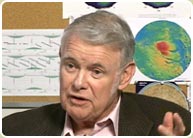 ファイルサイズ:5.6MB フォーマット:MPEG |
Q.NASAの「スピリット」は成功しましたが、JAXAの「のぞみ」は失敗に終わりました。なぜでしょうか? 一人のアメリカ人として「スピリット」が完璧に着陸したことをとても嬉しく思っています。ただ、今回の成功に確信があったわけではありません。その前の「マーズ・ポーラー・ランダー」の場合は万事うまくいっていると思っていたのに、結局失敗に終わっていましたからね。火星探査、宇宙探査というのは、それだけリスクを伴う難しいことなのです。ESA初の火星着陸船「ビーグル2」も、いまだに信号が何も返ってこないことから判断すると失敗に終わったと言えるでしょう。 ソ連とアメリカが先駆けとなり、他国がこれに続くかたちとなっている火星へのミッションですが、その約3分の2が途中か到着後に失敗に終わっています。ですから、国家的に宇宙探査を目指す場合は、成功よりも失敗の方が多く、ミッションが失敗しても誰か1人の失敗や組織の中の個人的な失敗ではないのだという事実を受け入れる用意ができていなくてはなりません。 その用意がなければ宇宙探査にチャレンジすることはやめたほうがいいでしょう。リスクを毛嫌いしているようでは、宇宙探査は不可能です。日本は決断を下す必要があります。個人的には日本が侍魂を維持し、宇宙探査に引き続きチャレンジして将来世界の一翼を担うことを期待しています。宇宙探査(宇宙開発)では、失敗を経験し、不愉快な思いをすることは避けて通ることができない道なのです。 |
||||||
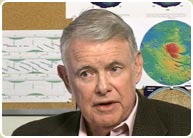 ファイルサイズ:7.7MB フォーマット:MPEG |
Q.コロンビア号の事故に関して、NASAの構造、文化、歴史に問題があったと言われていますが、そのあたりについてはいかがですか? また、JAXAの最近の事故についてはどうでしょうか? 失敗と成功の両面について、アメリカのプログラムから学ぶべき点は多々あると思います。コロンビア号に関しては、事故調査委員会が公に批判を行いました。同じような批判を日本ですれば衝撃的な結果をもたらすことになるのでしょうが、幸いにもアメリカでは関係者が肩身の狭い思いをしただけで済みました。その批判とは、NASA内部の態度、つまり幅広い視野から考えたり、他の可能性を模索したりすることを拒否したことが失敗の重要な原因であり、その態度が改められない限り将来も状況は変わらないというものでした。 私たちが「マーズ・ポーラー・ランダー」の失敗に関してJPLの調査を行った際にも同じ結論に達しました。国や状況を問わず組織の文化を変えるのは至難の業で、組織が成功を収めていて、そのやり方が確固たるものになってしまっている場合には特にそうです。JPLの場合にもそれが当てはまりました。私は以前JPLの所長を務めていましたから、そのことをよく理解しています。有人プログラムを行うヒューストンのジョンソン宇宙センターにもそれが当てはまります。JPLの場合には、「スピリット」が成功を収めたことから判断すると、改革がうまくいったのではないかと思います。 当然のことながらJPLにとって「マーズ・ポーラー・ランダー」の失敗後、JPLが宇宙計画から排除されてしまうことに対する危機感は非常に大きいものでした。「スピリット」が、散々注目を集め大金を投資したのにもかかわらず、失敗に終わっていれば「JPLよりも我々の方がまともな仕事ができますよ」と言う人たちが出てきたことでしょう。独占がない状態で宇宙プログラムを実際に実行しなくてはならないという危機感。ですから競争というのは良いことだと考えています。しかし有人飛行は、宇宙探査より独占的なものになっています。これは問題です。危機感が生まれるために必要な改革はいまだ実行されていません。改革が行われなければ、さらに失敗が繰り返され、比較的小規模な成功しか収めることはできないでしょう。
|
