
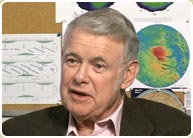 ファイルサイズ:5.6MB フォーマット:MPEG |
Q.H-IIAロケットや「のぞみ」など、最近のJAXAの失敗について、博士の意見もしくは、アドバイスをお聞かせください。 ケネディ大統領が引用したことで知られる「勝利に100の父あり、敗北は孤児なり」ということわざがあります。最初に申し上げたいのは、宇宙計画(開発)で失敗を経験したことのあるすべての者が、皆さんの苦痛を分かち合っているということです。その過程は非常に痛みを伴いますし、乗り越えるのは簡単なことではありません。するべきことをするより他に選択肢はないのです。つまり、何をなすべきなのかを考えることが重要です。 国を問わず一番重要なことは、失敗の原因を客観的に見つめることです。それには、個人を中傷するのではなく、事実を確実に突き止めることが肝心です。アメリカでそれを実行に移すのは、ある程度簡単でしょう。アメリカの文化というのは、日本よりも対立的だからです。アメリカ人は公の場で意見を戦わせますし、それが許されます。対立はマナーに反する行為だとは見なされません。日本の文化は、公での対立をできるだけ少なくしようとします。しかし、事実関係とその原因に関して厳しく議論を交わす必要があるのです。関与した人物や組織を中傷するのではなく、事実関係をきっちりと捉える方法をとらなければなりません。 |
||||||
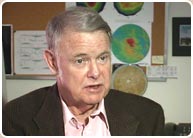 ファイルサイズ:14.5MB フォーマット:MPEG |
Q.博士も過去に火星探査計画で失敗を経験されていますが、どのように分析してきたのですか? 私は、「マーズ・ポーラー・ランダー」(MPL)とペネトレーターの「ディープ・スペース2」(DS2)、「マーズ・クライメイト・オービター」に携りました。 これらに従事していた当時、私にとって素晴らしい時期だったのですが、不幸にもまず「マーズ・クライメイト・オービター」が1999年10月に失敗に終わりました。計画を進める上で意思の疎通が不十分だったことが原因です。MPLは同じ年の12月3日に失敗。ちょっとしたソフトウェア、ハードウェアの問題が原因でした。点検や試験の際に検出されるべきだった問題が見落とされてしまったのです。「ディープ・スペース2」は1999年12月3日に火星に着陸するはずでした。DS2が失敗に終わった原因は定かではありません。火星そのものが原因だったのかもしれません。実際に氷に激突してその衝撃に耐える強度を持ち合わせていなかったのかもしれないですね。 しかし私の不幸はこれで終わりませんでした。当時のNASA長官から、失敗を詳細に分析する調査委員会のメンバーとして3カ月間の任務を依頼されたのです。というわけで、結果的にこういったミッションとその失敗について多くを学ぶことになりました。 私たちが失敗から学んだことをお話しします。 英語にはproximate cause(近因)という言葉があります。その近因の裏にもっと大きな原因があるわけです。MPLの近因に関して言えば、それはハードウェアとソフトウェア間の微妙な問題と、着陸システムの方法でした。その問題は事前にコロラド州ボルダーの契約企業の施設で検出されてしかるべきだったのですが、実際には見落とされてしまいました。 この2つの点検を両方担当する1人の責任者が、2つの現場に同時に居合わせるのは不可能です。つまり問題が発生する可能性があることを判断できる知識を有する人間が、もう一方の点検に立ち会えない結果になってしまいました。 なぜなのか。それは予算があまりにも少なすぎたために、JPLも契約企業も人員を切り詰めなければならなかったからです。なぜそんなことになったのかという疑問が湧いてくるのも当然でしょう。答えは、このような開発には予想外のことがたくさんあり、それをカバーしなければならないが、そのための予算がなかったからなのです。 しかし悲劇、つまり近因の裏にある本当の原因は、JPLのマネージメント側がNASAに「安全にミッションを遂行するには、当初の見積もりよりも少し高くなることになってしまいそうなのですが」と相談しなかったことにあるのです。私に言わせれば責任を負うべきなのはJPLで、すでにこのことは調査委員会の報告と同様に私からもJPLに伝達済みです。 同じような問題が「マーズ・クライメイト・オービター」の失敗の際にも蔓延しており、DS2に影響を及ぼした可能性も否定できません。このことから出た結論というのは、これまでの組織的な考え方を変えさせるということです。そして本当の敵、本当の問題というのは、「物事には議論の余地のないものが存在する」という態度にあったわけです。この場合はコストの上限を「絶対的に議論の余地がないもの」としてしまったことが間違いでした。 「スペースシャトルは安全な宇宙船として作られている」という考えの下でコロンビア号、チャレンジャー号は失敗してしまいました。実際はそうではないことを示すものが多々あったのですが、原則は「我々にはシャトルを飛ばすことができる、飛ばすべきだ」というものでした。誰かが立ち上がって「私には懸念があるんだ」と言っても、「申し訳ないがスケジュールを守らなくてはいけないんだ。計画は実行するよ」と言われてしまう。この態度こそ失敗が起こってしまった原因なのです。 これは日本にとっても重要なことです。H-IIAロケット、「のぞみ」が失敗に終わった本当の近因と原因を見つめなくてはいけません。その上で、なぜそれが改善されなかったのか? なぜ対処されなかったのかということを自らに問い詰める必要があります。そうすることは、関係者の頭の中にあったアイデアを見つめ直すことにもつながります。それが今後変えようとすること、到達しようとすることの中で最も重要なことです。
|
