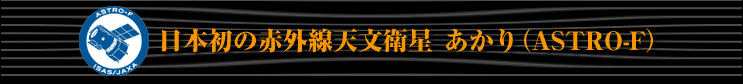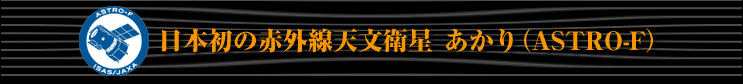|

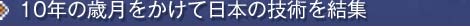
地球上では赤外線の大部分は、大気に吸収されてしまって観測できません。特に波長の長い赤外線で観測するには、大気の外に出るしか方法がないのです。日本でもIRASが打ち上げられる前から、赤外線望遠鏡を衛星に搭載することは考えられていました。小さな望遠鏡でもまずは宇宙に打ち上げて、何が難しいのか理解したかったのです。スペースシャトルに載せるというアイデアも検討されましたが、結局1995年に、SFUという実験衛星に直径15cmの赤外線望遠鏡(IRTS)を搭載しました。これによって液体ヘリウムを使って観測するという技術的な実証ができたのです。
これで技術的にはいけそうだと分かったので、1996年から日本初の赤外線天文衛星の設計に着手しました。天文学者は欲張りなので、とにかく大口径の望遠鏡を打ち上げたいという話になりましたが、当時、科学衛星をコストパフォーマンス良く打ち上げられるのはM-Vロケットだったので、M-Vのフェアリングに入る一番大きな望遠鏡を作ろうという話になりました。M-Vは、直径2.5mですから、まあ一声、1mクラスの望遠鏡を目指しました。また、M-Vの打ち上げ能力は、最大1800kgなので、ヨーロッパのISOのように2400kgもある大きな衛星は打ち上げられません。しかもその内2200リットル(約310 kg)は、望遠鏡を冷却するための液体ヘリウムです。ですから小さなスペースで大きな口径を確保するために、機械的な部分はできるだけ小さく、軽くするという日本のお家芸的なアプローチで設計していきました。その結果、これまでの赤外線宇宙望遠鏡としては、SSTの85cmには及ばなかったものの68.5cmと世界第2の大きさです(第3のISOとIRASは60cm)。冷凍機を使うことによって液体ヘリウムは、わずか170リットル(約24 kg)、ISOの10分の1以下にしました(SSTは360リットル=50.4kg)。観測期間は、ISOやSST(約2年半)と比べて、約1年半と短いですが、冷凍機のおかげで液体ヘリウムがなくなったあとでも一部の観測は可能です。また、情報通信研究機構(NICT)と共同で開発したセンサも世界のトップレベルです。そのほか名古屋大学、東京大学をはじめ、多くの大学、機関にも参加いただ き、日本の技術を結集させました。 |
 |


多目的実験衛星SFU(1995) |
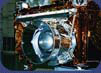
小型赤外線望遠鏡(IRTS) |

打ち上げを待つ「あかり」

内之浦宇宙空間観測所で打ち上げ前の最終確認をする筆者(手前)
|
 |