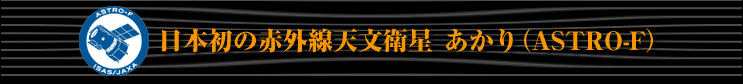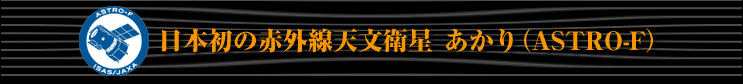|
 |
 |
 |
 |
 |
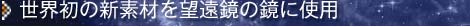
もう1つの画期的な技術は、炭化ケイ素(セラミックの一種)という新素材を使って望遠鏡の鏡を作ったことです。これは世界初の試みです。これによって直径約70cmの鏡がわずか11kgの軽さでできました。普通の鏡材であるガラスでは、200kgにもなってしまいます。軽くて歪みがない反射鏡ができたのは良かったのですが、この反射鏡を支える部分にも新しい材料を使ったことで問題が発生し、結果的には打ち上げが1年半延びてしまいました。しかし問題の解決に当たっては、宇宙科学研究本部の工学の先生を中心に、旧NASDAの技術研究本部(当時)や大学の方も入った対策チームを作ってもらい、多くのサンプルによる確認実験や解析をおこないました。これにより最終的には不安のないものに仕上げました。 |
 |

軽い新素材(炭化ケイ素)で作られた反射鏡 |
 |
 |

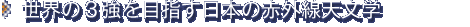
これまで世界で赤外線天文衛星を打ち上げ、成功させているのは、アメリカ(NASA)とヨーロッパ(ESA)だけです。日本はこれまでに、気球や観測ロケット、そして多目的実験衛星(SFU)に小型赤外線望遠鏡(IRTS)を搭載した実績もあり、赤外線天文学の分野では健闘していると思います。「あかり」が成功すれば、世界で3番目の赤外線天文衛星保有国になり、自信を持って世界の3強と言えるでしょう。そして「あかり」によって20年ぶりに更新される全天観測(宇宙の地図)のデータを、世界の天文学者の皆さんに活用していただき、宇宙の謎を解明したいと思っています。
|
 |

 |
 |
 |
村上 浩(むらかみ ひろし)
赤外・サブミリ波天文学研究系教授、研究系主幹。
名古屋大学大学院、助手を経て、1987年より旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)。大気球、観測ロケットを使った赤外線天文観測に従事。1995年、SFUに搭載された日本初の赤外線宇宙望遠鏡(IRTS)実験に参加。「あかり」には、構想から参加し、2005年4月、プロジェクトマネージャーとなる。
子供の頃から理科好きで、毎月プラネタリウムに通う。小学生の時に読んだ、故糸川英夫博士の話に影響を受ける。宇宙か生物学か迷った末に宇宙を選び、その後、銀河に興味を持ち、大学院では、当時、まだ日本で確立されていなかった赤外線天文分野の世界に飛び込む。理学系でありながら、モノ作りや実験が好き。その理論だけでない探究心が、衛星や観測装置作りにも活かされている。 |
|
 |
 |
 |