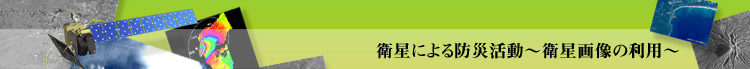

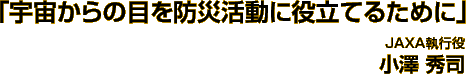

陸域観測技術衛星「だいち」
衛星が防災利用できるかどうかを考えた時にまず出てきたのは、衛星画像による被災地の状況把握です。車が行けないような場所や悪天候で飛行機やヘリコプターによる観測ができない場合でも、宇宙からは被災地を観測することができます。実際に、「だいち」の衛星画像は、日本だけでなく海外の災害を把握するためにも利用されています。しかし、防災活動は発災時の応急対応だけではありません。発災後の復旧・復興に関わる救援活動の情報提供や平常時から災害予防や事前準備を行い、いざ災害が起きた時に被害を最小限に押さえる、減災への取り組みも重要です。
そこで、JAXA では衛星利用推進センター内に防災利用システム室を作り、防災活動全般に関わる衛星利用の窓口を一元化しました。防災利用システム室では、被災地の緊急観測に対応するだけでなく、防災関係機関や有識者の方からのご要望やご意見をうかがい、各々のニーズにこたえられるよう検討を重ねています。JAXAでは、国民の安心安全を確保するために、災害が起きた時だけでなく、普段から衛星を利用し、防災に役立ててもらえるよう、さまざまな提案も行っています。
Q. 現在、国内では防災分野でどのような協力体制が築かれているのでしょうか?
元々「だいち」は、地図作成が主な目的の衛星でしたが、その地図を使って、さらに国民の生活を守るための防災活動に役立てないかと考えました。近年、宇宙は開発の場から実用の場へと大きく進化しています。しかし、私たちは宇宙開発研究機関ですから、防災の現場のことがよく分かりません。そこで、内閣府と文部科学省の共同で「防災のための地球観測衛星等の利用に関する検討会」が設置され、防災関連の各府省庁、機関、有識者などによる意見交換が行われました。どのような衛星写真の見せ方をすれば、現場で使ってもらえるのかを聞き、参考にさせていただきました。このように、防災活動の最前線にいる方たちからの要望を直接うかがうのは、初めての試みでした。この検討会は、2006年2月から同年8月まで、計6回にわたり開催され、衛星の防災利用に関するさまざまなニーズを出していただきました。現在は、その実現のために関係省庁や機関とワーキンググループを作り、実証実験を進めています。
実証実験はいくつかの分野に分かれます。まずは、衛星地形図の作成及び防災利用です。例えば、ハザードマップの作成に「だいち」の衛星画像を利用できないか検討しています。ハザードマップとは、災害の被害を予測して、その危険性を地図上に表したものです。危険な場所を事前にモニタしておけば、実際に災害が起きた時にどこに避難をすれば安全か判断できます。また、「だいち」の観測画像と、国土地理院が発行する数値地図の情報とを重ね合わせることによって衛星地形図を作成できます。これを、防災訓練や、発災時の救助隊の派遣計画などの初動対応に利用できないかと、警察庁や消防庁、防衛省の方からのニーズをうかがい、東京南部の25,000分の1の衛星地形図のサンプルを作成しました。この地図には緊急輸送路が色分けで示され、ヘリポートなどの情報も盛り込まれています。また、平常時に衛星画像を準備しておくと、発災直後の画像と比較することによって、どこの建物が倒壊しているとか、どこで火事が起きているかなどの災害状況を迅速に把握することもできます。さらに、「だいち」のセンサは立体視ができますので、将来的には全国規模の三次元画像を作り、関係省庁が共通で使える衛星地図として、防災対策に利用していただきたいと考えています。
その他にも、火山噴火、地殻・地盤変動、海上・沿岸災害、土砂災害、風水害といった災害の予兆や被害把握をするために、定常的な観測を含めた実証実験が行われています。衛星写真の特徴は、何といっても、一度の撮影で広い範囲が撮れ、新しい情報が得られることです。しかし、衛星写真をそのまま提供しただけでは、防災対策になかなか利用できません。例えば、火山噴火の予兆を調べる場合、火山活動が活発になる前に撮った写真と比較し、その少しの差を解析することによって、山が隆起している情報を得ることができます。そのために、火山噴火予知に関する実証実験は、気象庁、国土地理院や防災科学技術研究所など火山噴火予知連絡会に参加されている多くの研究機関と共同で進めています。
普段の防災活動にいかに衛星を使ってもらうかが重要であり、そのためには、どういった情報を提供できるのかを我々が提案していく必要があります。実際に情報を使うユーザーの方たちと積極的な意見交換をし、相互協力することによって、衛星を有効的に活用していきたいと思います。
Q. 衛星を防災活動に使うための今後の課題は何ですか?
先程申し上げた検討会では、次期地球観測衛星の仕様についての意見交換も行われました。皆さんの要望で高かったのは、分解能と観測幅、そして、迅速性でした。「だいち」のパンクロマチック立体視センサ(PRISM)は2.5mの分解能ですが、より詳細な観測データを得るためには、1mの高い分解能が必要です。また、過去の災害被害規模のデータから分析しますと、地震では40〜70km、風水災害では30〜50km四方程度に被害が出ています。それらの被害範囲を1回の撮影でカバーするためには、観測幅を約50km程度にする必要があります。「だいち」は最大2.5mの分解能で最大70km幅の観測が可能ですが、皆さんのご要望に沿うためには1mの分解能で50km以上の観測幅を持つセンサの開発を目指す必要があります。さらに、「だいち」は約2日に1回の頻度で同一地点を撮影することができますが、災害発生時に被害状況を迅速に把握するために遅くても発災から3時間程度以内には、衛星からの情報が欲しいという要望もありました。3時間ごとに同一地点を観測(撮影)するためには、衛星が4機必要になります。
将来的には、いつでも必要な場所が観測できる静止軌道から、リアルタイムでの災害監視を実現したいと思っています。そのための技術開発も推進していきたいと思います。
実証実験はいくつかの分野に分かれます。まずは、衛星地形図の作成及び防災利用です。例えば、ハザードマップの作成に「だいち」の衛星画像を利用できないか検討しています。ハザードマップとは、災害の被害を予測して、その危険性を地図上に表したものです。危険な場所を事前にモニタしておけば、実際に災害が起きた時にどこに避難をすれば安全か判断できます。また、「だいち」の観測画像と、国土地理院が発行する数値地図の情報とを重ね合わせることによって衛星地形図を作成できます。これを、防災訓練や、発災時の救助隊の派遣計画などの初動対応に利用できないかと、警察庁や消防庁、防衛省の方からのニーズをうかがい、東京南部の25,000分の1の衛星地形図のサンプルを作成しました。この地図には緊急輸送路が色分けで示され、ヘリポートなどの情報も盛り込まれています。また、平常時に衛星画像を準備しておくと、発災直後の画像と比較することによって、どこの建物が倒壊しているとか、どこで火事が起きているかなどの災害状況を迅速に把握することもできます。さらに、「だいち」のセンサは立体視ができますので、将来的には全国規模の三次元画像を作り、関係省庁が共通で使える衛星地図として、防災対策に利用していただきたいと考えています。
その他にも、火山噴火、地殻・地盤変動、海上・沿岸災害、土砂災害、風水害といった災害の予兆や被害把握をするために、定常的な観測を含めた実証実験が行われています。衛星写真の特徴は、何といっても、一度の撮影で広い範囲が撮れ、新しい情報が得られることです。しかし、衛星写真をそのまま提供しただけでは、防災対策になかなか利用できません。例えば、火山噴火の予兆を調べる場合、火山活動が活発になる前に撮った写真と比較し、その少しの差を解析することによって、山が隆起している情報を得ることができます。そのために、火山噴火予知に関する実証実験は、気象庁、国土地理院や防災科学技術研究所など火山噴火予知連絡会に参加されている多くの研究機関と共同で進めています。
普段の防災活動にいかに衛星を使ってもらうかが重要であり、そのためには、どういった情報を提供できるのかを我々が提案していく必要があります。実際に情報を使うユーザーの方たちと積極的な意見交換をし、相互協力することによって、衛星を有効的に活用していきたいと思います。
先程申し上げた検討会では、次期地球観測衛星の仕様についての意見交換も行われました。皆さんの要望で高かったのは、分解能と観測幅、そして、迅速性でした。「だいち」のパンクロマチック立体視センサ(PRISM)は2.5mの分解能ですが、より詳細な観測データを得るためには、1mの高い分解能が必要です。また、過去の災害被害規模のデータから分析しますと、地震では40〜70km、風水災害では30〜50km四方程度に被害が出ています。それらの被害範囲を1回の撮影でカバーするためには、観測幅を約50km程度にする必要があります。「だいち」は最大2.5mの分解能で最大70km幅の観測が可能ですが、皆さんのご要望に沿うためには1mの分解能で50km以上の観測幅を持つセンサの開発を目指す必要があります。さらに、「だいち」は約2日に1回の頻度で同一地点を撮影することができますが、災害発生時に被害状況を迅速に把握するために遅くても発災から3時間程度以内には、衛星からの情報が欲しいという要望もありました。3時間ごとに同一地点を観測(撮影)するためには、衛星が4機必要になります。
将来的には、いつでも必要な場所が観測できる静止軌道から、リアルタイムでの災害監視を実現したいと思っています。そのための技術開発も推進していきたいと思います。


