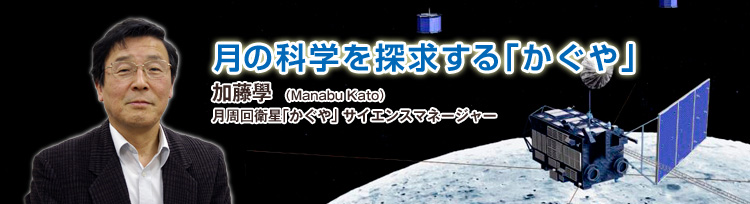
Q. 月周回衛星「かぐや」を打ち上げた理由は何でしょうか?

アポロ15号。アポロ計画では12人が月に降り立った(提供:NASA)
私は、月や惑星の起源あるいは進化に従来から興味がありました。学生の頃に見たアポロ11号の月面着陸の映像は鮮明に覚えており、当時は探査の詳細が分からなくても、「月で何をやっているのだろう」とテレビ画面に釘付けになりました。やはり、月を科学の対象として認識づけたのはアポロ計画だと思います。アポロ計画では12人が月へ降り立って科学探査を行いましたが、人間が月へ行って地球に帰ってくるたびにいろいろなことが分かりました。アポロは、「こうやって惑星の科学探査をするんだ」ということをすべて見せてくれたと思います。また、惑星をもっと詳しく調べるためにはどうすればよいかということも教えてくれました。
そのアポロ計画から40年が経ち、当時と比べて観測機器の精度が飛躍的に向上した今、アポロから教わったことを活かして、自分たちの手で月を調べたいと思ったのです。最先端の技術を使って月の全球を詳しく調べると、きっと新しい何かが見つかる、見つけたいという思いがありました。このようなことから、私たちは「かぐや」を打ち上げたのです。
そのアポロ計画から40年が経ち、当時と比べて観測機器の精度が飛躍的に向上した今、アポロから教わったことを活かして、自分たちの手で月を調べたいと思ったのです。最先端の技術を使って月の全球を詳しく調べると、きっと新しい何かが見つかる、見つけたいという思いがありました。このようなことから、私たちは「かぐや」を打ち上げたのです。
Q. 月を知ることによって何が分かるのでしょうか?

月と地球(提供:NASA)
月の起源は、約46億年前に地球が誕生した直後に、火星くらいの大きさの巨大な天体が地球に斜めに衝突して、そのときに飛び散ったものが集まって月になったという「ジャイアント・インパクト説」が今のところ有力です。そういう意味で、月は地球と対です。ですから、地球のことを知るためには、月のこと知ることが重要だと思います。地球だけでなく、太陽系全体やほかの星がどう生まれたかについても、「月を知らずして、ほかの天体が分かるはずがない」という思いがあります。月を詳細に調べて、その結果ジャイアント・インパクトで生まれたことに確信が持てたなら、その次は、火星はどうなんだろう?金星は?となります。あるいは、地球はどうなんだろう?と振り返って思うわけです。月探査は、私たちの太陽系や地球を知る大きな手がかりになるのです。
また、地球の古い物質を、今でも見ることができるのが月です。地球には大気や水があるのみならず、現在までも活発な火山活動が続いているため、表面の物質は、風、雨や火山などの自然現象によって岩石が浸食されるなど変化してしまいます。古い年代のものは、もはや表側に残っていないのです。それに比べ、大気も水もない月では気象現象は起こらないし、火山活動も終焉してしまっており、古い物質がいまだに表面に残っています。ですから、月を調べれば、40億年前の地球がどういう状況にあったかが分かるのです。
また、地球の古い物質を、今でも見ることができるのが月です。地球には大気や水があるのみならず、現在までも活発な火山活動が続いているため、表面の物質は、風、雨や火山などの自然現象によって岩石が浸食されるなど変化してしまいます。古い年代のものは、もはや表側に残っていないのです。それに比べ、大気も水もない月では気象現象は起こらないし、火山活動も終焉してしまっており、古い物質がいまだに表面に残っています。ですから、月を調べれば、40億年前の地球がどういう状況にあったかが分かるのです。

アポロ15号の着陸地点付近(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)
Q. 先生が特に興味を持っている月の研究は何でしょうか?
表面だけでなく内部も含めて、月がどういう物質でできていて、どんな構造になっているかを知りたいです。私たちが住んでいる地球ですら内部構造がすべて分かったわけではないので、それはとても難しいことだとは思いますが、月の物質構成を知ることがまず基本になります。そして、それを基に、物質がどのようにできたかという進化の過程を探ることができるのです。そういう意味で「かぐや」はまだ最初の段階で、月の周りから、表面の物質を見ています。
表面だけでなく内部も含めて、月がどういう物質でできていて、どんな構造になっているかを知りたいです。私たちが住んでいる地球ですら内部構造がすべて分かったわけではないので、それはとても難しいことだとは思いますが、月の物質構成を知ることがまず基本になります。そして、それを基に、物質がどのようにできたかという進化の過程を探ることができるのです。そういう意味で「かぐや」はまだ最初の段階で、月の周りから、表面の物質を見ています。
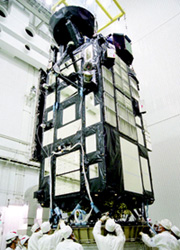
月周回衛星かぐや
「かぐや」は主衛星と2基の子衛星で構成されています。14種類の観測機器が搭載されており、まさに日本の最先端技術力を結集して作った衛星です。搭載している観測機器は、月の表面がどんな岩石でできていて、どんな鉱物組成を持っているかを調べるもの。地面がどのように起伏しているかを観測する機器。また、地下数kmに至る地層構造を調べるものもあります。そして、月の重力を測る機器。月の裏側の重力場を詳細に調べるのは「かぐや」が初めてです。さらに、月周辺の磁気やプラズマなど、月の環境を調べるもの。月から地球を観測したり、月の裏側からほかの天体を調べる機器もあります。そして、高画質のハイビジョンカメラです。「かぐや」が撮った地球や月の高精細画像は世界中に配信され、大変な話題となりました。この映像は、若い人たちに、科学の面白さを知ってもらうという意味でも、とても有効だったと思います。
※観測機器の一覧はこちら
Q. 「かぐや」のデータは、アメリカのアポロ計画、「クレメンタイン」、「ルナ・プロスペクター」など、過去の月探査のデータと比べて違いはありますか?

クレメンタインが観測した月の南極付近(提供:NASA)
1960年代から70年代前半にかけて行われたアポロ計画では、月着陸船の周りの限られた場所だけを探査しましたので、そういう点で、全球観測の「かぐや」とは違います。ただ、人類が初めて月面に着陸して直接観測をし、岩石や砂の試料を地球に持ち帰ったことは、月を理解するうえでとても役に立ちました。次に、1994年に打ち上げられた「クレメンタイン」は、月のほぼ全球を観測し、月面の物質や地形を調べました。月の全球観測の面白さを教えてくれたのは「クレメンタイン」です。そして、月の極地域のクレーターの底に水の氷が存在する可能性を見つけたのは大きな発見でした。その結果を受けて、1998年に打ち上げられたのが「ルナ・プロスペクター」です。この衛星は、極域の観測のほか、元素組成分布や表側の重力場の観測などを行いました。残念ながら、極域の水の存在については明らかにすることはできませんでしたが、月に関する貴重なデータを取得しました。
このようにそれぞれ成果をあげていますので、「かぐや」と一概に比べることはできませんが、明らかに違うと言えるのは、観測機器の性能です。「かぐや」の観測精度は、これまでのミッションと比べてはるかに優れており、一桁以上よくなったと思います。
このようにそれぞれ成果をあげていますので、「かぐや」と一概に比べることはできませんが、明らかに違うと言えるのは、観測機器の性能です。「かぐや」の観測精度は、これまでのミッションと比べてはるかに優れており、一桁以上よくなったと思います。