Q. 「かぐや」に対する国際的な評価はいかがでしょうか?

月面と地球(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)
「かぐや」のように、14もの観測機器を搭載し、多くの高精細データを取っている月探査機はほかにはありませんから、世界中の科学者たちが注目しています。そのため、海外の学会から招待され、講演をする機会が増えました。例えば、毎年3月にアメリカで「月惑星科学会議」が行われますが、「かぐや」の打ち上げ前はそれほど興味を示されなかったのに、昨年からは、「かぐや」の発表のために時間を持たせていただき、そのセッションにたくさんの人が集まるようになっています。特に、ハイビジョンカメラで撮影をした高画質の映像に興味を持つ方が多く、みなさん画面を食い入るように見ていますね。その様子を見ていると、みんな心底もっと月のことを知りたいんだなと思います。
「かぐや」のデータを世界中の研究者に向けて公開するのは、今年の11月からです。研究者の方々が使いやすいようにデータを提供し、みなさんの期待に応えるようにしたいと思います。
「かぐや」のデータを世界中の研究者に向けて公開するのは、今年の11月からです。研究者の方々が使いやすいようにデータを提供し、みなさんの期待に応えるようにしたいと思います。
Q. 「かぐや」の現状と今後の予定を教えてください。

グリマルディ付近(かぐやのハイビジョンカメラ撮影)
「かぐや」は、2007年末から約10ヵ月にわたって月の全球観測を行い、当初予定していた観測項目の目標を達成しました。2008年11月からは、一部データが取れなかったガンマ線分光計の観測を主に行っています。そして2月1日には、これまでの100kmから50kmまで高度を下げた運用を開始しました。高度を50kmまで下ろすと、これまでの8倍の感度で観測をすることができますので、さらに新しい発見があるかもしれません。高度50kmで数カ月観測をした後、燃料がまだ残っていたら、南極の上空で更に高度を低くして、磁場などを観測することも考えています。衛星の高度を下げるのに多くの燃料を使いますので、どれくらい燃料が残るかは今の段階ではまだ分かりません。そして、夏前には「かぐや」の燃料はなくなり、月面に落下します。月面に落下する最後まで観測が可能です。現在、これについて議論していますが、月面に衝突する直前まである場所の地形を観測するなどいくつかの案が出ています。いずれにしても地球から見える表側のどこか決めた場所に落ちるよう衛星の軌道を調整する予定です。そうすれば月面に衝突するときの発光を地球から見れるので、みなさんにも「かぐや」の最後を見届けてほしいと思っています。
また、2基ある子衛星のうち、リレー衛星「おきな」は一足早く、2009年2月12日に月の裏側に落下しました。もう1つの子衛星、VRAD衛星「おうな」は落下までには数年かかる予定です。
また、2基ある子衛星のうち、リレー衛星「おきな」は一足早く、2009年2月12日に月の裏側に落下しました。もう1つの子衛星、VRAD衛星「おうな」は落下までには数年かかる予定です。
Q. 今後期待される「かぐや」の成果は何でしょうか?
低高度での磁場の観測や、ガンマ線のデータから、これまでとは質的に違うものが出てくるかもしれないと期待しています。「かぐや」にかかわる研究者たちは、自分たちで衛星の運用をしながら、その一方で、データの解析を行っています。これまで確かに全球観測をしましたが、解析が済んだのはまだ一部で、最初の基礎的なデータが分かっただけです。その第一報として学会誌などに論文を発表したところですが、科学としては、これから面白い成果がたくさん出てくると思います。
Q. 「かぐや」のほかに、国内外ではどのような月探査ミッションが進行していますか?
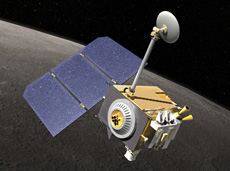
アメリカの月観測衛星ルナ・リコネイサンス・オービター
「かぐや」の約1ヵ月後の2007年10月に、中国が月周回衛星「嫦娥(じょうが)1号」を打ち上げました。「嫦娥1号」は中国初の月探査ミッションで、高度約200kmから月面の鉱物や元素分布などの観測を行いました。設計寿命の1年が過ぎ、高度を下げての運用を行っていましたが、燃料がなくなったため、3月1日にミッションを終えて月面に衝突しました。
また、2008年10月にはインドの月探査衛星「チャンドラヤーン1」が打ち上げられ、本格的な観測が始まりました。月の鉱物や地形などを調べる11種類の観測機器が搭載されており、その中には、NASAやESA(欧州宇宙機関)が開発した機器もあります。昨年の11月には月面衝突プローブを月面の南極に近い地域に衝突させたと聞いています。プローブの目的は至近距離で月面を観測することですが、どのような成果が出てくるかとても楽しみです。
そして今年の5月には、アメリカの月観測衛星「ルナ・リコネイサンス・オービター」が打ち上げられる予定です。この衛星は、高度50kmの低軌道からの観測を行う予定で、詳細な地形図の作成、月資源や水の存在の観測、将来の有人月探査や月面基地建設に向けた調査を行います。また、この衛星と一緒に「エルクロス」という探査機も打ち上げられます。「エルクロス」は、月の極にあるクレーターに探査機の先端部分を打ち込み、その衝突で飛び散った物質などを観測します。
日本でも「かぐや」の次の月探査ミッションが検討されていますが、2010年には中国の「嫦娥2号」、2010年から2012年の間にはインドの「チャンドラヤーン2」の打ち上げが予定されるなど、本格的な月探査を初めて成功させたアジアの国は、それに続く将来計画をそれぞれ立てています。ある意味では、日本、中国、インドというアジアの国が、月探査の新しい流れを作ったと思います。
また、2008年10月にはインドの月探査衛星「チャンドラヤーン1」が打ち上げられ、本格的な観測が始まりました。月の鉱物や地形などを調べる11種類の観測機器が搭載されており、その中には、NASAやESA(欧州宇宙機関)が開発した機器もあります。昨年の11月には月面衝突プローブを月面の南極に近い地域に衝突させたと聞いています。プローブの目的は至近距離で月面を観測することですが、どのような成果が出てくるかとても楽しみです。
そして今年の5月には、アメリカの月観測衛星「ルナ・リコネイサンス・オービター」が打ち上げられる予定です。この衛星は、高度50kmの低軌道からの観測を行う予定で、詳細な地形図の作成、月資源や水の存在の観測、将来の有人月探査や月面基地建設に向けた調査を行います。また、この衛星と一緒に「エルクロス」という探査機も打ち上げられます。「エルクロス」は、月の極にあるクレーターに探査機の先端部分を打ち込み、その衝突で飛び散った物質などを観測します。
日本でも「かぐや」の次の月探査ミッションが検討されていますが、2010年には中国の「嫦娥2号」、2010年から2012年の間にはインドの「チャンドラヤーン2」の打ち上げが予定されるなど、本格的な月探査を初めて成功させたアジアの国は、それに続く将来計画をそれぞれ立てています。ある意味では、日本、中国、インドというアジアの国が、月探査の新しい流れを作ったと思います。
Q. 「かぐや」の成果は、将来の月探査ミッションにどう活かされていくと思いますか?
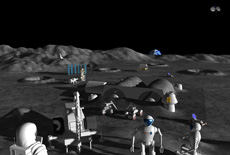
月面基地(想像図)
「かぐや」は月の基礎的なデータを与えてくれます。そのデータを基に、今度は、探査機を月面に着陸させて観測をすることになると思います。月に降りて直接観測をすれば、新しい発見がきっとあるはずです。そのためにも、「かぐや」のデータをきちんと解析して、月のどの場所に着陸をするか検討する必要があります。また、その場所に着陸するための技術を確立しなければなりません。月へ降りるためには、「かぐや」の重力に関する情報が役に立つはずです。
また、月を探査することは、その先にある、月面基地の建設や火星の有人探査へとつながります。月面基地で人間が生活をするためには、月で活用できる資源があるのか?水があるのか?ということが重要です。そういったことも、今後の探査で明らかにしていきたいと思います。
また、月を探査することは、その先にある、月面基地の建設や火星の有人探査へとつながります。月面基地で人間が生活をするためには、月で活用できる資源があるのか?水があるのか?ということが重要です。そういったことも、今後の探査で明らかにしていきたいと思います。
Q. 今後の月探査へどのようなことを期待しますか?
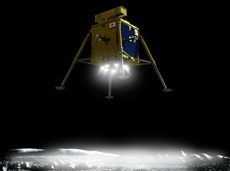
JAXAが検討するかぐやの後継機セレーネ2
科学の世界で、より深く月を知るということです。月の全球がだいたい分かってくると、もっと詳しく調べたいという場所が出てきます。地球を研究する「地球科学」が、近年では太陽系に関する研究を含めた地球惑星科学へと広がっていったのと同じように、月を研究する「月の科学」も、月と地球、月と太陽系の関係というように、研究の対象が広がっていくことを期待します。
また世界から、「こういうところは日本が得意だから任せよう」と思われるところをつくっていきたいです。その信用を得るためにも、「かぐや」のミッションを成功させることが重要です。「かぐや」は、月の全体がどういう物質でできていて、どんな構造をしているのか明らかにすることが、ゴールです。まずは「かぐや」の全球観測でその目標達成をしてから、次に何を期待するのかを見極めていきたいと思います。
また世界から、「こういうところは日本が得意だから任せよう」と思われるところをつくっていきたいです。その信用を得るためにも、「かぐや」のミッションを成功させることが重要です。「かぐや」は、月の全体がどういう物質でできていて、どんな構造をしているのか明らかにすることが、ゴールです。まずは「かぐや」の全球観測でその目標達成をしてから、次に何を期待するのかを見極めていきたいと思います。
加藤學(かとうまなぶ)
JAXA宇宙科学研究本部 固体惑星科学研究系。教授。
1976年、名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了。名古屋大学理学部助手を経て、1997年より旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)にて、惑星の元素分布を観測する蛍光X線分光器の開発などに従事。2003年に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ」や2007年打ち上げの月周回衛星「かぐや」に搭載した蛍光X線分光器を担当。月周回衛星「かぐや」のサイエンスマネージャーにも従事し、現在に至る。専門は、惑星科学。
JAXA宇宙科学研究本部 固体惑星科学研究系。教授。
1976年、名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了。名古屋大学理学部助手を経て、1997年より旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)にて、惑星の元素分布を観測する蛍光X線分光器の開発などに従事。2003年に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ」や2007年打ち上げの月周回衛星「かぐや」に搭載した蛍光X線分光器を担当。月周回衛星「かぐや」のサイエンスマネージャーにも従事し、現在に至る。専門は、惑星科学。