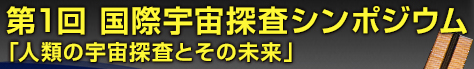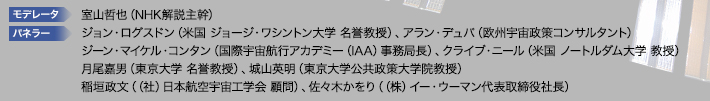
室山:現在世界では、経済やエネルギー、環境問題など数多くの問題を抱えています。その中で、有人宇宙開発を行う意義は何なのか。人類が初めて宇宙飛行をしてから50年が経ち、この50年の成果と課題は何か。これから、どう有人宇宙開発を進めるべきか。ということを議論したいと思います。まずは、この50年間の成果についてお聞きします。
ログスドン:過去半世紀の有人探査において最も印象的だったのは、1969年に、人類が月面に着陸したことです。ただこれは、人類の文明を、母なる地球以外の場所にもたらした鋭意の第一歩にすぎません。それだけで満足してはいけないと思います。
稲垣:私もアポロの月面着陸はよく覚えていて、それを見た時、人間の能力に感心し、希望と自信を持ちました。この巨大プロジェクトを遂行するための管理システムは、その後の宇宙の産業利用のベースラインとなっていますので、アポロ計画がもたらした宇宙の産業化への貢献は大きかったと思います。
城山:日本は1980年代に国際宇宙ステーション(ISS)計画への参加を決め、その後、いろいろ試行錯誤しながらも継続しています。国際共同の大きなプロジェクトに最初から関与し、これまで蓄積してきたこと。そのコミュニティの中で、それなりの存在感と信頼性を持つようになったことは、ある種の資産だと思います。
月尾:宇宙開発がもたらしたことは幾つもありますが、実は、インターネットもその1つです。インターネットは、ソビエトが1957年に史上初の人工衛星「スプートニク」を打ち上げたために起こった技術だと言われています。アメリカは、人工衛星から爆弾を落とされるかもしれないという危機感から、万が一の場合にも通信網を確保するため、1960年代からインターネットの研究を始め、今のインターネット時代がつくられました。
ニール:私は先ほど携帯電話を使ってアメリカの家族に電話をしましたが、これは衛星を通じて会話をしたわけです。このような衛星携帯電話は、目に見える形の宇宙開発の成果です。携帯電話の小型化の技術や、コンピュータの飛躍的な発展も、宇宙開発の成果で、一般の人々の生活にも大きな影響を与えています。
デュパ:アポロの宇宙飛行士が撮った写真は、地球が小さい青い星であることを示し、人々にインスピレーションを与えました。宇宙というのは、非常に多くの人の心を引きつけます。宇宙技術の進歩が社会にも重要な役割を担うものであると考えると、特に若い世代の人が宇宙からインスピレーションを受けて、科学技術に興味を持つことが大切です。そういう面でも有人宇宙開発の成果はあったと思います。
コンタン:過去50年間の最大の成果はVoyagerという人間が作った機械が太陽系の外に出たことだと思いますが、これは一般の人にほとんど知られていません。一般の視点での最大の成果は月面着陸だと思います。人類が月に到達できることを示し、更なる探査の可能性が広がりました。
室山:佐々木さんは、最も一般人に近い視点でこのシンポジウムに参加していると思いますが、なぜ人間が宇宙へ行かなければならないと考えますか?
佐々木:月に人が立ったことは、私にとっても大きなインパクトでした。神秘的で未知なる遠い存在の宇宙が、身近なものになったことが大きな変化だと感じたからです。人が実際に月へ行ったことで、もしかしたら自分も宇宙へ行けることができるかもしれないというような気持ちになりました。「なぜ人が宇宙へ行くのか?」という問いは、「人はなぜ生きているのか?」という深い話と関係するような気がします。心を持った人間が宇宙に行って、どんな感情を抱くかということに重要性があり、単なるデータ収集だけであれば人間でなくてもできるだろうと考えます。
室山:ISSは少なくとも2020年まで運用を継続することになっていますが、その費用対効果が問われています。ISSの評価も含めてご意見をお聞かせください。
ログスドン:ISSは2011年7月に完成したばかりで、まだ1年半しか経っていませんので、投資費用に対して、科学的・経済的なメリットがどれだけあったかを判断する時期ではないと思います。今後5年程の結果をもって、ようやく答えが得られるのだと思います。ただそのメリットというのは、目に見えるものだけではありません。例えば、人間の精神面への影響など、決して経済的な指標では表すことができない効果もありますので、広い意味での価値を見出さなければなりません。
ニール:そうですね。ISSは完成からまだ1年半しか経っていませんので、どれだけの費用対効果があるのかはまだ分かりません。とはいえ、ISSの今後のロードマップを、国際的なパートナーで作っていく必要があります。何がうまくいき何がうまくいっていないのか、人間でなければできないことは何なのかを、国際的な観点も踏まえて検討していかなければなりません。このような国際協力・国際協調の体制はISSによって築かれたものであり、ISSの成果だと思います。
稲垣:日本の場合、ISSの効果は、「きぼう」日本実験棟での実験成果によって算出されますが、これはもう少し待たないと出てこないと思います。ただ、「きぼう」を作る過程において、日本の宇宙産業は、有人宇宙活動の技術を学び、国際チームでプロジェクトを進める中で、その技術の信頼性をさらに高めることができました。これは、数字ではなかなか表せない成果ですが、日本の技術力向上に貢献していると思います。
室山:現在のISSの費用対効果については厳しい意見も多いですが、ISSの成果を判断するにはまだ早いということで、これからの活動に期待したいと思います。では、ISSを今後どう運用していくべきだと思われますか?
ログスドン:現在のアメリカの景気を考えると、宇宙予算の大幅な増額は見込めないと思います。従って、アメリカは現在のプログラムと同等レベルの形で有人宇宙開発を継続していくことになるでしょう。ISSについては、商業利用も視野に入れて、科学的・経済的に価値あるものかどうかを検証し、それ次第では、民間主導で運用することになるかもしれません。ISSは、技術的には2020年以降の運用も可能ですが、毎年20億〜30億ドルもかかる運用費用を正当化できるだけの成果を出せるかどうかが鍵となります。
デュパ:欧州でも宇宙予算の増額は期待できませんが、横ばいで推移するだろうと思います。たとえ予算が横ばいでも、技術の進歩と、適切な計画の選択をすれば、有人宇宙開発は前進していけると思っています。ISSについては、宇宙実験室として、投資に対する見返りを生み出すことができるのか。今すぐに結論は出せないものの、それを判断する ISSの転換期が必ずやってきます。ISSを実験室として使う以外に、月や火星に向かうときの中継地点とするという捉え方もありますが、それらも加味して総合的に、国際パートナー間で議論してほしいと思います。
稲垣:これまで長い年月をかけて作ってきたISSを利用しない手はありません。例えば、今問題になっている宇宙デブリを除去するための基地にすることも考えられるでしょう。ただ、それを効率よく行うためには、ISSを改修する必要があると思いますので、その時にやはり費用の問題が浮上します。今後のISSの運用については、いろいろなアイディアを募って、費用対効果を見極めて検討していくのが良いと思います。
室山:中国は独自に宇宙ステーションを作ると言っていますが、中国との関係はどうなると思われますか?
コンタン:我々の国際宇宙航行アカデミーは中国に事務所を持ち、中国との関係を拡げています。今、政治的な環境はあまり有利な状況ではありませんが、宇宙コミュニティとしては、協力の拡大に前向きです。中国は独自の宇宙ステーションを開発したいと言っていますが、 ISSとの類似性や補完性はあると思いますので、お互いに話し合って、経験を共有し合うこともできると思います。

室山哲也(NHK解説主幹)
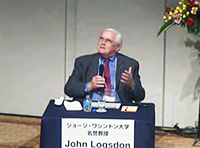
ジョン・ログスドン(米国 ジョージ・ワシントン大学 名誉教授)

稲垣政文((社)日本航空宇宙工業会 顧問)

城山英明(東京大学公共政策大学院教授)
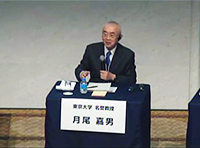
月尾嘉男(東京大学 名誉教授)

クライブ・ニール(米国 ノートルダム大学 教授)
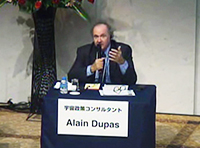
アラン・デュパ(欧州宇宙政策コンサルタント)

ジーン・マイケル・コンタン(国際宇宙航行アカデミー(IAA)事務局長)

佐々木かをり((株)イー・ウーマン代表取締役社長)