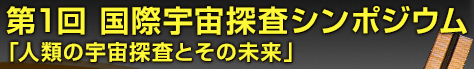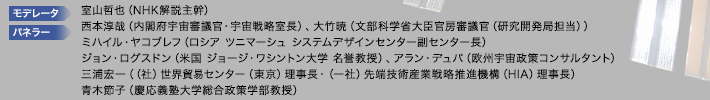
室山:日本は、2011年3月11日の東日本大震災の原発事故の後、科学技術に対する国民意識が変わりました。その中でどう有人宇宙開発に踏み出すべきか。無人宇宙探査を含めた日本の宇宙開発はどうあるべきか。について議論したいと思います。震災後をどのように捉えていらっしゃいますか?
青木:科学技術に対する信頼が揺らいだと言われることもありますが、科学技術そのものとそれを操る体制とは分けて考えるべきで、今回は後者に対する不信が顕になったのだと思います。人間は、どの時代も常に科学技術の先端を突破し、そのおかげで生活が豊になってきたと思います。仮に、科学技術そのものに対する不信が顕著なものになったとしても、だからこそ、今抱えている危機を、科学技術の力によって乗り越えなければならないと思うのです。例えば、宇宙に関して言えば、宇宙太陽光発電の研究開発を進めて将来のクリーンエネルギーを目指すといった具合に、科学技術の発展を進める中で、肯定的な未来に向かって出発する合意を作り出さなければならないと感じています。
三浦:東日本大震災では、科学技術のあり方を問われました。科学技術そのものというよりも、科学技術を運用するシステム等に対する問題を投げかけられたように思います。今後は産学官や国際間での連携を強化するなどして、科学技術のあり方を見直さなければならないと思います。
室山: 震災を受けて宇宙開発はどうあるべきだとお考えでしょうか?
西本:震災の時にはっきり分かったのは、宇宙がどれほど貢献できるかということです。例えば、震災で浸水をした所の水が、引き潮になっても引かないのは何故だろうと測位衛星で調べてみると、全体の地盤が70cmも沈んでいることが分かりました。また、電話がつながらない時は、通信衛星を使って通信網を確保することができました。このようなことから、宇宙利用が国民生活に役立つことを再認識したのです。
これからの宇宙開発は、皆さんの生活にどう役立てられるかという観点で進めていく必要があると思いますし、それをきちんと国民に理解していただいた上で進めていくことが大事だと思います。現在、私ども宇宙戦略室では宇宙基本計画を検討しておりますけれど、その中では、科学技術の向上、産業振興、安全保障利用の3つをバランスよく進めていくことが議論されています。この安全保障には防災も含まれています。
大竹:震災後、科学技術政策研究所で、科学技術に対する信頼度・期待度を2000人程の方に調査したところ、震災前後であまり変わっていないという結果が出ました。しかし、科学者に対する信頼度は下がりました。これまで科学技術に対して良い話ばかりしていた専門家に、裏切られたという思いがあるのかもしれません。これは大きな教訓で、今後の宇宙開発の進め方にも当てはまると思います。
先程お話がありましたように、震災時に人工衛星がとても役立ちました。また、特に若い世代の方が、宇宙にいる宇宙飛行士からのメッセージに元気づけられたという話も聞きました。確かに、宇宙は役に立ち、若い人を引きつけ、夢を掻き立ててくれるものです。けれども、専門家がその危険性を説き、何が実現できるのかをきちんと明らかにして進めていくべきだと思います。また、有人宇宙探査については、日本単独で行くことは難しいと思いますので、国際協力の枠組みの中で、日本がどんな役割を果たしていくべきかを、国際パートナーと議論をしていくべきだと思います。
室山:このような日本の話を聞いて、どのような印象をお持ちですか?
ログスドン:宇宙利用は、現代の社会になくてはならないものだと改めて思いました。普段一般の方は、自分たちの生活の中で通信衛星や測位衛星などが使われていることを意識しませんが、災害が起きた時に、その存在価値を認識します。それが、宇宙の活動を知ってもらえるきかっけになりますので、災害が起きた時にすぐに宇宙を役立てられるようにしておくことが重要だと思います。
ヤコブレフ:ロシアでも災害時の人工衛星の活用に力を入れています。できるだけ早く被災状況を把握するためには、衛星情報共有の国際的な取り組みが有効的であると思いました。
室山:先日行われた「ふわっと'92から20周年記念シンポジウム」で、「日本は有人宇宙開発をするべきか?」という質問をしてみたところ、反対の方からは、“安全性の問題”“コストがかかり過ぎる”という意見。一方、賛成の方からは“人類精神の拡大にはお金に換算できない価値がある”“技術力と人材は国力の証明である”という意見がありました。これを受けて、日本の有人宇宙開発の今後についてどう思われますか?
西本:1986年にスペースシャトル・チャレンジャー号の事故が起きた後、直ちに、アメリカの大統領が「不幸な悲しいことが起こったけれど、人類の未来のために、アメリカは宇宙開発を続けるんだ」という声明を出しましたが、私はそれを見てとても感動しました。人類全体の進歩のために、犠牲を払ってでもやらなければいけないんだという、アメリカの強い意志を感じたんです。でももし同じような事故が日本で起きたらどうでしょうか。国民から「そうだ!」と喝采を受けるようなメッセージを国から出せるかというと、なかなか自信を持てないのが正直なところです。
国際宇宙ステーション(ISS)のような国際協力の枠組みの中で、日本が貢献するということは大いにあると思いますが、日本独自の有人宇宙飛行は、社会としての受容性に問題があるように思います。小惑星探査機「はやぶさ」に代表されるロボティックスや自律制御など、日本が得意とする技術で世界に貢献するのが、日本の宇宙開発のあり方ではないかと思います。
大竹:日本が独自の有人宇宙探査をするかどうかは慎重に議論しなければならないことですが、個人的には、有人宇宙探査に関心があります。未知への挑戦は人間の欲求だと思っていますから。でも日本に独自の有人宇宙探査に挑戦する覚悟があるかどうかが大きな問題です。日本は長い鎖国時代を経て、明治維新で開国をした後に、外国に追いつけ追い越せでいろいろなものを輸入し、ここまでの経済大国になりました。これからは、海外の真似ではなく、自分たちで最初に何かにチャレンジする精神が必要だと言われています。でも皆の前を走っていれば、大きなリスクを被る可能性がありますので、その覚悟を持てるかどうかが一番大事なことだと思います。これは日本社会への挑戦かもしれません。
室山:私も、シャトル事故の後のアメリカ大統領の声明に感動をした1人ですが、人の命をかけてまで有人宇宙開発をすべきということに対してはいかがでしょうか?
ログスドン:私は2003年のコロンビア号事故の事故調査委員会の委員を務めました。事故の後、どう対応するかを検討しましたが、有人宇宙飛行を止めようという意見は誰からも出ませんでした。宇宙のフロンティアに挑戦し続けるという精神は、アメリカ社会の一部なのです。有人宇宙飛行は常にリスクを伴うものだという認識があり、それに関与する国・人は、ある程度のリスクを引き受けなければならない。そのリスクをできるだけ減らしたいけれど、ゼロになることはないという認識があるわけです。これは、宇宙開発に限らず、最先端の活動には必ずつきまとう問題です。ですから、それに対応できない日本社会は、未来志向の社会ではないのかもしれません。
青木:私は、人命の損失があったからといって、日本の宇宙開発が滞るとは全く思っていません。むしろ、失敗があった時に初めて、次は必ず成功させようという気持ちが国民の中に生まれると信じております。人類がアフリカで誕生して世界に拡がっていったように、宇宙へ行くことは人間の本能としてごく自然なことです。日本も今すぐにその一翼を担わなければならないと私は思います。
三浦:日本は資源も領土も少なく、しかも、GNP(国民総生産)が世界第3位から4位になりつつある時ですから、イノベーションの振興、つまり科学技術の振興が1番重要な鍵になると思います。科学技術を振興していくためには、ISSのような有人宇宙開発は必要だと思います。
但し、今後の日本の有人宇宙探査のあり方を改めて考える場合、我々が自然によって生かされているという認識から始めなければならないと感じています。人類だけでなく、動植物との共存も含めた環境、文明の中で、科学技術の振興がどうあるべきかを考え、その結果、有人宇宙探査が必要だということになれば、踏み出せばよいと思います。
西本:有人、無人に関わらず宇宙探査は科学技術の塊だと思っています。人類の未来に貢献するという意味でも、宇宙探査は必要だと思います。おそらく日本は科学技術の分野では世界のトップを走っていると思いますが、どんどんライバルが出てくるわけですから、積極的にその分野に投資をするべきだと思います。しかしその時に、目標をしっかり見据えたうえで取り組む姿勢が大切です。アメリカの年間宇宙予算が4.5兆円に対して、日本の宇宙予算は年間3000億円。アメリカの15分の1しかない予算で、アメリカと同じようなことはできないと思いますので、具体的な目標を掲げて、それを達成するためのメリハリのある予算配分をしなければならないと思います。
その優先順位を考える時に、有人探査にこだわる必要はないというのが私の考えです。天文衛星や「はやぶさ」といった日本の科学衛星は、世界的にも高い評価を得ています。少ない予算の中で、日本の科学技術の粋を集めて作り、素晴らしい結果を残しているのです。有人については、人間でなければできないことが何かをしっかり説明し、それが国民にも認められた上で進めるべきだと思います。
デュパ:欧州でも有人か無人かという議論をすることがありますが、例えば、ISSはすべてを自動化することはできず、宇宙飛行士がいなければ実験の運用はできません。もちろん、ロボットだからできることはありますが、人間でなければできないこともある。そういう意味では、人間とロボットを比較するのではなく、お互いに補完する関係が理にかなっていると思います。欧州宇宙機関ではそのような考えのもとで、バランスがとれた形で予算が配分されています。

室山哲也(NHK解説主幹)

青木節子(慶応義塾大学総合政策学部教授)

三浦宏一((社)世界貿易センター(東京)理事長・(一社)先端技術産業戦略推進機構(HIA)理事長)
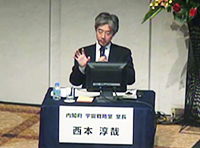
西本淳哉(内閣府宇宙審議官・宇宙戦略室長)
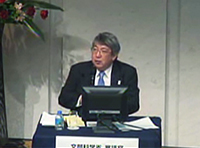
大竹暁(文部科学省大臣官房審議官(研究開発局担当))

ジョン・ログスドン(米国 ジョージ・ワシントン大学 名誉教授)
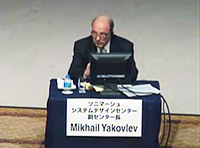
ミハイル・ヤコブレフ(ロシア ツニマーシュ システムデザインセンター副センター長)
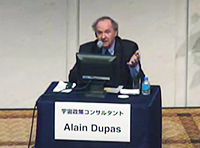
アラン・デュパ(欧州宇宙政策コンサルタント)