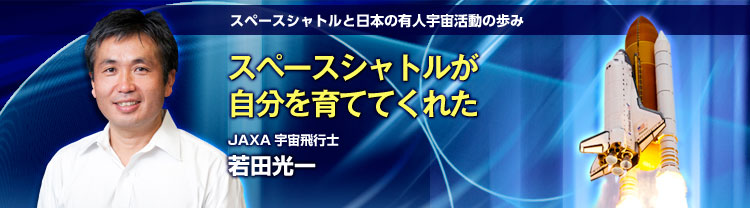Q. 若田宇宙飛行士はもともと飛行機の技術者であり、ロボットアームの専門家でもあります。技術者の視点からスペースシャトルをどのような宇宙船だと思いますか?

2005年5月に行われた、5回目のハッブル宇宙望遠鏡の修理ミッションのようす(STS-125)(提供:NASA)
スペースラブ(スペースシャトルを使って打ち上げられた宇宙実験室)を使った数多くの宇宙実験、ISSの組み立て、ロボットアームを使った人工衛星の回収など、スペースシャトル独自の能力を活かしたさまざまな有人宇宙活動が行われてきました。その意味で、スペースシャトルは非常に多様性に富んだ宇宙往還システムだと思います。例えばハッブル宇宙望遠鏡は、スペースシャトルによる船外活動を駆使した5回のメンテナンス飛行が実施されなかったらここまで延命できなかったでしょう。スペースシャトルは、この30年間、間違いなく有人宇宙開発の一時代を築いてきましたし、これだけの多様な能力を持つ宇宙船は、今後当分の間出てこないと思います。
スペースシャトルは、オービターと外部燃料タンク、固体ロケットブースターという組み合わせの宇宙往還機ですが、人だけを乗せるソユーズ宇宙船やアポロ宇宙船のようなカプセル型のものに比べると、運用上の大きなリスクがあります。それは、カプセル型宇宙船は打ち上げや帰還時のほとんどの段階からでも緊急脱出ができるのに対して、スペースシャトルは水平飛行状態でなければ脱出できない仕組みになっているからです。
スペースシャトル構想の初期には、固体ロケットを使わない液体燃料ブースターによる完全再使用型など、いろいろなオプションがあったようですが、開発が行われた70年代のアメリカにおける技術水準と、当時の経済状況下では、推力が高い固体ロケットを使うという形で収束せざるを得なかったのでしょう。スペースシャトルの持つ能力は非常に優れたものですが、安全性と経済性も含めて満足できる宇宙往還システムを構築することは、世界の宇宙開発をリードしてきたアメリカにとっても難しい課題であったと思います。
Q. これまでの飛行で印象に残っていることはありますか?

1996年1月、若田宇宙飛行士が初めて搭乗したスペースシャトルの打ち上げ(提供:NASA)
いろいろありますが、中でも1996年の初めての飛行は印象に残っています。やはり宇宙へ行くまでは分からないなあと思ったことがありました。打ち上げは午前4時過ぎで暗く、スペースシャトルが発射台から離れる時に操縦室天井の窓から外を見ると、発射台がメインエンジンの炎に照らされて明るく、まるで昼間のようでした。そして、打ち上げから4〜5分程経つと、窓の外に、稲妻がピカピカ光っているような光景が見えたんです。このような光が見えることは事前に聞いていなかったので、これは何だろう?と不思議に思いました。でも他のクルーはその光を見ても平然としています。だから、たぶん大丈夫だろうと思いつつも心配で、メインエンジンが停止すると、船長に「窓の外が光っていたけど大丈夫ですか?」と聞いたんです。すると、上空に行って空気が薄くなると、それまで下に向かって噴射していたメインエンジンの炎が機体の前方にも回り込んで、ピカピカ光って見えると教えてくれました。
そして、この炎の光とともに窓の外に見えていたのが薄い氷のかけらでした。映画で、スローモーションでガラスが割れるようなシーンがありますが、それと同じように、氷の大小の板状の破片がゆっくり窓の外をスペースシャトルに吸い付くように飛んでいきます。打ち上げは1月でとても寒い日だったのですが、打ち上げ前から外部燃料タンクに付着していた氷が打ち上げ上昇時にはがれ落ちていたのです。それはまるで輝く宝石のようで、メインエンジンの炎でピカピカ光る宙を、たくさんの宝石と一緒にスペースシャトルが突き抜けていくような印象を受けました。このような光景に遭遇することは、宇宙に行ってみて初めて分かったことです。
しかし、この氷と同じように打ち上げ時に機体からはがれ落ちるものが、将来、大事故を起こすことを予測できた人はほとんどいませんでした。2003年のコロンビア事故は、外部燃料タンクからはがれた断熱材が、スペースシャトルの左翼の前縁部の熱防護材を砕いたのです。初飛行の時に窓から見た光景を思い出すと、もしかしたら、あの氷の塊がスペースシャトルの機体を損傷して、事故を起こしていたかもしれないという気持ちになります。そういう意味でも、この時の光景は目に焼き付いています。