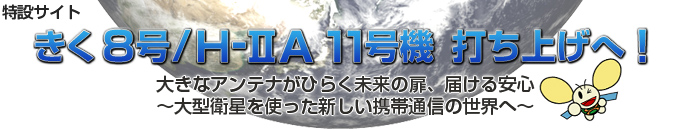ここでは、これまで開発・運用した技術試験衛星をご紹介します。
 技術試験衛星VII型「おりひめ・ひこぼし」は、将来の宇宙活動において必要なランデブ・ドッキング技術や宇宙用ロボット技術を修得することを目的とした人工衛星です。この衛星は、チェイサ衛星(ひこぼし)とターゲット衛星(おりひめ)の2機の衛星から構成されており、2機は打ち上げ後宇宙空間で分離し、自動操縦により分離や接近・ドッキングを行うランデブ・ドッキング実験を3回実施しています。
| 打ち上げ |
1997(平成9)年11月28日/H-IIロケット6号機
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
高度約550kmの円軌道/傾斜角 約35度/周期約96分 |
| 質量 |
約2,860kg |
| 寿命 |
1.5年 |
| 形状 |
展開型太陽電池パドルを有する箱型 |
|
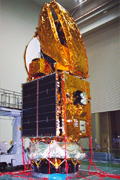 1990年代における高性能実用衛星開発に必要な大型三軸衛星バス技術の確立を図るとともに、高度の衛星通信のための搭載機器の開発・実験を目指して開発されました。
| 打ち上げ |
1994(平成6)年8月28日/H-IIロケット試験機2号機
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
高度約36,000kmの静止軌道/153.8度の赤道上 |
| 質量 |
約2,000kg ペイロード 660kg以上 |
| 寿命 |
10年(衛星バスシステム) |
| 形状 |
展開型太陽電池パドルを有する箱型 |
|
 きく5号は3軸姿勢の衛星技術を確立し、移動体通信実験を実施した技術試験衛星です。H-Iロケット(3段式)の試験機の性能を確認するとともに、静止3軸衛星バスの基盤技術を確立し、次期実用衛星開発に必要な自主技術の蓄積と、移動体通信実験を行うために打ち上げられました。
| 打ち上げ |
1987(昭和62)年8月27日/H-Iロケット2号機F(H17F)(3段式試験機)
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
高度約36,000kmの静止衛星軌道/傾斜角0度/静止位置東経150度 |
| 質量 |
打ち上げ時 約1,096kg(アポジ含む) 静止軌道上初期 約550kg |
| 寿命 |
1.5年以上 |
| 形状 |
展開型太陽電池パドルを有する箱型 |
|
 きく4号は電力を必要とする地球観測衛星などの開発力を高めるために、3軸姿勢制御や太陽電池パドル展開機能の確認、能動式熱制御に関する実験、イオンエンジン装置の動作テストなどを行いました。1985年3月8日、姿勢制御燃料が枯渇状態となったため運用を終了しました。
| 打ち上げ |
1982(昭和57)年9月3日/Nロケット9号機(F)
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
高度約1,000kmの円軌道/傾斜角 約45度/周期約107分 |
| 質量 |
約385kg |
| 形状 |
展開型太陽電池パドルを有する箱型 |
|
 きく3号は気象衛星、通信衛星、放送衛星など、350kgクラスの静止衛星打ち上げ用N-IIロケットの、打ち上げ能力の確認と搭載実験機器の機能試験などを行いました。1984年12月24日、太陽電池の発生電力の低下が著しくなったため、運用を停止しました。
| 打ち上げ |
1981(昭和56)年2月11日/Nロケット7号機(F)
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
近地点225km遠地点36,000kmの楕円軌道/傾斜角約28.5度/周期約10時間36分 |
| 質量 |
約640kg |
| 形状 |
直径約210cm、円筒形、高さ約280cm |
|
 きく2号は静止衛星の打ち上げと追跡管制技術、軌道保持、姿勢保持技術などの習得、通信機器の宇宙環境での機器試験などを行うために打ち上げられ、日本初の静止衛星になりました。そして、1990年12月10日に全ての運用を終了し、静止軌道外へ移動させました。
| 打ち上げ |
1977(昭和52)年2月23日/Nロケット3号機(F)
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
静止衛星軌道/静止位置東経130度 |
| 質量 |
約130kg |
| 形状 |
直径約140cm、円筒形、高さ90cm |
|
 宇宙開発事業団の初の人工衛星として、Nロケットの打ち上げ技術、衛星の軌道投入・追跡および運用技術などを総合的に習得するために打ち上げられ、1982年4月28日に運用を停止しました。
| 打ち上げ |
1975(昭和50)年9月9日/Nロケット1号機(F)
種子島宇宙センター |
| 軌道 |
高度約1,000kmの円軌道/傾斜角 約47度/周期約106分 |
| 質量 |
約82.5kg |
| 形状 |
直径約80cmの26面体 |
|
 技術試験衛星VII型「おりひめ・ひこぼし」は、将来の宇宙活動において必要なランデブ・ドッキング技術や宇宙用ロボット技術を修得することを目的とした人工衛星です。この衛星は、チェイサ衛星(ひこぼし)とターゲット衛星(おりひめ)の2機の衛星から構成されており、2機は打ち上げ後宇宙空間で分離し、自動操縦により分離や接近・ドッキングを行うランデブ・ドッキング実験を3回実施しています。
技術試験衛星VII型「おりひめ・ひこぼし」は、将来の宇宙活動において必要なランデブ・ドッキング技術や宇宙用ロボット技術を修得することを目的とした人工衛星です。この衛星は、チェイサ衛星(ひこぼし)とターゲット衛星(おりひめ)の2機の衛星から構成されており、2機は打ち上げ後宇宙空間で分離し、自動操縦により分離や接近・ドッキングを行うランデブ・ドッキング実験を3回実施しています。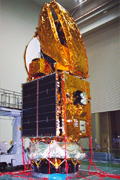 1990年代における高性能実用衛星開発に必要な大型三軸衛星バス技術の確立を図るとともに、高度の衛星通信のための搭載機器の開発・実験を目指して開発されました。
1990年代における高性能実用衛星開発に必要な大型三軸衛星バス技術の確立を図るとともに、高度の衛星通信のための搭載機器の開発・実験を目指して開発されました。 きく5号は3軸姿勢の衛星技術を確立し、移動体通信実験を実施した技術試験衛星です。H-Iロケット(3段式)の試験機の性能を確認するとともに、静止3軸衛星バスの基盤技術を確立し、次期実用衛星開発に必要な自主技術の蓄積と、移動体通信実験を行うために打ち上げられました。
きく5号は3軸姿勢の衛星技術を確立し、移動体通信実験を実施した技術試験衛星です。H-Iロケット(3段式)の試験機の性能を確認するとともに、静止3軸衛星バスの基盤技術を確立し、次期実用衛星開発に必要な自主技術の蓄積と、移動体通信実験を行うために打ち上げられました。 きく4号は電力を必要とする地球観測衛星などの開発力を高めるために、3軸姿勢制御や太陽電池パドル展開機能の確認、能動式熱制御に関する実験、イオンエンジン装置の動作テストなどを行いました。1985年3月8日、姿勢制御燃料が枯渇状態となったため運用を終了しました。
きく4号は電力を必要とする地球観測衛星などの開発力を高めるために、3軸姿勢制御や太陽電池パドル展開機能の確認、能動式熱制御に関する実験、イオンエンジン装置の動作テストなどを行いました。1985年3月8日、姿勢制御燃料が枯渇状態となったため運用を終了しました。 きく3号は気象衛星、通信衛星、放送衛星など、350kgクラスの静止衛星打ち上げ用N-IIロケットの、打ち上げ能力の確認と搭載実験機器の機能試験などを行いました。1984年12月24日、太陽電池の発生電力の低下が著しくなったため、運用を停止しました。
きく3号は気象衛星、通信衛星、放送衛星など、350kgクラスの静止衛星打ち上げ用N-IIロケットの、打ち上げ能力の確認と搭載実験機器の機能試験などを行いました。1984年12月24日、太陽電池の発生電力の低下が著しくなったため、運用を停止しました。 きく2号は静止衛星の打ち上げと追跡管制技術、軌道保持、姿勢保持技術などの習得、通信機器の宇宙環境での機器試験などを行うために打ち上げられ、日本初の静止衛星になりました。そして、1990年12月10日に全ての運用を終了し、静止軌道外へ移動させました。
きく2号は静止衛星の打ち上げと追跡管制技術、軌道保持、姿勢保持技術などの習得、通信機器の宇宙環境での機器試験などを行うために打ち上げられ、日本初の静止衛星になりました。そして、1990年12月10日に全ての運用を終了し、静止軌道外へ移動させました。 宇宙開発事業団の初の人工衛星として、Nロケットの打ち上げ技術、衛星の軌道投入・追跡および運用技術などを総合的に習得するために打ち上げられ、1982年4月28日に運用を停止しました。
宇宙開発事業団の初の人工衛星として、Nロケットの打ち上げ技術、衛星の軌道投入・追跡および運用技術などを総合的に習得するために打ち上げられ、1982年4月28日に運用を停止しました。