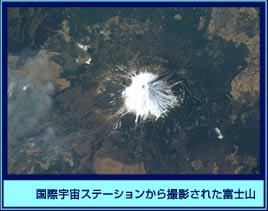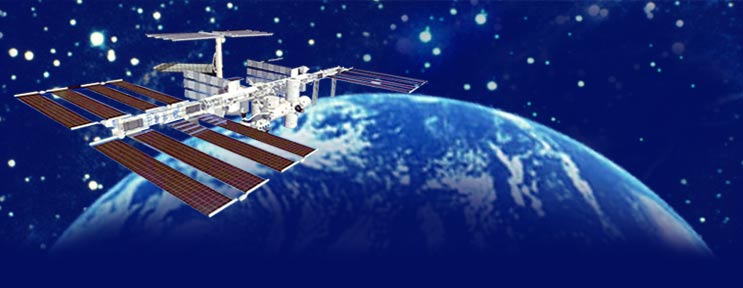 |
EarthKAMは世界中の学生が操作しますが、私がそのデジタルカメラをアメリカの実験モジュール「デスティニー」の窓に設置し、焦点を合わせ、地球に写真を送信する装置に接続しました。 ヨーロッパやアジア、北米の50校以上の学校が参加し、生徒たちがインターネットを通じて撮影場所の緯度や経度を指定すると、カメラが自動的に撮影をします。私たちが昼食をとっている時などに、突然カシャ、カシャとカメラの撮影音が聞こえてくると、非常に興味深く、私は窓の所まで行って、何処の写真を撮っているかを見ました。時には、陸を撮ろうとした時に雲が多すぎることもありました。また、日本の写真を撮っていた時に、「誰がこの写真を撮っているか知っているぞ」と思うこともありました。 EarthKAM実験をとても興味深いと思うのは、人々が地球に大変感心を持っていることが分かったこと、そして、その人々が何を行い、何に興味を持っているかが見て取れたからです。 また実験ではありませんが、とても興味深いことがありました。アメリカの実験モジュール「デスティニー」の窓のシステムの一部で微量の空気漏れを発見したのですが、他の場所でも空気漏れがあるかもしれないということで、宇宙ステーションのいくつかのハッチを閉じて空気漏れの点検を行いました。その際、私とカレリさんの2人は、サービスモジュール「ズヴェズダ」内の狭い場所での共同生活を余儀なくされたのです。他に行けたのはソユーズ宇宙船だけで、それはミール宇宙ステーションで生活した時よりも更に狭い空間でした。こういった環境で生活をしたのは2日間だけでしたが、長距離の飛行で月や火星に行く場合と同じような狭い状況で生活をするという経験ができ、とても興味深かったです。
私たちが船外活動を行っている間は、まるで私たちが地球に戻るために長期間留守するかのように、国際宇宙ステーションの生命維持装置を停止しました。私たちが外にいる間、宇宙ステーションは「保存」の状態でした。内部の環境を良い状態のままにしておいたので、後で戻った時に何か問題が起きているという心配はありませんでした。 また私たちは、ロシアのエアロックが万が一使えなかった場合のことを想定して、アメリカのエアロックをって国際宇宙ステーションの中に戻れる準備もしていましたし、宇宙ステーションに戻れなくなった場合には、ソユーズ宇宙船に付いているエアロックを使って緊急避難する訓練も行っていました。 ですから、私もカレリさんも特に心配はありませんでした 。 地上管制側は、国際宇宙ステーションを無人にしたことがなかったため非常に心配していたようですが、私にはそれをやり遂げる自信がありました。 日本のJAXAの微小粒子捕獲実験及び材料曝露実験(MPAC&SEED:Micro-Particle Capturer and Space Environment Exposure Devices)の装置を交換しました。これは日本が2001年から行っている実験で、スペースデブリなど宇宙の微小粒子を捕獲しています。私たちの役目は、その実験装置を船内に戻し、細心の注意を払って梱包し、地球に戻すことでした。 また、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の放射線計測実験装置の設置と配線の接続なども行いました。
|
|