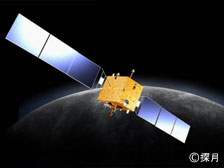Q.最近フリードマン博士は、中国との国際協力を進めていますが、どのようなミッションですか? 近年、中国は有人宇宙飛行を成功させ、世界は中国を「新たに宇宙進出を果たした国家」として歓迎してきました。これから中国は有人宇宙飛行に力を入れていくでしょう。政府が積極的な投資をしていますし、施設も充実していて、若い技術者たちが月探査ミッションに取り組んでいます。技術的には、部品など専門的なパーツを輸入せざるえないところもありますが、宇宙船の開発や科学探査における独自の技術開発に非常に力を入れています。 私が特に評価しているのは、中国が月や惑星探査に興味を持っていることです。これは軍事的な決断ではなく、科学目的のために行われることであり、国の発展を促すために行われているのです。平和的な活動ですから、奨励すべきだと思いますし、中国とは協力関係を築きながら友好的に競合していきたいと思います。
月関連のミッションは中国だけでなく、日本、インド、ヨーロッパ、そしてアメリカで進められていますので、一カ国が単独ですべてを行うのではなく、数カ国が協力して結果を共有していくべきだと中国の宇宙関係者に話をしています。今は米中関係がとりわけ良好ではありませんが、米ソの冷戦時代もそうであったように、国際協力を強く推し進めるべく努力していくのは民間である私たちの役目だと思っています。月関連のミッションを通じて、中国を含めた参加各国が友好関係を築いていければと思います。 Q.中国は、国際協力に積極的ですか? これまで会談した限りでは、中国は国際協力に対する強い希望を示しています。もちろん、中国は独自に月探査ミッションを遂行する能力を保有したいと考えています。これは中国だけが思っていることではありません。宇宙開発を行っている国は、外国の技術に依存するだけでなく、自国の才能を使って、自国の科学者と技術者を育成したいと考えています。中国は自分たちのミッションの利益となる、自国の能力を高める国際協力関係を望んでいるのです。この立場は、独自の惑星探査、月探査を進めている日本とも非常に似ています。要するに、国際協力を行う上では、「プロジェクトを遂行する際に、他国に少々依存するのは結構である」という考えでよいと思います。 その例が、国際宇宙ステーションです。国際的な協力関係、依存関係がなかったら、国際宇宙ステーションが建設されることはなかったことでしょう。ただ問題だったのは、アメリカのスペースシャトルに依存しきっていたということです。現段階ではシャトルの信頼性が高いものではありません。この宇宙輸送に関しては、もっと国際的な共同計画があるべきだったと思います。 Q.今後中国が、日本やヨーロッパ、ロシアのように、アメリカの宇宙開発のパートナーになると思いますか? はい、そう思います。中国がアメリカをはじめとする世界各国のパートナーになる可能性は充分ありますし、また、そうあるべきだと思います。単なる競争相手としてではなく、各国が中国と高いレベルで協力体制を築けば、より優れたものになると思います。そうすれば、関係各国と国民の関係も良好なものになっていくでしょう。 私たち惑星協会には国際共同ミッションの実績があります。1980年代はまだ米ソ冷戦時代で、両国にはまったく協力関係がありませんでしたが、ハレー彗星探査と火星探査のミッションで、私たちが協力関係を築きはじめたのです。アメリカがロシアに科学者を送り、ロシアも同様に自国の科学者をアメリカに派遣する中で、共同プロジェクトを推進していきました。そして驚くべきことに、NASAが私たちの後に続き、1990年代までには両国政府間に協力関係が生まれたのです。私たちの力でそれが実現したとは言いませんが、それを目指して努力し、あらかじめ関係を構築することは私たちでも可能だと思います。 |
| 1 2 3 4 5 |