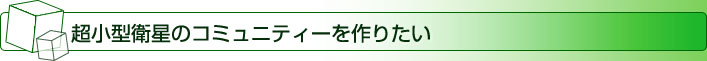
Q. 今後、先生はどのような研究をなさりたいですか?
私は、重量10kg以下の超小型衛星にこだわりたいと思っています。超小型衛星でどこまでの宇宙開発ができるのか、実用的なミッションができるのかを追求していきます。普通大きな衛星でしかできないと思っていたミッションを、どうやったら10kgの衛星に押し込められるかというのが研究開発の課題になります。例えば、大型衛星だったらこの方法で実現できる機能を、超小型衛星だったら別の方法で実現できるなど、実現の仕方や違う方法を小さな衛星用に開発していきたいと思います。また、小さな衛星を使って人工知能の研究もしていきたいと考えています。そして、費用が高い大型衛星だとなかなかできないような実験をどんどんやっていきたいです。宇宙にある衛星で実験をすることに意義があると思いますし、そこで開発された技術は、宇宙開発だけでなく情報処理につながる技術など幅広く展開されていくと思います。
その一方で、衛星を作るだけでなく、それを使う人たちのコミュニティーを作りたいと思います。これから、商業的にも小さな衛星を使う人たちが必ず出てきます。既に、2機の「CubeSat XI」を打ち上げてから、「こういうビジネスをしたいのだけど打ち上げてくれませんか」という話をたくさんいただいています。小さい衛星にかかる費用は企業の広告費と同じくらいですから、宇宙で何かやりたいと思っている企業にとっては魅力的なのだと思います。ですから、そういう人たちの要望に応えられるような衛星を作っていきたいです。これは1つの宇宙開発の世界になると思うんです。そのコミュニティーの中には、物を作る人と、使う人がいて、皆で1つのコミュニティーを形成していく。そういった世界を超小型衛星の分野で作っていきたいと思います。
Q. 先生は、宇宙をどのように利用していきたいと思われますか?
最近は、宇宙旅行というのが話題になっていて、これは新しい宇宙の使い道ができたという意味で、1つの大きなブレイクスルーだと思いますが、全般的には、宇宙をこう利用するというアイデアが少ないと思います。しかし、私たちのように宇宙にどっぷり浸かっている人たちからは、なかなか新しいアイデアが出てきません。ですから、私たち専門家が宇宙の利用方法を考えるのではなく、それを考える人を宇宙にたくさん取り込んでいくことが必要だと思います。その中から、私たちが想像もしないような宇宙の利用方法が出てきて、もしかしたら、それが宇宙の将来ビジョンになるかもしれません。要は、宇宙で何かをやりたいと考えてくれる人をどれだけ巻き込むかが鍵であり、逆に言えば、宇宙で何かができるんだと思わせることが重要なんだと思います。ですから、私は今、こういうふうに宇宙を利用したいということでなく、それを考える人を増やしたいと思っています。そのためにも、私は超小型衛星の研究・開発を続けていきたいと思います。
|