
Q.GOSATの優れた点 はどういったところでしょうか?
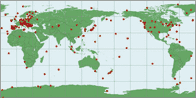
現在の地上観測地点:約260点
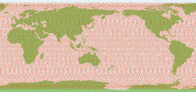
GOSATの観測地点:56,000点
まずは、分光分解能が非常に高いことです。GOSATの温室効果ガス観測センサは、赤外線の光の波長を約18,000チャンネルで測定します。チャンネル数が多いというのは、二酸化炭素やメタンをいかに詳しく、高精度に見られるかということです。一言でいえば、赤外線を18,000現色で細かく分析することになります。まるで、空を飛ぶ分光器です。
また、GOSATでは、4ppm、100万分の4という極めて微量な二酸化炭素の濃度の変化を測定することができます。地球の大気中の二酸化炭素の濃度は平均すると370ppm、100万分の370で、その1年間の濃度の変化はだいたい4ppmと言われています。ですから、4ppmの変化が測れないと意味がありません。GOSATは1ppm、要するに100万分の1の変化を測定することを目標に開発しています。1ppmというのがどれくらいの量かと言いますと、例えば、200リットルくらい入る風呂桶に、目薬を4滴たらして、その4滴の変化を検出できるくらいの精度です。ここまでの細かい精度を出すのは大きなチャレンジですが、私たちはそれを達成したいと思います。
さらに、GOSATのすごいところは、観測ポイントが全世界で56,000点もあるということです。GOSATは、高度666kmの軌道を1日で14周し、3日間で全球を観測します。通常、地上からの観測ですと、場所によって観測機器が違いますが、GOSATの場合は1つの測定機器で観測します。このように、偏りのない全球データが3日ごとに取れるということも大きな特徴です。
現在、世界の温室効果ガスの観測地点は約260点で、そのデータが月に1度程度、温室効果ガス世界資料センターを通じてインターネットで配信されています。この観測地点はヨーロッパと日本、アメリカでは細かく分布していますが、それ以外ではとても少ないのが現状です。これでは、世界の温暖化の平均値は分かっても、地域ごとに、また季節ごとにどうなっているかが分かりません。特に分からないのは海洋で、どの地域でどれだけの二酸化炭素が吸収されたり、吐き出されているのかはよく分かっていません。現在は非常に多くの研究所が地球温暖化問題に取り組んでいますから、例えば、アマゾンで夏に洪水があって川が氾濫し、水が引いた後にジャングルの木が根腐れしてメタンガスが発生したとか、シベリアの永久凍土が溶けてメタンガスが出てきたといったような話は、そのポイントごとに出てきています。しかし、それを世界地図のように「面」という形で見た時にどうなっているのかという、総合的なデータはまだありません。GOSATが世界で初めて定常的に、多くの観測点で温室効果ガスを観測するのです。だからこそ、世界中がGOSATに期待しています。
Q.開発において特に重点をおいたポイントはありますか?
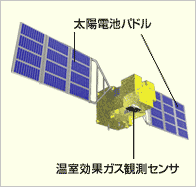
従来の衛星ですと、寿命はだいたい3年間といわれていますが、GOSATは京都議定書の第一約束期間の5年間を継続して観測することを目標にしています。人工衛星の場合、打ち上がった後では修理ができません。ですから、信頼性の高い部品を使うというのは当然ですが、それに加えて、ある部分が壊れた時にそれと置き換えられるような代替機能をつけています。どの機器も2段構えで備え、片方が失敗しても観測が継続できるようにしてあります。このような機能を冗長系と言います。
従来は、性能が低下してしまうという理由から、センサの中で代替機能を持たせるのは難しいとされてきましたが、GOSATはセンサの中にも冗長系を持っています。例えば、前後左右に振って地上を観測するミラーは通常一式しかありませんが、GOSATには2系統あって、それが完全に独立して動くようになっています。ですから、片方が完全に壊れても、もう1つのミラーを使って観測を継続することができます。
また、衛星本体でも信頼性を上げるための工夫がいろいろあります。例えば、太陽電池パドルです。従来の衛星では片翼だけのものが多かったですが、GOSATは2翼の太陽電池パドルです。これまでは、片翼だけでも十分な信頼性があるということでやってきましたが、残念ながら、過去の地球観測衛星「みどり(ADEOS)」「みどりII(ADEOS-II)」で、2度続けて太陽電池や電源系に関する問題が起き、運用が短期間で終了してしまったという失敗があります。その失敗を繰り返さないためにも、GOSATは太陽電池パドルを2翼にしてあります。しかし、2翼にしただけでは完全な解決にはなっていません。もし1翼が壊れたら、電気が半分になってしまいます。その半分の電気で衛星を運用するのは非常に難しいことです。衛星にはセンサの他にもいろいろな機器があり、それを全部動かすためだけでなく、衛星全体の温度を維持するための電気も確保しなければなりません。GOSATは 電気が半分になった場合でも、ただ生き残るだけでなく、最低限の観測ができるように、省エネモードを設けました。ここが最も工夫した点でもあり、苦労した点でもあります。
このように、衛星の寿命を5年間保証するための設計を徹底的に行った衛星は、世界でもGOSATが初めてだと思います。GOSATは絶対に失敗させたくありません。
Q.打上げ後はどのようなスケジュールで運用されるのでしょうか?
打上げは2008年度を予定しています。最初の3ヶ月間程は、衛星のすべての機能が正常に動くか確認をします。その次の3ヶ月間は、集中的にデータを取り、そのデータを地上からの観測データなどと比較して校正します。本当にどれくらいの精度なのかを検証し、その後、本格的なデータを取得し始めます。
GOSATは、衛星と観測センサの開発をJAXAが行い、データ利用を環境省と国立環境研究所が担当する共同プロジェクトです。JAXAが取ったデータを使って、国立環境研究所が世界中の二酸化炭素やメタンの濃度分布を出したり、地域ごとの吸収排出量を出します。そのような作業にどれくらいの時間がかかるか今はまだ分かりませんが、打上げから1年後にはデータを配布できるようにしたいと思います。データは全世界に無料で提供する予定です。
Q.GOSATの観測によって、科学的な研究が行われる予定もありますか?
温室効果ガスに関する研究者などからなる「GOSATサイエンスチーム」を組織しています。定期的に会合を開き、科学者の立場から専門的なご意見をいただいて、それを開発にも反映しています。打上げ後にはデータを皆さんに配布し、共同で研究することになっています。その成果は論文という形で発表されるほか、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change)」に参加している方たちもチームに入っていただいていますので、IPCCがこれから出す報告書という形で、データが直接貢献することもあるでしょう。また、アメリカやヨーロッパの科学者たちも、GOSATのデータを使って研究を進め、その成果はIPCC等を通じて発表されていくと思います。
ただし、JAXAにとって一番大事なのは、正確なデータをきちんと取得することです。JAXA自身は温室効果ガスの研究を専門としていませんので、後ろから研究者たちを支援するというのが大きな役割だと思います。