
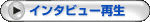
ファイルサイズ:13.6MB
フォーマット:MPEG |
|
Q.すばる望遠鏡のこれまでの大きな成果は何ですか?
すばる望遠鏡の本格的な成果は、これからだと私は思っています。完成して実際に活動を始めてからまだ3年ですから、そろそろ望遠鏡として脂がのり、いろいろな装置が100パーセント稼働して自由自在に性能を発揮しはじめています。ある意味、こういうものは永久に完成しません。複雑な装置がいろいろあり、それを使い込んで良い性能を出す。さらに頑張って改善すれば、想定した以上の良い性能を出すこともできるわけです。ですから私たちはいつも改良・性能改善との戦いです。常に良くしていくのです。他の望遠鏡も改善してきますから、競争してお互いに良くなり、次々に新しい観測ができるというわけです。
実は、すばる望遠鏡ほど複雑で高精度、しかもいろいろな観測機能を持った8m級望遠鏡は世界中にありません。いま口径8メートル級の望遠鏡は、ヨーロッパが4台、アメリカは4台、日本は1台で計9台が世界で動いていますが、日本は1台だけですから、そこにいろいろな機能を集中させました。望遠鏡というとやはりまず、きれいな画像を撮らなければなりませんが、その性能は世界一です。世界中の観測者が来て他と比較し、これはすごいと言っています。まずは、それがすばる望遠鏡の第一の成果でしょうか。
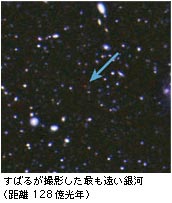 搭載された装置を使った観測が既にたくさん行われていますが、一番華々しいのは、先程申し上げたような非常に遠い天体を次々発見していることです。すばる望遠鏡は宇宙の遠い天体観測のレコードホルダーで、今見つかっている遠い天体を一番遠い順から10並べると、そのうち9つまではすばる望遠鏡が発見したものです。すばる望遠鏡は微かな像をとらえる能力が高いため、非常に遠くの天体を次々に見つけているのです。何故遠いかすかな天体を見たいかというと、遠くは宇宙の始まりに近いところだからです。例えば、現在は宇宙の誇張が始まってからおよそ137億年と言われていますが、すばる望遠鏡が発見した一番遠い銀河(それぞれがおよそ1千億の恒星の集まり)の距離は128億光年向こうで、そこから光が来るまでに128億年かかりますから、128億年前の銀河ということになります。つまり宇宙の膨張が始まってから9億年経った銀河です。137億年経った今の銀河の年齢を仮に50歳とすると、9億年しか経っていない銀河はまだ3才すぎの幼児ということになります。そういう意味からすると、すばるは宇宙膨張がはじまったばかりの頃の宇宙に迫っています。これに関してはすばるの独壇場というとちょっと言いすぎですが、いま世界をリードしているのは確かです。他にも太陽系内の現象から遠い銀河まで発見した成果はいろいろあり、毎月ニュースになっています。 搭載された装置を使った観測が既にたくさん行われていますが、一番華々しいのは、先程申し上げたような非常に遠い天体を次々発見していることです。すばる望遠鏡は宇宙の遠い天体観測のレコードホルダーで、今見つかっている遠い天体を一番遠い順から10並べると、そのうち9つまではすばる望遠鏡が発見したものです。すばる望遠鏡は微かな像をとらえる能力が高いため、非常に遠くの天体を次々に見つけているのです。何故遠いかすかな天体を見たいかというと、遠くは宇宙の始まりに近いところだからです。例えば、現在は宇宙の誇張が始まってからおよそ137億年と言われていますが、すばる望遠鏡が発見した一番遠い銀河(それぞれがおよそ1千億の恒星の集まり)の距離は128億光年向こうで、そこから光が来るまでに128億年かかりますから、128億年前の銀河ということになります。つまり宇宙の膨張が始まってから9億年経った銀河です。137億年経った今の銀河の年齢を仮に50歳とすると、9億年しか経っていない銀河はまだ3才すぎの幼児ということになります。そういう意味からすると、すばるは宇宙膨張がはじまったばかりの頃の宇宙に迫っています。これに関してはすばるの独壇場というとちょっと言いすぎですが、いま世界をリードしているのは確かです。他にも太陽系内の現象から遠い銀河まで発見した成果はいろいろあり、毎月ニュースになっています。
|

