
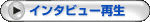
ファイルサイズ:18.2MB
フォーマット:MPEG |
|
Q.今後JAXAとどのようなことを一緒にやっていきたいですか?またJAXAに期待することがあったら聞かせてください。
天文学にとって、宇宙空間からの観測は非常に大事です。すでに旧宇宙科学研究所(現JAXA宇宙科学研究本部)がたくさんの天文観測衛星を打ち上げていますが、地上に望遠鏡を作って観測するだけでなく、宇宙に衛星を打ち上げる理由はやはり、空気の邪魔がないからです。かろうじて空気を通ってくる可視光でも雲があると見えませんし、ゆらぎで像が乱れます。また電波では波長が長いと地球の電離層の電子が邪魔をして通さず、波長が短いと水蒸気が邪魔をしてなかなか通ってきません。その他にもX線を全く通さないなど、空気の底にいる限り、宇宙についてわかる範囲が非常に限られています。
一方、地上から宇宙を見ることができるのは、可視光から近赤外線という少し波長の長い光と、ずっと波長が長い電磁波である電波で、それを観測するための巨大で複雑な光赤外線望遠鏡(例えば「すばる」)と、電波望遠鏡(例えば野辺山のミリ波電波望遠鏡群)が地上にあります。しかし、こういった大きな望遠鏡を宇宙に打ち上げるのは大変です。すばる望遠鏡や45m電波望遠鏡を宇宙に打ち上げろと言われても、今は不可能です。その代わり、地上では観測できないX線の望遠鏡や、波長の長い赤外線を観測する、比較的小型の望遠鏡を宇宙に打ち上げます。そうすると今までと異なる観測ができ、違う宇宙が見えてくるのです。
その良い例が、ブラックホールです。これはX線観測衛星を打ち上げたからその存在を確認できたのであり、地上からではなかなか見えなかったでしょう。最近では、ガンマ線バースターという、ものすごく強い光のエネルギーの高いガンマ線という光をポッと出して消えてしまう天体がたくさん見つかっていますが、それも、ガンマ線を観測する衛星が打ち上がって初めてその存在がわかりました。このように、宇宙には人間の想像を越えるようなとんでもないことがたくさんあり、やはり宇宙空間にも観測装置を打ち上げることが必然です。
JAXAと国立天文台の関係という点では、今後宇宙空間からの天文学と地上からの天文学は、さらに密接な関係を持つと思います。従来は、国立天文台は地上の望遠鏡を作る係で、旧宇宙科学研究所は衛星を打ち上げる係といった感じでしたが、今後はその関係はもっと複雑で密接になるでしょう。
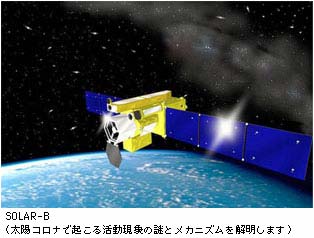 国立天文台の中には、宇宙空間に観測装置を打ち上げたいと思って研究しているグループが既にいくつもあり、当然、JAXA宇宙科学研究本部が考えている今後の観測衛星計画についても、国立天文台とJAXAの研究者が一緒にいろいろな議論をしています。それがなくてはもう日本の宇宙観測は成り立ちません。今後国立天文台でも、衛星を使った宇宙観測をどんどん行うようになるでしょう。過去には太陽や電波の観測で協力をしてきましたが、今後は研究だけでなく、技術開発の協力などでも関係が大きくなると思います。例えばすでに、今度打ち上げる太陽観測衛星「SOLAR-B」の太陽観測用の光望遠鏡のテストは国立天文台内で行っています。大きなクリーンルームを作り、その中でいろいろな光学テストを実際に行っているのです。このように、今後どんどん相互乗り入れが進むことでしょう。 国立天文台の中には、宇宙空間に観測装置を打ち上げたいと思って研究しているグループが既にいくつもあり、当然、JAXA宇宙科学研究本部が考えている今後の観測衛星計画についても、国立天文台とJAXAの研究者が一緒にいろいろな議論をしています。それがなくてはもう日本の宇宙観測は成り立ちません。今後国立天文台でも、衛星を使った宇宙観測をどんどん行うようになるでしょう。過去には太陽や電波の観測で協力をしてきましたが、今後は研究だけでなく、技術開発の協力などでも関係が大きくなると思います。例えばすでに、今度打ち上げる太陽観測衛星「SOLAR-B」の太陽観測用の光望遠鏡のテストは国立天文台内で行っています。大きなクリーンルームを作り、その中でいろいろな光学テストを実際に行っているのです。このように、今後どんどん相互乗り入れが進むことでしょう。
昨年、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所、宇宙開発事業団という大きな組織が一緒になって、日本の宇宙開発・宇宙科学は一元化されました。 |
 |
 |
 |

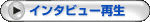
ファイルサイズ:9.2MB
フォーマット:MPEG |
|
しかし正直に言って、トップダウンでの一元化が良かったか悪かったのか。私たちには心配も残ります。必ずしも、日本政府や関係者の、一緒になって更に発展させましょうという一致した方針のもとで統合したのではないからです。行政改革を進める側の頭の中には、どうやってお金を減らそうか、人を減らそうかという発想がほとんどすべてのように思われます。今の日本の世の中全体がそのように動いていて、科学や技術・教育をどうすれば良くなるかは誰も知らない。現場の人は皆頑張ってやろうとしていますが、今真っ先に言われるのは、とにかく一緒になったんだからお金を減らすということのようですね。これでは心配にならない方がおかしい。
これはJAXAに対してだけではありません。国立大学の費用も法人化したから減らすと、財務省は言っています。国立天文台も同じです。大学共同利用機関は国立大学と兄弟分の法人になり、いくつかの研究所が合同で新しい組織を作りますが、するとすぐに費用を減らせというわけです。もちろん、文部科学省は反論していますが。
今、日本はお金がありませんから節約をしなければならないのは分かっていますが、ともかく統合して費用を減らせという発想でいくと、みな萎縮して駄目になってしまいます。大体、気持ちが奮い立たないでしょう。効率化や経済効果の圧力のもとで、日本の科学も技術もどんどん内向きの発想になっていくのを、私は恐れています。
一方JAXAには、一緒になった効果を、科学を長期的に推進するという面でしっかり出してほしいと思います。私たちにもよく分かりますが、一時的には大変だろうと思います。しかし、今まで別々であったがために出来なかったようなことを、一緒になったから推進できる、また、法人になればこれもできるということに実際になると良いなと思います。例えば、宇宙ステーションの利用にも、そういう大胆な面が生まれてくると期待しています。また、一流の科学を自分の手で進めるという宇宙研の良さ、大胆に計画を進める事業団の良さが併わさると、すばらしいでしょうね。単に組織を一緒にしただけでなく、本当に良い結果をもたらせるようになることを大いに期待しています。
|

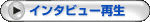
ファイルサイズ:8.3MB
フォーマット:MPEG |
|
Q.天文や宇宙を研究する意義は何だと思いますか?
基礎科学の場合、社会生活にこう役立ちますと言っても、それはたかが知れていますね。むしろ皆さんが面白いと思うかどうか、大きく言えば人類の知的関心に応えられるかどうかが重要です。当然、私たちは新しい発見理解によって、自分たちの住んでいる世界や宇宙が広がっていく、それがとても面白いし大事だと思うから、やっています。それは私たちの大きな喜びですが、同時に一般の人にとっても喜びでなければ意味がありません。私たちだけが面白がっているだけではいけないと思います。世界的にもこういった面白さや成果を社会に返していくという意識が重要になっている中で、日本ではまだこの点では遅れていると思います。私たちの研究は税金でやっていますから、国民がその意義を認めなければならない。私たちがいろいろな努力をした上で、社会がそれを面白いと思ってくだされば良いなと思います。
例えば野辺山の電波望遠鏡は1982年完成ですが、予算は110億円、自然科学のプロジェクトとしては当時日本最大でした。これは国民一人あたり、お年寄りから赤ちゃんまで含めて一人100円という計算になります。100円ずつ頂いてこれだけのことをやりました、ということを国民の皆さんが納得してくれるかどうかが一つのポイントだと、私はよく話したり書いたりしました。100円でこれだけ面白いことが分かったのかと思ってもらえれば良いというか、やる意味があるんだと皆さんが思わなければ、私たちもそれだけの予算を頂くことは出来ないと。同じように、すばる望遠鏡では一人350円ずつ頂いたことになり、私は見学の方々にも「皆さん一人ひとりから“高いコーヒー一杯”分をいただいて、すばるはできたのです」と説明してきました。
これは一つの考えかたに過ぎませんが、私はずっとそういう意識でやってきました。研究者それぞれが、これだけのお金をもらって使っているんだということを意識すれば、面白くて良い成果を出して社会に知らせていきたいという気持ちになります。 |

