
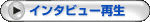
ファイルサイズ:15.2MB
フォーマット:MPEG |
|
Q.国立天文台は「ALMA」など国際協力の大きなプロジェクトを行っていますが、海外からの日本への共同研究への期待は大きいですか。また国際共同プロジェクトを遂行していく上で重視する点は何ですか?
はっきりと申し上げて、日本はまだ国際協力の後進国です。全体的に、国際協力に必要なシステムづくりが遅れているからです。例えば言葉の問題は別にしても、予算の使い方などが日本はとても窮屈です。予算が足りないということだけなく、決まった予算をどう主体的に投入し、プロジェクトの進展に応じてどう有効に使っていけるかという面で、柔軟性がありません。がんじがらめに予算の使い方が縛られています。柔軟性のある諸外国の研究機関と私たちがまともに競争したり、協力する際に一番困るのはその点です。それは、今いろいろ問題になっている法人化によって多少良くなる点であると、私は期待をしているのですが・・・。
日本が諸外国からどれだけ期待されているかという点ですが、これは私たちがどれだけ優れた仕事を出来るかにかかっています。きちんとしたことをやっていれば、自然とお互いに期待し、信頼して対等な立場で協力するようになるのです。そういう意味では、旧宇宙科学研究所(宇宙研)の衛星計画はアメリカ、イギリス、ヨーロッパなどといろいろ協力の実績がありますし、それは非常に期待も歓迎もされています。
信頼という点では国立天文台も実績がありますが、天文学の場合、宇宙研とは少し違います。そもそも「宇宙科学」は国際協力がないと成り立たない世界で生まれたものですが、「天文学」は基本的にそれぞれの国で頑張って研究し、必要に応じて協力をするという世界です。例えば、野辺山観測所では観測に来る天文学者の3分の1は国外の人です。私たちは観測の場を国際的にもオープンにしています。良い人が来て良い観測をしてくれれば、これは野辺山の成果ですから。日本が良い望遠鏡を持っているから彼らは来ます。すばる望遠鏡の場合は、ハワイという外国に作りましたので、野辺山とは違って別のいろいろな難しさはありましたが、やはり日本の望遠鏡であって、海外とは必要に応じて協力をするという体制はもちろん同じです。
一方、ALMAは今までと違って、国立天文台にとっても、科学にとっても新しいジャンプです。もちろん科学の世界では今までも国際協力は盛んでしたが、本当の意味での対等な国際協力というのは、実は世界的にもあまりありません。宇宙研の衛星でもNASAの衛星でもそうですが、たとえ協力をしても、まずは打ち上げ国の衛星なのです。例えば、NASAのハッブル宇宙望遠鏡(HST)はヨーロッパも協力をしていますがアメリカのHSTですし、宇宙研の太陽観測衛星「ようこう」ではアメリカも装置を乗せていますが、これは日本の「ようこう」です。しかしALMAは、どこのものでもありません。ヨーロッパ、アメリカ、日本という世界規模で一緒に協力して作り、共同で経営する初めての「世界望遠鏡」です。
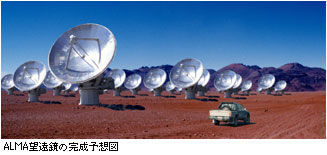 実は、ALMAは、日本が野辺山のミリ波望遠鏡を基礎にして構想した計画が基礎になっていて、並んでアメリカが、そして後にヨーロッパが同様の計画を打ち出しました。私たちのオリジナルの発想が中心に座っていますから、他の国の計画にのったわけではありません。そういう意味でも、アメリカ、ヨーロッパと日本は、基本的に対等な関係を保っています。特に電波天文の分野では日本はミリ波で世界をリードしてきた立場です。大変面白い国際協力の実験ができると期待しています。 実は、ALMAは、日本が野辺山のミリ波望遠鏡を基礎にして構想した計画が基礎になっていて、並んでアメリカが、そして後にヨーロッパが同様の計画を打ち出しました。私たちのオリジナルの発想が中心に座っていますから、他の国の計画にのったわけではありません。そういう意味でも、アメリカ、ヨーロッパと日本は、基本的に対等な関係を保っています。特に電波天文の分野では日本はミリ波で世界をリードしてきた立場です。大変面白い国際協力の実験ができると期待しています。
|

