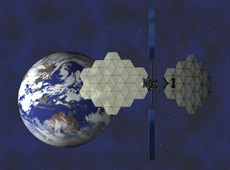Q. JAXAの震災への取り組みに関して、被災地の方たちの反応はいかがでしたか?

超高速インターネット衛星「きずな」

被災地の現地対策本部に設置された「きずな」の直径1mのアンテナ
被災地の方たちからは、非常に役に立ったというお言葉をたくさんいただきました。でも、「JAXAがこういう活動をやっていると事前に知っていれば、被災直後に、もっと早く要望したのに」と言われてしまいました。私たちは、「だいち」等の衛星を使って防災に関わる利用実証実験を行うという協定を締結した地方自治体の方とは、以前から衛星を利用した防災訓練を行っていました。でも岩手県とは、震災前にそのような協定を結んでいなかったのです。そこで、防災訓練を実施する予定で滞在していた新潟県の防災担当の方から、岩手県の担当者にJAXAを紹介していただきました。ですから、私たちの防災活動をもっと広める必要があると思いました。
また、今回はアンテナの設置場所は主に県や市の庁舎でしたが、これからは、より多くの避難所等へ設置したいので、地上アンテナの設置をもっと簡単にして、県の防災課の人たちだけで組み立てから運用ができるようにしてほしいという意見もありました。「きく8号」の地上アンテナは2時間もあればセットアップができるのですが、「きずな」のアンテナはセットアップにも時間がかかります。いずれにしろ、まだ実験用の機器なので、専門家が行かないと組み立てられない仕様になっているのです。
JAXAから数名の専門家が被災地に行き、常駐するとなると、県の職員たちはその対応をしなければならず、それに手間がかかります。もちろん、私たちはできるだけ手間をかけまいとしますが、アンテナの設置場所を用意していただいたり、被災地に向かう高速道路の通行証を手配していただくといったことは、県の方にお願いするしかありません。そういったことがネックになったのでしょうか。こちらから、津波の被害を受けたほかの自治体に電話をかけてみましたが、衛星回線のメリットを理解していただいたにもかかわらず、他に優先すべきことがあり、今はそのために人員を確保できないということで断られたこともあります。
Q. いずれは自治体にアンテナを常備して県の職員だけで通信回線を確保できるようになるのでしょうか?
災害によって交通手段や地上の通信インフラが遮断され、孤立した被災者の方にとって衛星通信は生命ラインになりますので、一刻でも早い対応が求められます。JAXAの「きずな」や「きく8号」は技術実証衛星ですが、将来的にこのような衛星が実用化されれば、やはりアンテナ設置の簡易性は必要になると思います。
昨年の東日本大震災の際には、被災地に電源がなかったため、私たちはアンテナと発電機を持って行きました。また日本の通信会社では、地域ごとに非常用の車載用アンテナを常備し、災害が起きると被災地に最も近いところからアンテナを持っていき、臨時回線をひくといった災害対策を行っています。ただ、インターネット回線の場合は復旧に時間がかかってしまうため、地上局だけ持っていけばすぐに通信ができるというインターネット衛星は、需要があると思います。
Q. 災害時の自治体との連携について、東日本大震災の後に改めて感じたことはございますか?

衛星画像を活用した地方自治体の防災訓練の様子
あらかじめ、自治体の方と防災関連の協定を結んでおくことの重要性を感じました。協定を結んでいれば、防災訓練を通して交流が生まれます。お互いの顔を知っていて、万が一の場合に、電話一本で頼める環境を作っておくことは非常に大切だと思いました。
そこで震災後には、できるだけ多くの自治体と積極的に協定を結んでいます。そして、県の防災訓練に合わせて、地球観測衛星と通信衛星を使った実証実験を行うなど、衛星の使い勝手も見ていただくようにしています。これによって自治体との連携が深まれば、次に災害が起きた場合、JAXAと直接連絡ができる体制ができ、自治体の受け入れ態勢も整うと思います。
Q. 災害時の衛星利用における課題は何でしょうか?
これは自治体の方からも言われたことですが、誰もがパッと見てすぐに分かるようなデータを提供するという点です。解説付きで提供したデータもありましたが、全てがそういうわけではありませんでした。ただ、どこが浸水しているとか、倒壊しているかといった情報は、私たちには判読できず、国や防災関係の研究所や地元の方たちにしか分からないことです。
そこで現在、衛星データ利用における、地域の防災拠点づくりを進めています。地域の状況をよく分かっている人が衛星画像を判読し、画像と一緒に解説文をつけて提供すれば、被災状況を迅速に把握ができます。また、自治体の方がより一層、衛星データを使いやすい環境になると思います。
Q. 災害を予知するという観点での衛星利用はいかがでしょうか?
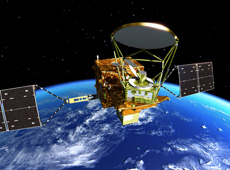
第一期水循環変動観測衛星「しずく」
気象衛星による台風進路の予測は以前から行われていますが、その他の衛星でも災害予知の取り組みが行われています。陸域観測技術衛星「だいち」による観測では、活断層の位置を把握し、地震の研究に貢献しました。また現在軌道上にある準天頂衛星初号機「みちびき」では、波の高さを測る実証実験を計画しています。また、今年打ち上げられる予定の第一期水循環変動観測衛星「しずく」では、雨などの降水量を測定し、洪水予測に貢献が期待されます。
このように衛星を使った災害予防の試みは行われていますが、国内ではまだ、衛星が減災に貢献するには至っていません。一方、東南アジアでは、衛星と地上による観測で洪水を予測し、避難警報を出すというプロジェクトが進められていて、JAXAもそれに協力しています。こちらも、成果が出るのはこれからです。
Q. 防災活動における国際協力は進んでいますか?
2011年5月まで運用していた「だいち」は、JAXAが参加する国際災害チャータやセンチネルアジア等の国際協力により、海外で起きた災害の緊急観測に貢献してきました。海外から災害時の緊急観測の依頼が来れば、ほぼすべて引き受けるというスタンスで協力してきました。一方、昨年の東日本大震災では、海外機関から多くの画像をいただきました。
震災当時、日本には「だいち」しか震災対応の地球観測衛星がなかったため、観測には限界がありました。でも、海外から約5000シーンもの衛星画像を提供していただき、「だいち」が観測できなかった地域のデータを活用することができました。「だいち」の緊急観測によって撮られた衛星画像は約400シーンでしたので、海外から膨大な量の提供を受けたことになります。
Q. 衛星利用の今後の可能性についてどのように思われますか?

衛星は今後ますます使われるようになって、社会のインフラになると思います。今は、通信衛星と放送衛星、気象衛星、アメリカのGPS衛星が主に社会のインフラですが、今後は日本の準天頂衛星もありますし、地球観測衛星も社会のインフラとして定着してくると思います。特に、地球観測衛星は防災のための社会インフラとして大いに期待できます。そのほか、地球環境の監視や海洋表面の観測、農業の分野への利用にも、地球観測衛星は使われるようになっていくと思います。
日本では、2013年度に「だいち」よりも高分解能の陸域観測技術衛星2号「ALOS-2」を打ち上げる予定です。また、「きずな」や「きく8号」の発展型の衛星も考えたいと思っています。衛星通信については、将来的には、普段使っている携帯電話の端末を、災害時にも使えるようにしなければならないでしょう。災害時だけに使うのではなく、平常時に使って慣れている端末を、緊急時にも使うというのが理想だと思います。
JAXAの衛星利用推進センターでは、衛星が私たちの生活に欠かせない重要な社会インフラとしてますます利用されるよう、衛星の精度向上や、データの早期提供、国内や海外における連携および協力を推進していきたいと思います。
JAXA 衛星利用推進センター センター長
1982年、宇宙開発事業団(現JAXA)入社。衛星設計、運用、利用、追跡、宇宙活動全体の企画、国際分野にも従事。2009年よりJAXA衛星利用推進センターにて衛星利用のとりまとめ役としてセンター長を務める。
地殻変動の検出で地震発生メカニズムを明らかに
防災に役立つ衛星による火山活動の把握
地域における衛星利用の拡大を目指して
「だいち」後継機で大規模自然災害に備える